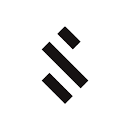語らずして語る、そのストライカー ーー渡邉��千真「THE DAY SPECIAL ARTICLE」
2025年10月22日
|
Article
引退セレモニーのスピーチといえば、往々にして長くなる。何を話すかはもちろん自由だが、多くはこれまでの感謝を伝え、仲間との思い出を振り返り、次のステージへの決意を語る。単なる「区切り」ではなく、選手としての歩みを総括する場でもある。
ましてや、セレモニー自体誰にでも与えられる催しではない。人々の目に焼き付くほどの功績を残し、仲間やサポーターから深く愛された者だけに訪れる特別なものだ。
だから、この日の渡邉千真のスピーチもきっと、想いがあふれ、言葉が止まらないものになると思っていた。プロキャリア17年の節目を迎えるにあたり、語りたいことは山ほどあるはずだと。
だが、サポーターを前にマイクを手にした渡邉が、最後にピッチに残した言葉はこうだった。
「チームとしては優勝して昇格するということはできなかったですけど、しっかり2位に入って昇格条件に入ったので、すごく満足していますし、僕個人としては、今日最後の試合ということで、たくさんの方に応援してもらい、家族にも見守られ、兄弟も来てくれて、本当に素晴らしい一日になりました。本当に感謝しています。ありがとうございました」
ここで拍手が送られた。この日への感謝を、そして今シーズンのチームの奮闘を称えるには十分にあたたかい言葉だった。今度はこれまでのサッカー人生について、多少なりとも触れるのかと思いきやーー
シーン……と沈黙の瞬間が訪れる。どうやら本当にこれで終わりらしい。客席から笑いが起き、会場が和んだ。
わずか1分弱のスピーチだった。涙を見せることもなく、簡潔で、フラットで、抑揚ない語り口。言葉一つひとつに彼なりの誠実さはあったが、17年のキャリアを締めくくる言葉としては、正直物足りないように感じた。
けれども、それこそが渡邉千真らしかった。

関東サッカーリーグ2部・第18節、日立ビルシステム戦。シーズンの幕を閉じる最終節を迎え、渋谷はすでに2位を確定させていた。勝っても負けても順位の動かない、いわゆる“消化試合”だったが、選手たちの表情に一切の緩みはなかった。
それもそのはず。この一戦は、リーグ17試合を戦い抜いた今季の集大成であり、この日の主役といってもいいだろうFW渡邉千真が現役生活にピリオドを打つ、最後のゲームだったからだ。
彼のキャリアについては今更触れるまでもないだろうが、横浜F・マリノスでプロの扉を開き、ヴィッセル神戸、ガンバ大阪、横浜FC、松本山雅FCと渡り歩いた。Jリーグ屈指のストライカーとして名を馳せ、日の丸を背負った経験も持つ。
こうした実績の持ち主が、昨年この渋谷に加入したことはその事実だけで、チームの内にも外にも新たな刺激と驚きをもたらしたことだろう。
それゆえに、このラストゲームに寄せられた期待は特別だった。キャリアの終着点を飾るにふさわしいゴールを、自らの足で決めてほしい。そんなストーリーを、誰もが心のどこかで描き、願っていた。
だからこそ、この日の彼が無得点で終わったのは、理想的な幕切れとは言い難かった。それでもGK積田景介が「シュート練習とかやってても、キーパーの嫌なところを突いてくるというか。一番嫌なところに打ってくるから厄介な選手」と評したその足は、この日もゴールを射程圏内に捉えていた。

サイドや最終ラインから送られるボールに果敢に抜け出し、ゴールを脅かす姿は健在。十八番のポストプレーでも存在感を示し、ひとたびボールを収めればスタンドから「千真が決めてくれ」と期待の視線が集まったのは想像に難くない。
そして後半32分、交代ボードに「39」が掲げられた瞬間、ピッチの空気が一変した。
その直前まで続いていた激しい攻防と歓声が、ふっと静まり返る。両チームの選手、ベンチの面々、そして観客席の隅々に至るまで、視線は一斉にひとりの背中へと注がれた。送られた拍手は「ありがとう」という感謝と、「まだいかないで」という惜別の思い。その両方が入り混じった、温かくも切ない響きだった。
このときピッチインしたFW政森宗治も、偉大な先輩の引退に複雑な思いを抱いていたうちのひとり。政森が幼少期を過ごした兵庫で、当時ヴィッセル神戸に所属していた渡邉と同じポジションを争う。尊敬の対象であると同時に、意識せざるを得ない仲間だった。
「年齢的に今年か来年か、いつ引退してもおかしくなかったけど、引退するのは俺らより早いわけで。だからなんとなくわかってはいたけど、やっぱりああやって(引退発表を)聞くと、なんかこう……すごい人と一緒にやれていたんだなって思う。
でも俺は忖度とか何もなくて『千真くんより点を取る』『千真くんからスタメンを奪う』っていう自信を持ってやってた。ただ、自主練とかシュート練習のときはやっぱり上手いからお手本にはしてたし、仲間としていろいろ味わえたことは良い財産だった。ライバルとしてやれた嬉しさ、寂しさ、いろんな感情がある」

引退試合から3日後の10月1日。あの77分間を振り返り、引退後の渡邉の口から出てきた言葉はあっさりしていた。
「もう終わったか、って感じだったね」
ピッチを離れると、一転して穏やかになり、言葉数も少なくなる。こちらが問いを重ねなければ多くを語らないタイプだ。だからこそ、この短い一言の奥にあるものを知りたくなった。
続けて、「『もう終わったか』とは?」と尋ねた。
「やりきった。ほっとした。寂しいとかはない、別に。でもチームメイトのみんなが寄ってくれて花道を作ってくれたじゃん。それがもう、嬉しかったね。相手チームには時間をかけてしまって申し訳なかったけど、ありがたかった。あのときは時間が経つのが早かったし、あっという間だった。楽しかったし、もっとやりたかったな。いつも以上に試合に出たのに、いつも以上に短く感じた」
そう感じられたのは、やはり最後の試合だったからだろうか。サッカーに限らず、「終わり」という瞬間には、どうしてか「あっという間」という感覚が同居するものだ。渡邉もまた、例外ではなかったのだろう。
試合前日の練習後の取材では、「一日一日、寂しくなるなという思いはありつつも、そんなに普段と変わらず。(試合が)終わってからどんどん実感が湧くのかなあ……」と、特別な高揚や感傷を見せることはなかった。
心の内までは完全に見せないが、かといって無理に平静を装っているわけでもない。いつもと同じようにチームメイトと談笑している姿を見ると、「本当に明日が最後なのか」と言いたくなってしまうほどの通常運転だった。
その心持ちは試合当日も変わらなかった。あくまで長年積み重ねてきたその延長線上に、“最後の一日”があったことを物語っていた。
「『明日で終わりか』と思って寝られないのかなと思ったけど、すんなり寝れた。11時キックオフなんてここ最近はなかったし、しかも遠い会場だったから『朝早いな~』って。そんな中でも目覚めもよくて、なんなら嫁とかが全然起きてこなくて、『行くぞ!』って逆に俺が起こしに行ったくらい」

波打ち立てないそのメンタリティは流石だが、ラストゲームで得点を挙げられなかったことについては、やはり悔しさも残っていたようだ。苦笑いを浮かべながら、こう振り返る。
「『点取れよ』って自分にも言い聞かせてたし、チャンスもあったけどダメだったなあ」
自分自身への期待と、少しばかりの諦め。そして、自らの限界を感じ取っているかのような窮屈さが入り混じる。
そう言うのも無理はない。今シーズンの個人成績を見れば、その背景がおのずと浮かび上がる。出場数は18試合中10試合、平均出場時間は15.6分。得点数もわずか1にとどまり、数字だけを見れば満足のいくシーズンとは言い難かった。それを当の本人が痛いほど分かっていたからこそなのか、自分の数字なんて、もはやうろ覚えだった。
「(今年は)何試合出たんだろうね?途中出場が多かったけど、試合に絡んだのだって半分ぐらい。周りからは『まだまだできるよ』って言われてたけど、自分としてはもう本当にきつかった」
引退については、シーズン開幕当初から「リーグ戦まで」と区切りをつけていたという。上位カテゴリーの結果次第では12月に関東1部昇格を懸けた入れ替え戦が控えているが、残り2か月続く厳しいトレーニングに身を置くより、潔くピリオドを打つことを選んだ。その決断は、クラブスタッフらの慰留にも揺ぐことはなかった。
「身体がボロボロになるまでプレーしたり、試合にまったく絡めないまま引退するよりも、プロとして、選手としてのパフォーマンスを出せるのは今年までかなという感覚が、自分の中にあったのがまずひとつ。
あとは、Jからこの社会人のカテゴリーに移ってきて、やっぱり『心技体』がしっかり揃っていないとやっていけない環境の厳しさを、ひしひしと感じていた。今年で(渋谷に加入して)2年目になってこの環境には慣れてきたけど、年齢を重ねるにつれてきつくなってきて。夏場の練習なんかは『もう無理だな』って思うこともあったし、メンタル的にも結構厳しかった」

アスリートとしていずれ訪れるであろう、“その時”というのはなんとも突然で悪戯だ。もっと彼のプレーを見たかった人もいただろうし、あの引退試合で90分間の勇姿を見届けたかった人も少なくないはず。もう一年現役を続けていたら、いったいどこまで我々を魅了させていたのだろうか。
こうして不用意に「もしも話」を並べても仕方ないのだが、こう言いたくなるのもわかってほしい。なぜならば、彼は一人の人間として、そして一サッカー選手として、感嘆せざるを得ない姿勢で評価されてきたからだ。
「『調整したい』『コントロールしてくれ』ということは一回も言われなかったので、彼のために一回もトレーニングの強度を考慮したことがなかった」
増嶋竜也監督がこのように賞賛するほどに、今年で39歳を迎えた渡邉は若手に引けを取らない姿勢で、日々のトレーニングに打ち込んでいた。
同じ美容院仲間だという積田も、その姿を間近で見てきたその一人だ。
「引退発表したけど、『来週の練習も来るでしょ?思わせぶりでしょ?』って言いたくなるくらい、普段の練習でもプレーを見ていてもずっとできそうな感じはあったから『おおっ……』と思った。うちの練習って結構キツいし大変だけど、もう食らいつくとかじゃない。引っ張ってもらっているくらい」
実際に、当の本人も冗談半分に「ちゃんと俺、やってたからね?」と胸を張る。

かくして今日の彼があるのは、渋谷の仲間たちの存在が大きいという。なかでも名に挙げたのは、選手会長であるMF水野智大のこと。2人は普段からウォーミングアップで組むことが多い常連のペアで、思い返せば引退試合の日もその相棒だった。
「あいつもしょっちゅう足を痛めてて、それを抱えながらもプレーする姿を俺も見てた。みんなのこともそうだけど、トモ(水野)のことは尊敬してたね。弱音を吐かずに、仕事もサッカーも両方ちゃんと全力でやる姿を見てたから、俺はまだまだやめられないなって」

そして話はさらに遡る。聞かずにはいられない、渋谷で過ごした日々のこと。覚えているようで、どこか遠く霞む思い出を、記憶の引き出しから取り出すように語ってくれた。
「懐かしいね。1月31日だったかな。ずいぶん前とかじゃないね。昨日のような感じ。最初の練習参加で高井戸公園に行ったのは覚えてるね。みんな真面目で、練習に取り組む姿勢もちゃんとしてるんだなって良い印象があって。それで『ここに入ろう』って思えたから。
なんかその時に誰だったかなあ……トキ(政森)だったかな?トモ(水野)だったかな?フィジカルトレーニングのときに、『千真さん、いきましょう!』って声をかけてくれたのをすごい覚えてる」
その何気ない一言は、チームに受け入れられた実感を与えたのだろう。その場面を振り返りながら語る渡邉の表情はふっと和らいだ。
試合の行き帰りの車内では自宅が近いというDF陣の鈴木友也や山出旭、MF佐藤蒼太を送迎するのが常だったという。後輩たちを乗せた車内は、いつも賑やかで騒がしかった。
「結構面白かったよ。旭のおかげでBAD HOPも覚えたよ。全然知らなかった。ああいう系、みんな好きなんだよね。(青木)友佑とか蒼太とか結構好きみたいで。意外でしょ?若いやつは今そういう、なんか、ヒップホップ系?なのかなと。
あと(植松)亮は試合前はバラードを聞きたいらしくてロッカーにいたくないらしい。旭がいるとガンガン流すから。バラード系で落ち着かせると気持ちが上がるんだって。変わってるよね、それも」
自信なさげに、ところどころ確認しながら話す渡邉。ひと回りも年下の彼らを語るその姿は、まるで父親のよう。
「でもいい刺激になったね。逆に若いやつらが、そういう音楽とかもそうだし、プライベートはどんな感じなのかって、いろいろ話を聞くと、自分も若く見えるっていうか。良い意味でポジティブに捉えて取り入れたりしてた。自分が知らないことを知ってたりしたら面白いから」

もっとも、加入してからの毎日が充実感で満たされていたわけではない。Jクラブのように潤沢な環境や資金が整っていないだけに、不自由を感じる場面も少なくなかった。たとえばリーグ第6節・EDO ALL UNITED戦もそのひとつ。
試合前から小さな森の家フィールドは雨風にさらされ、ピッチは水たまりだらけ。この日メンバー外だった渡邉は、スタッフや他の控え選手と共に、グラウンド整備に汗を流した。
「あの時は正直、『俺、何やってんだろう?雨降ってるのにもういらないでしょ!』って思ってたよ(笑)でもスタッフの人もほかのメンバー外の選手もみんなやってたし、自分だけやらないわけにはいかなかった。あの時とかマジしんどかったな。でもあんなの初めてだから良い経験をしたよ。全部プラスに捉えてやっていたね」
「ははっ」と思い出し笑いを浮かべるその表情には、与えられた環境を素直に受け入れる柔軟さがあった。新しい当たり前を受け入れ、その新鮮さを楽しんでいた。

「いろんなご縁があって、ここ(渋谷)に来て。最初は環境の違いに、いろんな苦労したこともあったけど、チームメイトだったり、スタッフだったり、いろんな人との新たな出会いがあった。そういった環境を与えてもらえたっていうのも単純に嬉しいし、感謝してます。
なんかみんな渋谷愛が強いのか、このクラブのために頑張る姿勢とかマインドを持ってるから、めちゃくちゃいいチームだね。同じ目標に向かって頑張ってる集団なのかなっていうのはすごく感じた。ここにやっぱり来てからじゃないと感じない経験もできたから、本当によかった」
このクラブで過ごした2年間は、キャリアの終盤という言葉だけでは片付けられない意味をもっていた。環境の新鮮さよりも、それ以上に、仲間との関係の近さや、サッカーを純粋に楽しむ空気が心地良かったのだ。

こうして渋谷での総括を聞いたところで、最後にひとつだけ、少し抽象的な問いを投げかけた。プロキャリア17年、7歳からボールを蹴り始めてから数えれば実に32年にわたってサッカーと共に過ごしてきた彼に対してなら、こうぶつけても構わないと思った。
「これまでのサッカー人生を、ひと言で表すとしたなら?」
渡邉は「いやー、難しいなあ」と困り顔になり、ほんの少し考え、言葉を選ぶようにして答えた。
「サッカーは人生そのもの、だったね。本当にサッカーから離れることはなかったし、サッカーを中心として生きてきたから。人生そのものだし、自分らしくいれる。サッカーやってる時って一番楽しいし、夢中になれるし、どんどん上手くなりたい、強くなりたい、上目指したい、そういった目標や欲が出てくるから。サッカーのおかげで成長できたし、生きてきてこられたんだなって思う。だから人生そのものなんだなと」
言葉に力を込めるわけでもなく、事実を並べるような口調。今度は「いやー」と笑みを浮かべて続ける。
「こんな39歳のおっさんになっても、勝った時とか点入った時にあんなに喜ぶことないでしょ、もう。大人になって悔しがったり、ましてや泣いたりするかどうかわからんけど、抱きついて喜んだりすることなんかない。そこがやっぱりサッカーのすばらしさじゃないかなって思います」
そう自らを「おっさん」と口にするお茶目なところもまた可愛いらしい。政森が「オンオフ変わらない人。天然なのかボケてるのかわかんないもん。でも面白いし、良い人だよ」と語っていた意味もわかる気がする。

そして話は、自然と“あの頃の自分”へと向かう。いや、正確にはいまの彼とも重なるように思える。それは渡邉千真という「人となり」について。
「Jにいたときに、自分の中でも『もっと熱くならないといけないな』と思ったことはあったし、『もっと喜怒哀楽を出せ』って言われたこともあった。自分よりエゴを出してるFWだって見てきたし、『俺もああなったらもっと点が取れるのかな』とか『上に行けるのかな』とか思ったりしたこともあったけど、性格上良い意味で変わらないので。これが俺なんだろうなっていうところもある。
でも試合にも使えてもらえなかったら、めっちゃ悔しいしイライラすることもある。まあ、それはFWとか関係ないか。サッカー選手としてはそこはやっぱり思ってたし。いくら年齢を重ねてもそこは譲れるところじゃなかったね。
叶えられなかった夢はいっぱいあるけど、小さい頃からの夢だったサッカー選手になれて17年やってこられたから満足してます。欲はいっぱいあるけど、自分のキャリアには誇りをもってる。『よくやった』と言いたいですね、自分に」

穏やかな笑みを浮かべながらその表情には安堵があったが、感傷や達成感に浸るわけでもなく、最後の最後まで淡々としていた。
だが、それこそが彼の強さなのかもしれない。勝負の世界にいれば、もっと強く自己主張をする選手のほうが光を浴びやすい。それでも彼は自分をブラさないことで信頼を積み上げてきた。飾らず、誠実で、ひとたびピッチに立てば確実に仕事をこなす。17年間、息を長くしてピッチに立ち続けてこられた理由はそこにある。
「でもこれだけ選手としてサッカーやってきたから、それが抜けるっていうのは、心にポッカリ穴が開いたような感じ。今日の時点では次は何をするかまだ決まってないから、『どうしよう』っていう不安はもちろんある。
けど、まだ決まってないだけに『何をやるんだろう』っていうワクワク感とか、自分に対しての期待感もある。半々かな」
であれば、最後に送りたいのは「よくやった」と終わりを告げる労いではない。その背中を、これからも突き動かすような、鼓舞の拍手を送りたい。事の大小はさておき、新たな挑戦へと踏み出せるように。

「39番、39歳。たまたまだけど、揃ってるよね。キリいいし。来年から40歳だし、また違うセカンドキャリアが始まるからよりいいじゃん」
こうして振り返ると、あのスピーチもあれでよかったのかもしれない。言葉を尽くさずとも、彼の生き方そのものがすでに雄弁だった。
言葉の続きはこれからの人生で語られるはず。そのとき、どんな表情で、どこで、何を見ているのか。
それを確かめる日が、きっとまた来る。
取材・文 :西元 舞
写真 :福冨 倖希
企画・構成:畑間 直英
SHIBUYA CITY FC
渋谷からJリーグを目指すサッカークラブ。「PLAYNEW & SCRAMBLE」を理念に掲げ、渋谷の多様性を活かした新しく遊び心のあるピッチ内外の活動で、これまでにないクリエイティブなサッカークラブ創りを標榜している。
渋谷駅周辺6会場をジャックした都市型サッカーフェス「FOOTBALL JAM」や官民共同の地域貢献オープンイノベーションプロジェクト「渋谷をつなげる30人」の主宰、千駄ヶ谷コミュニティセンターの指定管理事業など、渋谷区での地域事業活動も多く実施している。
お問い合わせ
担当:畑間
問い合わせはこちら