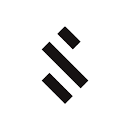憧れた側から憧れられる側へ。ひたむきな努力が導く、まっすぐな未来ーー大越寛人【UNSTOPPABLES】#13
2025年6月5日
|
Article
「結局プロになってる人って、子供たちから『こういう人になりたい』って言ってもらえてる人が多いじゃないですか。今度は僕が、子どもたちから尊敬されて、憧れてもらえるような人になりたいです」
大越を取材するのは、これが2回目だった。初めて彼を取材したときは、まだ加入して間もない頃で、どこかよそよそしくて静かな印象だった。とにかく真面目な選手だなというのが第一印象で、その奥行きをもっと知りたくて、今回もう一度話を聞いた。取材を終えて改めて感じたのは、やっぱり彼は誰よりも真面目で、その姿勢こそが最大の魅力だということだった。
【UNSTOPPABLES~止められない奴ら~】
昨シーズン、関東2部への昇格を決めたSHIBUYA CITY FC。その栄光の背後には、ただの勝利以上のものが隠されていた。選手たちの揺るぎない自信と勢いは、彼らの人生に深く刻まれた歩みから来ている。勝利への執念、それを支える信条。止まることを知らない、彼らの真の姿が、今明らかになる。
第13回目は、控えめで自己主張は多くないが、誰よりも純粋かつ、熱い信念と夢を持つ大越寛人に迫る。
大越寛人(おおこし・ひろと) / DF
埼玉県川口市出身。2000年9月19日生まれ。168cm、63kg。上青木サッカー少年団からFCアビリスタ、グランデFCと地元・埼玉で育ち、高校はサンフレッチェ広島ユースへ。3年時には、JFA U-18サッカープレミアリーグ2018ファイナルで、日本一を経験。その後桐蔭横浜大学に進学し、出場機会こそ限られたものの、確かな実力から卒業後は当時J3のY.S.C.C.横浜に加入。2年目で契約満了になり、今季からSHIBUYA CITY FCに加入。粘り強い対人守備と、右サイドを駆け上がる攻撃の起点となるプレーの両面で、チームに勢いをもたらす。
自由より、夢を選んだ
幼い頃からずっと胸にあった、「プロになる」という夢。その思いが一層強く、現実味を帯びたのは、中学生の頃だった。静岡県・時の栖で行われた大会に参加した際、サンフレッチェ広島ユースの姿を目にしたのがきっかけだった。
「当時のトップチームの監督は森保さんで、広島はJリーグで二連覇中でした。めっちゃ強くてかっこいいなって思っていました。バスから降りてくるユースの選手たちも、他のチームとは雰囲気が違ったのを覚えています」
プロに近づくためには、高体連ではなくJクラブの下部組織に入るのが最短ルート。そう考えていた彼にとって、進むべき道は明確だった。特別、広島ユースへの強いこだわりがあったわけではない。だが、ユースで勝負したいという気持ちが人一倍強く、高体連は最初から選択肢に入っていないことも周囲にはっきりと伝えていた。
そんな中、複数のクラブの中で一番早く声をかけてくれたのが広島ユースだった。プロ輩出率の高さも決め手となり、迷うことなく決断した。
その後飛び込んでみて感じたのは、サッカーへの意識の高さ、そして環境の厳しさ。どれも、その実績に見合うものだった。
「寮生活では携帯を回収されるのがルールだったんです。絶対学校に持って行ってはいけない決まりだったから、毎朝寮に預けてから登校してたんです。6時起床で、朝は10分くらいしか触れなかったけど、その時間に携帯を触るならその分寝ていたいなって思って、そんなに見てなかったかもしれないです。夜も8時か9時前までしか使えなくて、9時半に回収されていました。
チームの伝達事項も、寮のホワイトボードに書かれてあるんです。だから別に携帯を触る必要もなかった。遠征のバス移動でも、夜11時に出発して翌日の朝到着するんですけど、そこでも『夜は寝るだけだから、もういらないでしょ』って言われて回収されていましたね」
そのような厳しいルールに加えて、生活環境そのものも自分を律するには十分だった。
「周りも本当に田舎で、遊ぶような場所なんてなかったです。市内に出るには歩いて片道1時間半かかるし、タクシーを使っても15分はかかる場所だったので、気軽にどこかに行くこともできませんでした」

そんな閉ざされた日常の中で、唯一の楽しみといえば、昼と夜の食事が提供されない、月曜日のオフ。この日だけは仲間たちと市内まで足を運ぶことができた。
「でも往復2000円くらいかかったから、高校生の自分たちには痛い出費でしたね。しかも市内に出ても何もないから、美味しいご飯を食べるくらい。オフの日の門限は夜9時で、ギリギリまで遊べたとしても、それくらいしかできなかったです」
とはいえ、そのオフの日以外も自由のない日々だった。
「学校の授業は7限まであって、寮に帰れるのが夕方の5時。門限は7時だったので、自由に使える時間は2時間しかなかったんです。しかも、弁当箱は5時半までに寮のキッチンに返却しないといけない決まりがあったので、本当に何もできなかったですね」
サッカーに打ち込む以外の選択肢はない生活。でも、だからといってそのサッカーの日々が順風満帆だったわけではない。
1年時は、ユース全体でおよそ30人弱のメンバーが在籍していたが、その中で大越は公式戦に登録されない、メンバー外の5人のうちのひとりだった。そのためBチームの一員として、プリンスリーグの試合に出場。地道に努力を重ねた末、2年時からは上のカテゴリーに関わるようになった。
「練習が終わっても、最後まで残ってボールを蹴ったりするのは当たり前。寮からグラウンドまでは、すごく急な坂があって何キロか距離もありました。他のみんなが自転車で行く中、僕はなるべく走って行っていたんです」
プロになるために、派手な近道なんて存在しない。地に足をつけ、やるべきことをひとつずつ積み上げていくしかなかった。

先ほど挙げたように、私生活においても自由がないぶん不便なことは多かった。けれど、その生活は苦ではなかった。
「23時就寝って決まっていて携帯を回収されていたけど、みんなと話す時間が楽しかったし、結局ケアする時間も必要だからなって思ってたんです」
そしてなにより、制限があったなかでもそれを自然に受け入れられたのは、根底にある揺るがない目標があったからだ。
「本当にサッカーだけに集中できる環境だったんです。だから僕はサンフレを選びました。今だったら、携帯なしの生活なんて無理だなって思うけど(笑)でも当時はプロになることしか考えてなかったから、全然苦じゃなかったし、それが当たり前でした」
練習参加の時点から、練習生であっても携帯は回収されていた。つまり、厳しさは最初から知っていた上での選択だった。
「覚悟はしていたけど、それでもすごくきつかったですね」
そう言って、どこか懐かしむような苦笑いを浮かべながら続ける。
「今思うと、よくやってたな……。アントラーズもきつそうな話はよく聞きますけどね。でもこれをみんなに話すと、『そんなルールあるの?』って驚かれることが多いです。やっぱりユースでも、ここまでの環境はなかなかないよなって思います。もし高体連に行ってたら、どうなってたのかな?」
ユース全体の中でも、特に厳しいとされていた当時の環境。それでも大越はその時間を少しも否定しない。むしろ、「一番成長できた」と迷いなく言い切る。削ったものの大きさを超えるほど、充実した3年間だった。
伝える力を育てた日々
桐蔭横浜大学卒業後、Y.S.C.C.横浜(以下YS)に加入が決まった大越。プロとしてのキャリアをスタートさせた彼は生活費を稼ぐため、週に3回、コナミのサッカースクールでアルバイトをしていた。そこには後に渋谷で共に戦うことになる、チームマネージャーのてんてんこと、角野天笙も同じく働いていた。
「渋谷に加入する前から、てんてんからは渋谷の話をよく聞いてました。YSを退団することになったときも、てんてんから『チームの雰囲気も良いし、ちょうどウイングバックの選手が抜けたからどうですか?』って声をかけてくれました」
サッカースクールでは、幼稚園児から小学生までを対象に、サッカーの指導だけではなく、自身の得意分野であった器械運動も教えていた大越。
とはいえ、それが彼にとって初めての仕事だった。真面目で大人しい性格ということもあり、最初はかなり苦戦したという。
「幼稚園生の子たちは、まずちゃんと並ぶこともできないんです。並んでもすぐどこかに行っちゃったりして。だから『みんな電車に乗ろう』って例えて言うと、楽しそうに来てくれるんです。『丸いの落ちたら食べられちゃうからね』とか言って。でも電車って言っても、結局どこかにいっちゃう子もいるんですけど(笑)。
あとはなんでかわからないんですけど、同じ年齢でも体操よりサッカーの子の方が言うこと聞かないんです。特に月曜日のサッカーの子たちは大変でした。これはてんてんに聞いても同じことを言うと思います(笑)サッカーの方はマジで苦労しましたね」
中でも特に手を焼いたのは、1~3年生の低学年の子どもたち。何度注意をしても、とにかくまとまりがなかったという。
「人間性を育てるのも仕事の一環でした。騒がしい子たちばかりに目を向けていると、全体の練習が進まない。なのでちゃんと話を聞いてくれる子を中心に教えていたら、他のコーチに『なんでそのまま続けるの?親から見たら見捨ててるように見えちゃうから、それはだめだよ』って怒られたことがあります」
加えて、気を配るべき相手は子どもたちだけではなかった。
「保護者の方たちも見てるから、あまり強く怒れなかったんです。他のコーチの人はそのあたりを気にせずビシッと言えるんですけど、俺は練習が終わったら、保護者へのフォローもしに行かないといけなくて。一人ひとりのお子さんの様子を見て、『今日はどうでしたか?』『こんなプレーができたので、こういうところをもう少し練習すると良くなると思いますよ』って言う感じで声をかけていました。クレームが来ないように、伝え方にはすごい気を付けました」

さらに通っている子供たちの中には、韓国や中国、ヨーロッパ系など、さまざまな国籍の子もいた。日本語が通じない子には、身振りや手振り、表情で伝えていった。
「もう、子供たちに合わせるしかなかったです。自分もバカになって、一緒にはしゃいで。最初は他のコーチから『もっと崩していいよ』って言われて戸惑ったんですけどね。お手本を見せるときも、どうやったら笑ってくれるか、やる気になってくれるか、いつも考えていました。そうじゃないと、子供たちもやりたくなくなっちゃうので。言葉遣いとか、ちょっとふざけてみたりとか、だいぶ意識していましたね。大変だったけど、良い経験になりました」
子供たちと真剣に向き合う中で、伝える力と寄り添う姿勢を、プレーとはまた違ったかたちで育んでいった。コーチとしての経験は、のちに彼が理想とする選手像へとつながっていく。
背中を押してくれた言葉、支えてくれた人
スクールでまた違った経験を積んだ大越だが、それまでの生活の裏には、プロを目指すものとしての葛藤を抱えていた。
「YSに入る前も、クラブからは『大卒の選手にはお金をほとんど出せない』と言われていて。当時はJ3のクラブだったから当然なんですけどね。だから、流石に社会人1年目でそれだけで生活するのは正直かなり厳しいなって思ってました」
就職活動もしていた大越には、一般企業からの内定も出ていた。その企業はプロを目指す彼の気持ちを理解し、応援してくれていた。
「『プロになれるならなっていいよ』って言われてて。もしプロになれなくても、そういう人のほうが、絶対結果を残そうっていう意志が強いから、歓迎するって言ってくれていたんです」
両親にも自身の思いを伝えた。返ってきたのは「やるならやっていい」と、全面的にサポートするという後押しだった。
そしてもうひとり、彼の決断に大きな影響を与えた存在がいた。交際していた彼女だ。
「『サッカーしているところを見たい。そこはサポートするから』って言ってくれて。彼女も高校までサッカーやってて、大学もオファーもらってたくらいバリバリやってたんですけど、怪我で辞めちゃったんです。そしたら彼女が、『私は中途半端に辞めたことを今でも後悔している。だから、あなたには後悔してほしくない。サッカーが好きなら続けてほしい』って言ってくれました」
そんな言葉に背中を押されながら、家賃の一部を親と彼女に支援してもらい、あとは生活をやりくりして生活していた。
「なんとかそれで生活していましたね。今でも本当に支えてもらってるなって感じます」
そして渋谷に加入する前にも、YSで契約満了になった大越は、また大きな決断に直面していた。
「ちょうど(小関)陽星も藤枝で契約切られてたから、ふたりで『これからどうする?』って話していたんです。陽星とは大学が一緒だったから、桐蔭の蹴り収めのOB会に行って、いろいろチームを紹介してもらおうって」
その流れで、大越は渋谷の因縁の相手でもある、EDO ALL UNITEDの関係者を紹介してもらい、練習参加にも行った。評価は高く、オファーも後々出したいと言われた。
「たしか1月の下旬くらいのことだったかな?そしたらすぐ渋谷からもオファーが来たんです」
気持ちは渋谷に傾いていたが、これまで動いてくれた分、EDOにも誠実に対応しなければいけなかった。
「だからちゃんと『渋谷に行きます』って伝えたんです。そしたら『じゃあ今正式にオファーを出す。こういう条件だけど、どうする?』って聞かれて。でも僕が『渋谷の方が……』って言ったら、どんどん条件を上げてくれたんです」
大越に提示された待遇は相当手厚いものであった。報酬や設備ーーいずれもこれまでサッカーだけに打ち込んできた彼にとっては、十分魅力的な条件だった。
「『今なら即決できる』って言われたんですけど……そのころ、陽星はすでに渋谷に入ることが決まっていて。そしたら陽星から、『また一緒にサッカーしたい』って言ってくれて。今後の自分のキャリアを考えても、やっぱり渋谷だなって思って決めました」

そのほかにも決断を後押しする要素はあった。以前渋谷に所属していた佐藤海斗と知り合いだったこともあり、渋谷の存在はもともと気になっていた。
「実は去年の小机であった関東昇格戦、僕もちょっとだけ見ていたんです。EDOに知り合いがいたから、そっちの準決勝を観に行っていたんですけど、その後が渋谷が出た第2試合で。スタンドから見てて、『東京都1部のチームで、こんなにサポーターがいるんだ』って驚いたのを覚えています」
新たな歴史が刻まれつつあったあの日、大越も同じ場所にいた。ただ、その時の彼はまだ外からその景色を見つめていた。だが今は、渋谷でプレーすることを選んでくれた。
そしてこの選択がいつか、自分にとって正しかったと胸を張れるように、大越は進み続ける。
夢はまだ終わっていない
そんな素直でひたむきな大越には、今も支えになっている言葉がある。中学時代、部活動への入部が義務づけられていた彼は、体力をつけるために陸上部に所属していた。そこで、ある言葉と出会う。
「”努力に勝る天才なし”って、ずっと言われていたんです。もともと速く走れる天才もいるけど、結局は努力すれば勝てるよって。天才だって努力しなかったら伸びない。成功している人は、やっぱり何かしら努力をしてると思います」
幼い頃から必死に夢を追いかけ、地道な努力を積み重ねてきた彼に、この言葉は心に沁みた。
そしてもうひとつ、大越の中で強く残っているのが、リオネル・メッシの言葉だ。
”努力すれば報われる?そうじゃないだろ。報われるまで努力するんだ"
「ほんと……そうだなって思います。努力しても報われないことはある。でも、努力せずに成功した人はいない。努力して報われなかった人もいるかもしれないけど、成功している人はみんな努力している。
だから僕も『やらないと』ってずっと思っているんです。学生時代も最初はずっと試合に出れない状態からスタートしたので。だからこそ、その努力の部分を大切にしています。努力、好きですね」

簡単に諦めない姿勢。何度も壁にぶつかっても、コツコツと積み重ねてきた時間。では、そこまでやり続けられる原動力は、一体どこから来ているのだろうか。
「プロになるには、まず試合に出なきゃダメ。プロの人でさえ、めちゃくちゃ努力しているじゃないですか。
高校時代のとき、トップチームと試合する機会があって。そのときに感じたレベルの高さもそうだけど、練習前後の取り組み方を見て、プロでもこんなにやってるんだって驚きました。全体練習が終わった後にも走ったり、自主練も時間ギリギリまでやったり。練習の1時間前にはグラウンドにいるのが普通って、トレーナーさんからも聞いて。そこから自分の意識も変わったんです」
そして何より、そんな環境のなかで大越の目をさらに開かせたのは、現在Jリーグや海外で活躍する同期や先輩。中野就斗、東俊希、大迫敬介(サンフレッチェ広島)、山田新(川崎フロンターレ)、満田誠(ガンバ大阪)、川村拓夢(RBザルツブルク)など。錚々たる顔ぶれの中でも、大迫敬介の姿勢は特に印象に残っている。
「大迫選手は常に筋トレルームにいましたね。練習が終わって、自分が片づけしてシャワーを浴びて帰ろうとしたときも、まだ一人で黙々とトレーニングしてて。『え、今もやってるの?』って。その時からやっぱり流石だなと思いました」
本気で何かを目指す人間の背中ほど雄弁なものはない。大越はそれを目の前で見てきた。そして自分自身に問い続ける。
「YSの時にJ1のチームと練習試合をして、ある程度通用する手応えはあったんです。でも自分に何が足りないのかっていうことは、ずっと考えてます。だから大迫選手みたいな選手を見ると、『そりゃ成功するよな』って思うんです」
だからこそ、大越は自分に対して正直だ。
「あそこまでやりきれなかった自分は、すごく弱いです。やっているつもりになっていただけで、あれじゃ全然足りてないんだなって。あの状態でプロになりたいって言ってたのか、って思いますね」
そう語る大越の言葉には、過去への自分への悔しさと、同時に、それでも前へ進もうとする覚悟がある。
「たしかに、俺は他の人と比べたらあまり主張するタイプじゃないかもしれない。でも、サッカーの時は声を出すことを意識しています。これは高校のときからずっと言われてきたことなんです。やっぱり集中すると無言になりがちで、自然と声が減ってしまうんです。今もマスさん(増嶋 竜也監督)に指摘されていますよ(笑)YouTubeのINSIDE CAM、成城大学との試合の回を見てください。あの時もめっちゃ言われてましたから」

そう言って笑うが、そこに照れはない。自分に足りないものを受け入れ、改善しようとする姿勢は変わらない。
「でもそういう指摘があるたびに思うんです。もっと、もっとやらないといけないなって」
プレー中の大越といえば、派手さはないが右サイドを何度も上下動し、少しずつ試合の空気を変えていく。サッカーをよく知る人ほど、彼の存在価値を感じるだろう。いわば玄人好みのプレーヤーだ。
「自分の中で、理想としているプレーが続けて出せるときは、いつも以上に集中できます。自分がやりたいと思っていることを、どれだけ遜色なくできているか。そういうところでゾーンに入る感覚があるんです。
だから、誰よりも一番走って、チームを引っ張りたい。どれだけきつい時間でも、『こいつがまだ走ってるなら、俺もついていかないと』って思われる存在になりたいです」
そして彼が目指すのは、ただ上手い選手になることではない。その先にある、人としての在り方だ。
「YSのときも、子供たちから応援されてる選手を見て、純粋にいいなって思ったんです。結局プロになってる人って、子供たちから『こういう人になりたい』って言ってもらえてる人が多いじゃないですか。自分もスクールで教えた経験があるので、今度は僕が、子どもたちから尊敬されて、憧れてもらえるような人になりたいです」

幼い頃に抱いた夢は、大人になるにつれて形を変えることがある。現実の理想の狭間で折り合いをつけながら、自分なりの落としどころを見つける人も多い。
だが、大越は違う。愚直に、まっすぐに、今もその夢に向かって走り続けている。その姿は、必ず誰かの心を動かすだろう。かつて誰かに憧れたようにーー今度は、自分が憧れられる存在になるために。
取材・文 :西元 舞
写真 :福冨 倖希
企画・構成:斎藤 兼、畑間 直英
UNSTOPPABLES バックナンバー
#1 渋谷を背負う責任と喜び。「土田のおかげでJリーグに上がれた」と言われるためにーー土田直輝
#2 頂点を目指す、不屈の覚悟。全ては世界一の男になるための手段ーー水野智大
#3 冷静さの奥に潜む、確かな自信。「自分がやってきたことを発揮するだけ、『去年と変わった』と思わせるために」ーー木村壮宏
#4 這い上がる本能と泥臭さ。サムライブルーに狙いを定める渋谷の捕食者ーー伊藤雄教
#5 問いかける人生、答え続ける生き様。「波乱万丈な方へ向かっていく。それがむしろ面白い」ーー坪川潤之
#6 サッカーが導く人生と結ぶ絆。ボールがくれた縁を、これからも。ーー岩沼俊介
#7 楽しむことを強さに変えて。夢も、欲も、まっすぐに。ーー小沼樹輝
#8 誰かのために、笑顔のために。誇りと優しさが生む頂点とはーー渡邉尚樹
#9 九州で生まれた男の背骨。「やっぱり男は背中で語る」ーー本田憲弥
#10 選手として、父として。見られる過去より、魅せたい現在地ーー渡邉千真
#11 余裕を求めて、動き続ける。模索の先にある理想へーー宮坂拓海
#12 この愛に、嘘はない。激情と背中で示す覚悟の真意とはーー鈴木友也
SHIBUYA CITY FC
渋谷からJリーグを目指すサッカークラブ。「PLAYNEW & SCRAMBLE」を理念に掲げ、渋谷の多様性を活かした新しく遊び心のあるピッチ内外の活動で、これまでにないクリエイティブなサッカークラブ創りを標榜している。
渋谷駅周辺6会場をジャックした都市型サッカーフェス「FOOTBALL JAM」や官民共同の地域貢献オープンイノベーションプロジェクト「渋谷をつなげる30人」の主宰、千駄ヶ谷コミュニティセンターの指定管理事業など、渋谷区での地域事業活動も多く実施している。
お問い合わせ
担当:畑間
問い合わせはこちら