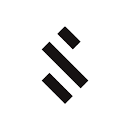SHIBUYA CITY FCに人生を懸けた男「俺をこんなにも好きにさせた、このクラブが悪い!」ーー植松亮【UNSTOPPABLES】 #17
2025年7月5日
|
Article
「このクラブのせい!俺をこんなにも好きにさせた、このクラブが悪いんだよ!」
植松亮といえば、渋谷。そんな言葉が違和感なく響くほどに、彼はこの街とクラブの一部となる存在となった。取材を終え、あらためて強く確信したことがある。それは、彼がこのクラブにいる価値と、本気で愛する覚悟の尊さだ。
【UNSTOPPABLES~止められない奴ら~】
昨シーズン、関東2部への昇格を決めたSHIBUYA CITY FC。その栄光の背後には、ただの勝利以上のものが隠されていた。選手たちの揺るぎない自信と勢いは、彼らの人生に深く刻まれた歩みから来ている。勝利への執念、それを支える信条。止まることを知らない、彼らの真の姿が、今明らかになる。
第17回は、まだ年齢的には中堅の立場ながら、今チーム最古参となった植松亮。一見つかみどころのない彼の中にある、渋谷での覚悟。その素顔とクラブへの真っ直ぐな想いに迫る。
植松 亮(うえまつ りょう)/ MF
埼玉県越谷市出身。1999年8月29日生まれ。171cm、64kg。中学・高校時代を大宮アルディージャの下部組織で過ごし、高校3年時には副キャプテンを務めた。青山学院大学では、4年時にはキャプテンとしてチームを牽引。1年で東京都1部リーグから関東大学リーグの昇格を果たし、自身は最優秀選手賞に選ばれた。卒業後、SHIBUYA CITY FCに加入。今季で4年目を迎え、チーム内では最古参の一人となる。中盤での冷静なボール捌きと、相手の意表を突く技巧的なパスを武器に攻守のリズムを操る。
キャプテンじゃなくても
SHIBUYA CITY FCが今年から関東リーグという新たな舞台に上がり、植松亮の心境にもひとつの変化が訪れていた。これまで語る機会の少なかったその思いを、率直に明かしてくれた。
「今年はあまり考えすぎず、いい意味でサッカーとプライベートを切り分けられているかな。関東リーグに昇格できたことで、それまで3年間背負っていたプレッシャーがやっと外れた。もし3年目も昇格できなかったら、俺の人生もクラブの歴史も進まないから。だから今は、すごくのびのびやれている」
穏やかな表情やリラックスした話しぶりから、これまでとは違う落ち着きが感じられた。肩の荷が下りたところで、自分らしさをより自然に表現できているのかもしれない。
「寝られない時もあったし、朝起きるのもきつかった。体に出るくらい、変化が大きかった。だからこそ、その不安や責任からの解放感がめちゃくちゃある。ずっと頭の片隅で、いろいろ考えてたからね」
自身の性格を「割り切るタイプ」と語る彼だが、それでも昨年までの重圧は並大抵のものではなかったようだ。
「毎年見えている景色は違うし、良くも悪くも『一歩ずつ進んでいる』って自分に言い聞かせていた。でも同じステージで3年間戦い続けていたから、実際には進んでいなかったんだよね。だから昇格できて一歩階段を上れたのは、めちゃくちゃ大きい」
そして今、彼はチーム最長の在籍年数を誇る選手となった。SHIBUYA一筋で歩んできたその道のりを思えば、昇格の喜びは他の誰よりも深く、格別なものだった。

それでも彼は、キャプテンにはならない。クラブを誰よりも知り、誰よりも背負ってきた彼がキャプテンマークを巻いていても、不思議に思う人はいないだろう。だが本人は、その役割を自分が担うべきものとは考えていない。
「正直、キャプテン・副キャプテンの肩書きを、俺がつける意味を感じない。もともと責任感はあるタイプだし、それは自分自身でも気づいたこと。マスさん(増嶋監督)や翔さん(小泉翔 / 代表取締役CEO)も理解してくれてて、もう自由にやってくれって感じかな」
だが今季、関東リーグという新たな戦場に身を置くなかで、ここからさらに自分自身もチームも一段と引き締めていくには、これまでと違う変化が必要なのではないか。そんな思いが芽生え始めていた。
「自分がキャプテンという立場を引き受けて、もっとこのクラブを上に引っ張っていく覚悟を持つべきではないかって、シーズン前に翔さんと話をしたんだよね。ステージがひとつ上がったことで、今なら違う責任感でキャプテンができるかもしれないって思ったから」
その決意の背景には、ある人物の存在がいる。それが、彼にとってもSHIBUYAにとっても大きな存在であり続けた、宮崎泰右。湘南ベルマーレやザスパクサツ群馬など、数々のJリーグの舞台を経験し、SHIBUYAには5年間在籍。昨シーズン限りで現役を退いた元エースの存在は、植松にとって特別だった。
「あの人が引退してから、すごく考えたんだよ。クラブと現場との関係って、外から来たばかりの選手にはまだ分からないことが多い。でも泰右さんは長くいたから、現場にも言えるしクラブ側にも言える。良くも悪くも、全部任せちゃってたところがあったんだよね」
クラブと現場、その両方の空気を理解し、つなぐことができる存在がいなくなった今。彼の中に「自分がその立場を担わなければ」という意識が芽生えていった。
「だから自分からキャプテンになってもいいって言ったんだけど、マスさんからは『やらなくていいから、ピッチの上で表現してほしい』って言われたんだよね。決まったことに対して、特に何か言おうとは思わなかったし、求められているのがそれなら、プレーで見せなきゃなって思った」

とはいえ、昨年の段階ではどうしてもキャプテンを務める気にはならなかった。ただでさえ、十分すぎるほどの重圧を背負っていたからだ。そこに役職が加われば、その重さは何倍にもなる。彼にとって、それは冷静な自己判断だった。
「自分でもいろいろやばくなるだろうなと思った。サッカー以外のことにもきっと影響が出ちゃいそうで。だから去年はやりたくないって言った記憶がある。別にキャプテンをやらなくても、チームをまとめないわけじゃないからね」
誰よりも渋谷を知っているからこそ、知らず知らずのうちに背負ってしまうものも多い。見えない重責と向き合いながらも、自分らしくあることを選び続けてきた。

好きにさせたのは、このクラブのせい
それは、彼が大学4年のときのこと。キャプテンとしてチームをまとめ上げ、わずか1年で関東リーグへの復帰を果たした。文句なしの実績を残し、次のステージへと進んでいくはずだったーー少なくとも周囲はそう思っていた。
だが、年が明けても彼の進路は決まらなかった。中学・高校時代を過ごした大宮アルディージャで再びプレーすることを強く望んでいたが、タイミングが合わず、他クラブからの練習参加やオファーも断った末に、大宮からは不合格の通知を受けた。
プレーヤーをやめるーーそんな考えが頭をよぎった。それでも、青学の総監督らからは「サッカー界には残ってほしい」という声が寄せられた。他大学の指導者になるという選択肢も浮上し、実際に契約書に印鑑を押す一歩手前まで話は進んでいた。
だが、どうしても心の奥に残っていたのは、「まだプレーがしたい」という本音だった。その想いに正直になろうと決め、指導者としての話は白紙に戻した。周囲も彼の気持ちを尊重し、もう一度ゼロからチームを探そうと、すべてをフラットに考え直した。

そんな矢先、大学の監督のもとに一本の連絡が入る。後に、彼の人生を大きく変えることになるーーSHIBUYA CITY FCからだった。
「はっきり覚えてないけど、翔さんから監督に連絡があって。同じ渋谷区っていうつながりがあったから、青学から選手が欲しいんですけど、誰かいい選手いませんか?って」
偶然のようで、必然だったのかもしれない。小泉代表も、大宮アルディージャユース出身。植松とは遠い先輩・後輩の関係性で、ちょっとした共通点もあり、一度話をしてみることになった。

そしてわずか数日後、彼はSHIBUYAに加入することを決めた。
関東リーグやJFLのクラブからの、練習参加の打診はゼロではなかった。Jクラブ入りの可能性だって、周囲は最後まで模索してくれていた。
それでも彼の決断は、驚くほど早かった。まるでそれまでの迷いが嘘だったかのように、即決だった。
「もう、その日の直感だったね。普通は、上のカテゴリーから入るのがセオリーなんだろうけど、俺はそこまでカテゴリーへのこだわりはなかったから。それよりも、クラブ自体に惹かれたのが一番大きかった。
変な話かもしれないけど、もし大宮がJFLまで落ちようが、どこにいようが、俺は大宮っていうクラブが好きだったから行きたかった。それと同じように、SHIBUYAがどのカテゴリーにいても『ここがいい』って思えたんだよね」
早すぎる決断だったが、その裏には彼なりの基準がある。
「俺って、いつも相手の熱量で決めることが多いんだよね。その熱に応えたいって思うから。クラブの魅力とかビジョンについてはいろいろ説明されたけど、何より翔さんの熱量が一番すごかった。良い意味で根拠のない自信っていうか、あれには引っ張られるものがあったな」
小泉代表からの熱烈なオファーに、ただただ圧倒された。まだどこにも所属先が決まっていなかった自分に、真正面からぶつけられた想いが純粋に嬉しかった。
「他に候補がいっぱいあったら、『また言ってくれたなあ〜』くらいにしか思わなかったけど、俺はどのクラブにも入れない選手だったから。しかも翔さんには俺のプレーを直接見てもらったことはなくて、本当に初対面だった。だからどうして俺のことを誘ってくれたのか今でもわからない。そこは聞いたことないから気になってるけどね。
でも、あの日もし『このチームに興味を持ったら、また連絡してね』って言われていたら、たぶん俺は他のチームに行っていたと思う。保留でもなく、その場で翔さんが『一緒にやろうよ』って言ってくれたから、その数日後には電話したんだよ。『僕、SHIBUYA CITY FCに入りたいです。一緒にやらせてください』って。そしたらまた会って、契約の話も進んで、そのあとの数日で全部決まったんだよね」
「後日でいい」ではなく、「今この場で」求められたことが何より嬉しかった。良い意味で、人の気持ちに影響されやすく、「応えたい」と思ったときの行動力は強い、植松らしい決め手だ。

「なんか、わかるんだよね。『この人は本気でやりたいんだな』っていうのが。逆に、この言葉は本気じゃないな、ただやりたいって言ってるだけだろうな、っていうのもなんとなく伝わってくる」
以前、彼が話してくれたことがある。人の熱量は、言葉以上にレスポンスの速さや連絡の文面、その温度感にこそ表れる、と。
「LINEの文の感じとか、ラリーのスピードですぐわかる。これって勘なのかな?でも多分、俺が逆の立場だったときに、そうしてきたからだと思う。今も青学のOBとかに結構図々しく連絡してるし。お願いごとがあるときや、ご飯に行きたいときもすぐLINEする。仲良くなれたら、自分からグイグイ行くタイプだからね。
人の熱量がわかるのって、あくまで自分の経験だけで分かっているだけなんだろうけど、でも、なんかわかる。本気のやつって、やっぱり熱がすごいから」
そんな自分の感覚を信じて、言葉の温度やタイミングに宿る本気を感じ取った彼は、導かれるようにSHIBUYAへの加入を決めた。

そして加入から半年ほどが経った頃には、こう確信していた。「このクラブでよかった」と。
渋谷区スポーツセンターでのホームゲームやイベント活動。裏方のスタッフたちとの何気ない交流の数々。それらを重ねるたびに、「このクラブのために」という想いは日に日に強くなっていった。

そんなSHIBUYAで迎えた初めてのオフシーズン。2年目を迎える前のことだ。実はそのタイミングで、彼にはJクラブのオファーが届いていた。
人生で一番といっていいほどの葛藤に悩まされた。Jリーグの舞台に飛び込むチャンスーー幼い頃から夢見ていた場所が、すぐ目の前にあった。だからこそ、これまで自分を信じ、期待を寄せてくれていた人たちの思いを裏切ってしまうのではないか、そんな迷いも当然あった。
もちろん、多くの人に相談した。田中裕介スポーツダイレクターからは、トップレベルで戦うことの楽しさと厳しさを。そして、さまざまなカテゴリーを渡り歩いてきた宮崎からは、クラブの外を知る者としての冷静な意見をもらった。
それでも彼が最終的に選んだのは、SHIBUYAに残ることだった。その決断に、後悔は一切ない。むしろ、胸を張って「この道を選んでよかった」と言い切れるだけの自信が、彼の中にはあった。

「このクラブのせい!俺をこんなにも好きにさせた、このクラブが悪いんだよ!」
そう冗談めかして笑ったが、その言葉からはクラブへの愛の深さが十分に伝わってくる。
たった1年。されど1年。どうしてこんなに惹かれたのか、自分でも不思議に思うほどだ。
「なんでだろうね。めっちゃ好きになってたんだよ。今でもふと考えるし、誰かと話していても思う。『なんで俺、SHIBUYAを選んだんだろう。なんでこんなバカみたいに、SHIBUYAのことを好きになってんだろう』って」

そして行き着いた感情は、SHIBUYAのスタッフからの「愛情」だった。
「『残ってほしい』って、そう言ってもらえたのが本当に嬉しかった。普通ならさ、上のカテゴリーからオファーが来たら『行け』って背中を押すと思うんだよ。でも、SHIBUYAの人たちは違った。いろいろ悩んで、整理はしたつもりだったけど、結局何が決め手だったかって聞かれたらーー
やっぱり、SHIBUYAのことをこんなに好きにさせた、スタッフ陣の愛情だと思う」
掴めそうで、掴めない
これまで彼のSHIBUYAでの歩みを聞いてきたが、どうしても聞いておきたい、本命の質問があった。それは、「植松亮という在り方」についてだ。
普段の植松は、年上・年下関係なく誰とでも気さくに話し、周囲からの信頼も厚い。実際、これまで他の選手を取材してきた中でも、彼の名前は頻繁に挙がっていた。「サッカーでもプライベートでも、よく面倒を見てくれる」「自分から話しかけてくれるし、ご飯にも誘ってくれる」ーーそんな声が多く聞かれた。
筆者自身もそう感じている。自分を含めたインターンのメンバーに対しても、彼は気を配ってくれている。だからこそ、こんな疑問が浮かんだーーこの「立ち回りのうまさ」は、意図的なものなのか、それとも自然体なのか。
そのことを伝えると、当の本人は苦笑してこう答えた。
「そんなに人によって態度は変えていないし、計算もしてない。けど、なんだろう……表現が難しいけど、相手には楽に接してほしいっていう気持ちはあるかな」

たとえばーーと、彼は続けた。
「年上の人とご飯行こうってなったら、場所もお店もだいたい俺が決めるし、後輩でも俺から提示することが多いかな。決めるまでのラリーがめんどくさいっていうのもあるけど、どれも全部感覚なんだよね。
誰かと予定合わせるのが好きではないっていうか、そんなに先の予定までは入れたくないから。タイミングが合わなかったら1人で行くこともあるし。でもほんの少しの時間でも誰かと話せたら嬉しいかな」
カフェやピアノ、散歩が趣味だという彼は、リラックスする時間こそが、誰にも止められない瞬間だという。
「サッカー以外のことをしているときに『いまから来て』って言われたら『ここにいるので嫌です』って言う。俺はプライベートの時間があるからサッカーを頑張れるし、100%で向き合えてる。だからサッカーの試合も普段はあまり見たくない」

そして昔から彼は、年下は可愛がり、年上にはひと回り、ふた回り年が離れていようが、分け隔てなく接してきた。
「今は、新しく来た選手たちに『このチーム、居心地がいいな』って思ってもらいたい。もちろん、もっと上の舞台に行ってほしい気持ちもあるけど、ここで過ごす時間を楽しいって感じてもらいたくて」
そんなふうに周りを思いやれるのも、かつて自分自身がそうされてきたから。
「上の人たちにしてもらったことが、単純に嬉しかったんだよね。だから、今は自分が下の子たちにも同じことをしているだけ。年上の人にご飯に連れていってもらったり、いろんな経験談を聞けたり、40歳でも50歳でも60歳の人でも、そうやって可愛がってもらえたのが、本当に嬉しかったから。信頼できる存在がいるって、めちゃくちゃ心強いんだよね」

ここで名前が挙がったのは、彼が日頃から多くの時間をともに過ごす、渡邉千真だ。数々のJリーグクラブで活躍し、日本代表経験もある、まさにレジェンドのような存在。そんな大先輩に対しても、植松はまったく臆することなく、プライベートでは一緒にご飯や買い物に行く間柄だ。
渡邉が取材時に語っていたこんな言葉が印象的だった。「亮は、年上に入り込むのがうまい。どんどん積極的に話しかけてくれるから、つい可愛がっちゃうんだよね」(UNSTOPPABLESーー渡邉千真#10 より)
一方の植松も、渡邉に対しては深い尊敬の念を示している。
「いろんな道を通ってきて、あの人の生き方ってすごくいいなって思う。あの年齢でも文句ひとつ言わず、プロ意識を持って今でも全力でプレーしてるしさ。千真さん、記事でも言ってたじゃん。『一番大事なのは、子どもたちが幸せでいること』だって。もう理想だよね」
ちなみにーー彼は渡邉のJリーグチップスのカードを2枚持っていて、それにサインをもらって家に飾ってるという。昔は浦和レッズファンだったこともあり、そこまで渡邉に関心があったわけではなかったが、今はピッチ内外問わず学ぶことの連続だ。
「あの人の考え方に惹かれるから、身近にいたいのかもしれない。『なりたい人の近くにいたほうが、自分もそうなれる』ってよく言うじゃん?千真さんがこれからどう生きていくかっていうのが、俺のその年の目標になっていくと思う」
そう語る彼には、学びの対象がひとりやふたりでは収まらない。
かつて選手として渋谷でプレーし、現在はスポーツダイレクターとしてクラブを支える田中裕介や、2023シーズンの序盤まで渋谷に練習参加していた長谷川アーリアジャスール(現・ガイナーレ鳥取クラブアンバサダー)の名前も出てきた。
「裕介さんも、去年お子さんが生まれたし、選手だったころのキャリアもすごいよね。アーリア君とはこの前一緒にカフェに行った。俺、大宮時代スタンドからアーリア君のこと見てたし、まさかアーリア君の引退までお祝いできるなんて、思ってなかったよ」


そんな中で、話は人生観へと移る。
「俺、人の後悔の話が好きなんだよね。特に年上の人だと、長く生きているぶん、いろんな後悔があるじゃん。でも、その人たちにとってはもう取り戻せないことでも、俺らからしたら先に聞ける後悔なわけで。それを聞いておけば、幸せになれそうな気がするんだよ」
時間の使い方、お金のこと、人生の選択。尊敬する人たちから聞く、リアルな過去の選択は、どれも自分の行動のヒントになる。
「そういう話を聞いて、自分に合うものはどんどん取り入れたいし、何より尊敬する人たちが仲良くしてくれることが嬉しい。それに、尊敬する人がいること自体が幸せなことだし、自慢じゃん」
彼にとって、その人たちは自分の頂点だ。だからこそ、ずっと追いかけたいと思う。
「でもさ、きっとその人たちにも、追いかけている人がいる。俺が今ついていっている人が、昔誰を追っていたのかっていう話を聞いて、またその人を追いかけたくなる。
だから今度は、自分が後輩たちにとっての、”その一歩目”になれたらいいなって思う。誰かと誰かをつなぐ、そんなきっかけを与えられたら嬉しいよね」

春頃には、河波櫻士と小関陽星を連れて、渋谷のおしゃれなレストランに出かけたことがあった。
「『なんか言ってくださいよ!俺ら場違いな格好で来たじゃないですか』って言われた(笑)ちゃんと事前に場所も伝えてたし、『オッケーです』って返ってきたんだけど、迷子になったみたいでさ。来たと思ったら、雨の中傘もなくて2人ともずぶ濡れ。あれは面白かったなあ」
楽観的な性格の河波と小関。その2人とは対照的に見える植松だが、だからといって気が合わないわけではない。その理由には、彼が持つ力の抜けた考え方がある。
「俺、堅い話はあんまり好きじゃないんだよ。自分から真面目な話はしないし。相談とかされたらちゃんと答えるけど、基本はふざけてるし。もちろん、たまには真面目な話もするけどね」
一見、何かと考え込んでいそうな雰囲気をまとっているが、実際はそうでもないらしい。

「基本、あんまり深くは考えてない。よく周りからは『考えてそう』って言われるけど、それはたぶん、関係ないことを考えているだけ。会話だって、ある程度話したらそこからは多分聞いてない。長々とやりとりするのは飽きちゃうし、疲れちゃう。だから、その場が楽しければいいやって感じ」
そうしたスタンスは、彼が楽観的になれたからこそだと言う。
「昔は全然なれなかったよ。考えすぎちゃうし、悩みも多かった。でも今は考えても無駄っていうか、結局は人それぞれだなって。俺は俺、っていう自己中じゃなくて、『ああ、そういう考えもあるよね』くらいの、いい意味での距離感でいられるようになったかな。
第一印象は怖いって、よく言われることが多い。でもそれって、ただぼーっとしてるだけなんだよね。顔つきもあると思うし。でも、俺の中身を知ってる人からは『ただのちょろいやつ』って言われるよ(笑)別に正論を語れるわけでもないし、頭がいいわけでもないから。だから俺のことをよく知らない人からすると、『なんかすげえやつ』みたいに見えているだけだと思う」

彼自身はそう語るが、「生き方がうまいですよね」と投げかけると、どこか納得したようにうなずいた。
「世渡り上手かもね。自分でもそう思うし、狙っているときもあるよ。例えば、年上の人に好かれたいなとか、この人といると楽しいからもっと話したいなって思ったら、グイグイ行く。人間観察も好きだから、相手が何を考えているのか、ずっと探ってる。監督とかコーチが今どんな気分なのかも、なんとなくわかる。『あ、怒ってそうだな』って思ったら、一歩距離置いたりね。そうやってうまく生きてる」
一見すると、計算高いように聞こえるかもしれない。でも、それは他者と丁寧に向き合ってきた証でもあり、人と信頼を築くことに長けた、彼ならではの強みなのだ。
「これは小さい頃からなんだよね。コーチとかにも好かれやすかった。でもそれは、素直だったのが良かったんだと思う。言われたことに対して愚痴をこぼさずに、『やってみます』ってとりあえずやってた。愚痴って言うほうが疲れるじゃん?『あ、愚痴が出そうだな』って思ったら、もうその人とは自分から距離を取ってた」
でもそれもすべて”感覚”の話なのだとしたら、こちらが勝手に深読みしすぎているだけなのかもしれない。本当はもっとシンプルに、あまり深く考えずに生きているのではないか。話を聞けば聞くほど、そんな気がした。

「そうだよ。クソガキでしょ?自分でも思うもん。だからたぶん、俺より相手の方がいろいろ考えてるよね。俺に対して偏見を持って接してるだけだと思う」
高校の卒業式のときには、クラスメイトからこんなことを言われた。
「『こんなに植松と仲良くなれると思わなかった。怖くて、1年間喋らず終わると思ってた』って。でも、別に俺は全員と仲良くしようなんて思ってなかったし、そのまま喋らずに終わっても後悔はなかった。だから、結局は向こうが考え過ぎてただけなんだよね」
また、サッカーをしているときと、普段の姿とのギャップも、彼のことをよく知らない人を惑わせる理由のひとつなのかもしれない。
「サッカーをやってるときだけの俺を見てる人には、『真面目だね』って言われる。逆に、普段の俺を知っている人には、『ただのクソガキじゃん』って(笑)俺と仲いい人に聞けば、みんなそう言うと思うよ。言っちゃえば、櫻士と陽星と似てると思う。だから気が合うんだろうね」
その場の空気をちゃんと読むことは意識している。けれど、それは「先回りして考える」というよりは、「その場で感じて、判断して、言葉に出す」ことの積み重ねだという。

どうやら、”深く考えていそうな人”というのは、こちらが勝手につくり上げたイメージに過ぎなかったようだ。
「日本人あるあるだね。そういう偏見って。昔読んだ本にも、『人間は良いところも悪いところも50ずつ持っている』って書いてあった。だから俺は、人に対して変な偏見は持たないようにしてる」
実は筆者は、今回の取材をするうえで悩んでいたことがある。植松のことだから、きっと「こういうふうに見られたい」という理想像があるんじゃないか。だったら、できるだけそれを汲み取るべきなのではないか……と。
そんな思いを口にすると、彼は笑ってこう言った。
「そんなのないよ。だって、仲良い人たちにはもうバレてるわけじゃん。仮に硬い言葉を並べて違う人格になったとしても、『お前、作んなよ』って言われるだけだし。だから、今さら良いように見られたいとかもない。
人との関わり方もそう。俺は自分を100でぶつけて、それを受け入れてくれる人に好かれたい。だから上とか下とか関係ないんだと思う。こっちがちゃんと向き合っていれば、相手の反応でも分かるじゃん。真摯に応えてくれているのか、適当に流されているのかって」

なんだか、両面ある不思議な人だ。どちらかに極端に振れていないぶん、こちら側が深読みしてしまう。
「全く考えてないとは言わないけど、人が思ってる以上に俺は考えてない。……でもわかんねえな。俺も考えてないから」
そんなふうに言われてしまうと、ますますわからなくなる。
「わからない方がよくない?ミステリアスなほうが惹かれるじゃん」
言うべきときに、自分が
先ほどまでは、彼の強みと言おうか、人としての持ち味について触れてきた。だがここからは、もう少し踏み込んで、彼の「弱さ」にも目を向けてみたい。
今シーズン、第2節・東京国際大学FCとの一戦のこと。SHIBUYAは前半に2点リードをしながらも、後半にまさかの3失点という悔しい逆転負けを喫した。開幕戦から期待値が高まっていただけに、その落差は大きかった。
試合後はどこか不穏で、チームとしてもバラバラになりかねないムードがあった。そんな中、最後の集合時に増嶋監督は「言いたいことがある選手は、言ってから帰ってほしい」と言葉をかけた。
すると即座に口を開いたのは植松だった。
『昨年の関東大会が終わってからこれだけ時間があったのに、クラブ全体がバタバタして開幕を迎えてしまった。その隙が、今甘さに出ている。でも、こんなにも社会人クラブでJリーグ並みの熱量を持って戦えているのは、スポンサーや企業さんのおかげ。それだけみんな熱くやれているから、その熱量は絶対に下げちゃダメ。
練習のパスコンから意識しろと言われている部分を、どこかみんな甘くやっているし、意識がふわっとしている部分がある。その一つひとつで、絶対に変わるから。別に下を向く必要もないし、ここから全部勝てばいいだけの話。もう一回クラブ全体で、自分たちが感謝を持ってやれば、間違いなく良い方向に進むから』

この言葉の真意を聞いてみた。
「あれは、言わなきゃいけない立場だなって思ったから言っただけ。それこそ去年までは泰右さんがいたけど、あの人はああいう場でしっかり言う人だった。でも今は、俺がクラブに一番長くいて、試合にも出てるわけだから、言う意味があると思った。もし試合にも絡んでなかったら、ちょっと躊躇ったりしただろうけど。
でも今まで自分から手を挙げて発言したのって、指名される以外では初めてだった。クラブスタッフたちも、俺がああいう場面で言ったのを見たのは初めてだったんじゃないかな」
それでも、あの発言を「自分の成長」と認める一方で、「弱さでもある」と彼は言う。
「本来は、あの場じゃなくてもっと早く言えたと思う。いろんなことが起きたから言ったけど、開幕で引き分けた時点で、絶対にタイミングはあったはず。でも、何かが起きそうとか、起きる直前にならないと言えないのは、自分の弱さ。守りには入っちゃう部分もあるし、一歩踏み出すまでに時間がかかる。まだ殻を破りきれていないのかもしれない」

たしかに彼は、普段からよく周りを見ているほうだが、自我をぐっと前に押し出すことは少なく、発言のタイミングも少しズレることがある。
「周りを見ちゃうのも、自分の弱さだと思う。練習でも、『あ、今ちょっと雰囲気ピリッとしてきたな。じゃあもう自分が言わなくても大丈夫か』って引いちゃうことがある。でも裕介さんやマスさんには言われるんだよ。『もうお前が言える立場なんだから言え』って」
決して遠慮しているつもりはない。ただ、無意識に周りを見てしまう。そして、何かあっても「まずは自分がちゃんとやろう」と考え、自分のプレーに集中しすぎてしまうのも、彼の癖だ。
「もちろん、個人のスキルアップも大事なんだけど、もう少し器用に、他のことも見れたらいいなって思う。もう弱いところだらけだよ」

だが、そのためらいや抑え込みは、徐々に消えつつある。
「俺が言ったとしても『なんであいつが言ってんだよ』って思われることは、もうないと思う。俺がめっちゃふざけてたり、適当にやってたらそう思う人もいるかもしれないけど。でも今の自分の立場とか、SHIBUYAに長くいることを考えたら、そう思う人数は少ないと思う」
ピッチでも年々存在感も増し、クラブでの経験も積み重ねてきた今だからこそ、発言に重みも増してくる。
だがそれでも、ここぞという時に言い切れない自分がまだいる。
「タイミングが遅いし、そもそも言う回数自体が少ないと思う。本当はもっと早く、要所要所でちゃんと言えるほうがいい。それができないのは、4年間このクラブにいても変わってない自分の弱さかな」

ここで、人生を捧げてもいい
最後に、少しベタな質問になってしまうが彼にだからこそ、率直に聞いてみた。
なぜ、今も渋谷にいるのかーー。
「『SHIBUYAが好きだから』としか言えないかな。必要としてくれていることが、ただただ嬉しいんだよね。たとえ個人昇格の可能性があっても、今は他のチームに行きたい気持ちはないかな」
一選手として、もし使い物にならなければクビ。それでも大好きなクラブでプレーできる今に、彼はひたむきに頑張っている。
「でも俺の考えって、その時々で結構変わるんだよね。昔からの考えにずっと執着することはないし、毎年変わるから。
だから今こう言っているとはいえ、来年どう思ってるかなんてわからない」
そのあと、少しだけ言葉を切ってこう続ける。
「でも、このクラブを上に上げて終わりたい。ひとつでも上のレベルに上がれば、良い選手がもっと来るようになるじゃん。そうなったら、俺はもう必要とされないかもしれない。でもその時はその時だなって。
それまでに後悔があったら嫌なんだよね。自分が少ししか試合に絡めなくて、他の人が活躍して昇格しました、ってなったら、俺のサッカー人生に後悔が残りそう。だからずっとピッチには立っていたいし、仲間と喜び合いたい。そのためには、怪我してたらダメだなって思うし、自然と意識も変わってきたよね」
もちろん、個人としての成長欲求がなくなったわけではない。幼い頃から抱いてきた「Jリーグの舞台でプレーしたい」という想いは、今でも変わらずにある。

それでも彼はいま、SHIBUYAにいる。
「1年目からクラブが上がれなかったっていう責任を、ずっと感じてた。関東大会に出て、自分がピッチに立って、大勢のサポーターの前でキャプテンマークを巻いたのに、結果を残せなかったから。
自分だけが上に行きたいと言っていいのかって、めちゃくちゃ考えた。SHIBUYAのおかげで、今の人生があるから。
もし自分が大怪我をして試合に出られなくなってもこのチームの勝利を願うし、このクラブの成功が一番の喜び。もちろん選手として考えたら、自分が試合に出て結果に直結できるほうが嬉しいし、プレーで演出してサポーターを楽しませるのが一番。ピッチに立たなきゃ、選手としての魅力は出せないから、そりゃあ自分の欲もあるよ」

でも今は、そんなことは言っていられない。
「もう、自分の中の一番はこのクラブだな。このチームが上に上がってくれればいい。ひとつでも」
自分のことよりも、SHIBUYA CITY FC。とんでもない愛がそこにはある。その理由を尋ねると、彼は迷いなくこう答えた。
「俺をこんなに好きにさせてくれたのは、クラブ関係者やサポーター、インターンの熱量や愛情。昇格して泣いて喜んでくれて、このカテゴリーなのに自分のわがままを聞いてくれて。
それがなかったら、きっと違うチームに行ってたよ。ここまで頑張ってくれる人たちがいるから、勝たせたいって思える」
これが、彼が最初に話した「このクラブを好きになった理由」とつながっている。

だが、あえてこう質問してみた。それは他のクラブも同じなのではないか、と。
彼は「まあね」と前置きしながら、こう続けた。
「たしかに、他のチームに行ってみないとわからないよ。でも今は、他のチームを知りたいとも思わない。知り合いから他のチームの話を聞くし、今だとYouTubeのINSIDE CAMでいろんなクラブの裏側を見れるじゃん。もちろんJクラブはあの人数がいるからこそ、パワーもすごいし。そういうのを見ると、やっぱり行きたくはなるよ」
最近のプライベートでは、大宮アルディージャの試合を観に行ったという。そこで感じたのは、やっぱり「このチームが好きだ」という気持ち。そして、あの大歓声を聞ける可能性が、自分にもあると思うと、自分の気持ちを優先したくなる瞬間もある。
それでも彼は、自分の気持ちを抑える。それは決して我慢しているわけではない。ただ純粋に、このクラブのために貢献したいからだ。

そして今ではすっかり、「SHIBUYA CITY FCの植松亮」というイメージが根づいている。彼自身も渋谷というクラブを愛し、誇りに思う一方で、それがときに葛藤になることもある。
「過去の経歴のインパクトは、他の人の方が絶対あるから、それは悔しい部分でもある。俺なんて、大宮のアカデミーにいたとはいえ、そんなの全国に何人でもいるし。青学も強かったかって言われれば、俺の代は都リーグだったし、キャプテンとして昇格させただけ。そのあとはSHIBUYAに来てるし」
特に今季は、SHIBUYAにはJリーグや強豪大学出身の期待のルーキーたちが続々と加入した。元から在籍しているメンバーにも、関東リーグに所属する大学や全国の舞台を経験してきた選手はザラにいる。
その中にいると、彼の言うとおり「経歴だけ」で見ればインパクトには欠けるかもしれない。だが、それでも闘争心がないわけではない。
「だから他の選手に負けたくない気持ちは、めちゃくちゃあるよ。だってこの俺の経歴だと、負けたら納得はされるじゃん。
でも個人として負けたくないし、うまくなりたいし、それと同時に、他のJリーグでやってる選手の活躍とか見るといいなって思うよ。観客席にいる一般の人が、あんなに大きい歓声を出すなんてすごいじゃん。それを自分がピッチで聞けるチャンスがあるわけで」

だからこそ、ずっと応援してくれている家族の存在を思うと、自分自身の気持ちにも、同情や共感が生まれる。
「俺も心配する気持ちはわかるよ。やっぱりサッカー選手ってギャンブルでもあるから。今日のこのあとの帰り道で交通事故に遭ったら、それでもう引退かもしれない。ちょっとした不注意で、全員にそれが起こり得る世界だからさ。
なおかつSHIBUYAは、まだこのカテゴリーにいるチーム。『渋谷にあるサッカークラブ』っていう多少のインパクトがあったとしても、入る前はめちゃくちゃ心配されたよ。
でもそういう不安を取り消すのも、もう自分次第。自分が活躍して、このクラブがJリーグの舞台にいったらすごく嬉しいことだろうし。
もし仮に、今からサッカーを辞めて就職するってなったら『え?』ってなるかもしれない。でも俺がやりきって、楽しそうにしてたら、誰も気にならないと思う」

「だからここまできたら、簡単にこのクラブを捨てることはできない。いろんな人が『もういらないから、他へ行け』って言ったら仕方ないけど、自分から感情を出すことはない」
つまり今、彼の頭にあるのは「SHIBUYA」しかない。そう、はっきりと宣言してくれた。
彼のこれからの成長も楽しみだが、それ以上にクラブを想いながらプレーする姿は、とても頼もしい。

「すべてのクラブ関係者、ファン・サポーター、インターンも含めて、みんながあんなに頑張ってくれるから、そう思わせてくれる。俺は1年目からそれを見てきたし、今も忘れないようにするために、自分から見ようともしている。
フロントスタッフはそんなに現場に来るわけじゃないし、頻繁に会うわけでもないから、イベントがあったらそういうコミュニケーションも大事にしたいなって思うし、インターンと話すのも大事なのかなって思ったりする」
言葉にしなくても、ちゃんと見ている。声をかけずとも、ちゃんと感じている。そして、ずっとその「熱」に動かされてきたのだ。

彼のSHIBUYAでの3年半がぎゅっと詰まった時間だった。もちろん、この取材で話していないことはまだまだ山ほどあるだろう。
けれど最後は、この言葉で締めようと思う。これが彼にとって一番伝えたかったことかどうかはわからない。この気持ちは、もしかしたら来年は違うかもしれない。それでも、今日という今日のこの想いが、嘘じゃなかったことだけは記しておきたい。
「何が正解かはわからない。でも今一番、俺が後悔するのはーー」

「このクラブを捨てることだと思う。それが生きていくなかで、すごく後悔する。俺はこのクラブで一生を終えたい。今はもう、この渋谷に、自分の人生を捧げてもいいと思って生きている」
彼がこの先どこでサッカーを続けていくのかは、誰にもわからない。ただひとつ確かなのは、彼の人生に「SHIBUYA CITY FC」というクラブが存在しているということ。
それは、簡単に忘れられるような関係じゃない。そしてきっと、クラブにとっても。
取材・文 :西元 舞
写真 :福冨 倖希
企画・構成:斎藤 兼、畑間 直英
UNSTOPPABLES バックナンバー
#1 渋谷を背負う責任と喜び。「土田のおかげでJリーグに上がれた」と言われるためにーー土田直輝
#2 頂点を目指す、不屈の覚悟。全ては世界一の男になるための手段ーー水野智大
#3 冷静さの奥に潜む、確かな自信。「自分がやってきたことを発揮するだけ、『去年と変わった』と思わせるために」ーー木村壮宏
#4 這い上がる本能と泥臭さ。サムライブルーに狙いを定める渋谷の捕食者ーー伊藤雄教
#5 問いかける人生、答え続ける生き様。「波乱万丈な方へ向かっていく。それがむしろ面白い」ーー坪川潤之
#6 サッカーが導く人生と結ぶ絆。ボールがくれた縁を、これからも。ーー岩沼俊介
#7 楽しむことを強さに変えて。夢も、欲も、まっすぐに。ーー小沼樹輝
#8 誰かのために、笑顔のために。誇りと優しさが生む頂点とはーー渡邉尚樹
#9 九州で生まれた男の背骨。「やっぱり男は背中で語る」ーー本田憲弥
#10 選手として、父として。見られる過去より、魅せたい現在地ーー渡邉千真
#11 余裕を求めて、動き続ける。模索の先にある理想へーー宮坂拓海
#12 この愛に、嘘はない。激情と背中で示す覚悟の真意とはーー鈴木友也
#13 憧れた側から憧れられる側へ。ひたむきな努力が導く、まっすぐな未来ーー大越寛人
#14 楽しいだけじゃダメなのか?渋谷イチの苦労人が語る「俺は苦しみに慣れちゃってる可能性がある」ーー高島康四郎
#15 かつて自分も”そっち側”だったからこそ、わかる。「もう誰のことも置いていきたくない」ーー志村滉
#16 絶対の自信を纏う、超こだわり屋のラッキーボーイ「必ず俺のところに転がってくる。そう思ってるし、信じてる」ーー青木友佑
SHIBUYA CITY FC
渋谷からJリーグを目指すサッカークラブ。「PLAYNEW & SCRAMBLE」を理念に掲げ、渋谷の多様性を活かした新しく遊び心のあるピッチ内外の活動で、これまでにないクリエイティブなサッカークラブ創りを標榜している。
渋谷駅周辺6会場をジャックした都市型サッカーフェス「FOOTBALL JAM」や官民共同の地域貢献オープンイノベーションプロジェクト「渋谷をつなげる30人」の主宰、千駄ヶ谷コミュニティセンターの指定管理事業など、渋谷区での地域事業活動も多く実施している。
お問い合わせ
担当:畑間
問い合わせはこちら