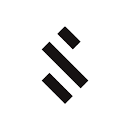絶対に壊されたくない、やっと思い出せた楽し��さ「副キャプテンを降ろさせられるんだったら、それでもいい」ーー楠美圭史【UNSTOPPABLES】 #18
2025年7月12日
|
Article
「サッカー人生で初めてですよ!練習中に『ふざけてる』なんて言われたのは」
真面目で、控え目で、キャプテンシーにあふれている。楠美圭史に対して、そんな印象を抱いているファン・サポーターは少なくないだろう。だが、今の彼はそのイメージと違うところに立っている。肩書きや期待に縛られることなく、自分らしくプレーする。FC今治の中心にいた男が、いま渋谷で見つけた自らの原点。その裏の葛藤と本音を明かした。
【UNSTOPPABLES~止められない奴ら~】
昨シーズン、関東2部への昇格を決めたSHIBUYA CITY FC。その栄光の背後には、ただの勝利以上のものが隠されていた。選手たちの揺るぎない自信と勢いは、彼らの人生に深く刻まれた歩みから来ている。勝利への執念、それを支える信条。止まることを知らない、彼らの真の姿が、今明らかになる。
第18回は、かつて今治の象徴だった楠美圭史。責任と自由の狭間で、彼がこの渋谷であらためて求めている、体現したいものとはーー。
楠美 圭史(くすみ けいし)/ MF
1994年7月25日生まれ。東京都三鷹市出身。177cm、70kg。中学・高校時代は東京ヴェルディのアカデミーで育ち、U-15・U-16・U-17日本代表に選出されるなど、世代別代表でも活躍を見せた。その後は東京ヴェルディのトップチームへ昇格。2015年にはヴェルスパ大分へ期限付き移籍し、翌年再び東京ヴェルディに復帰。2017年、当時JFL所属のFC今治に完全移籍。クラブの中心選手として在籍8シーズンを過ごし、J3、J2昇格と、2度の昇格を経験。2020年からは4季連続でキャプテンを務めた。今シーズンより、SHIBUYA CITY FCに加入。ボール奪取力と展開力を備えたボランチとしてバランスを保ち、的確なコーチングでゲームをコントロールする。
個性と競争の渦のなかで
「本当に唯一無二な世界観でした」
当時の環境を表すとしたら「異質」。そんな言葉がぴたりと当てはまる、東京ヴェルディ(以下:ヴェルディ)ユース時代。今から10年以上も昔のことだが、楠美の記憶にその日々は鮮明に焼きついている。
「ヴェルディは本当に特殊だったんです。『この人みたいになりたい』とか、『尊敬できるな』っていう人はあんまりいなかった。なんせ、変わってる人が多かったから」
人間的に強烈なキャラクターばかりが揃っており、誰に似せることもなければ、誰かの後を追うことが美徳でもない。テンプレートのような選手など、誰ひとりとして存在しなかった。それは決して主観的な印象ではなく、外から見ても「あのチームは異質だ」と言われていたという。
加えて、上下関係の厳しさも際立っていた。先輩の言うことは絶対ーーそんなルールが、暗黙の了解としてチームに根付いていた。
渋谷に昨シーズンまで在籍していた布施周士(COEDO KAWAGOE F.C)は彼のユース時代の同期だ。当時を思い出しながらこう語る。
「布施とかは、モロに飲まれちゃうタイプ。ああいうタイプの子は、なかなか自我を出していけないし、苦労したと思います。だから本当に、”自分”というものがしっかりないと、生き残れない世界だったんですよね」
個性のぶつかりあいが日常だったなかで、人としてのあり方まで丁寧に教えてくれるような指導はあまり多くなかった。だがその代わりに、サッカーに対する姿勢だけは徹底していた。
「みんなガッツがあるし、自分の軸を持ってるから周りに流されない。やっぱり実力の世界だからそこはサッカー選手には必要な要素だと思います。『サッカーが上手ければ全部正解』みたいな」
下手くそに人権はないーー攻撃的に聞こえるその表現も、当時においては、あながち冗談ではなかった。
「でも、上手ければ全員が認めてくれる世界。だからみんな本気だったし、必死でしたよ」
異質なほどに突出した個性と実力が同居していた。そして彼の同期には、今もJリーグの最前線で活躍する選手が何人もいる。そんな猛者たちが集まっていたなかでも、ひときわ記憶に残る選手がいた。それが彼の2学年上にあたる、小林祐希(いわてグルージャ盛岡)だ。
「ダントツで印象に残っていますよ。もうね、プレーのスケールのでかさが異次元。あの人がいるかいないかで雰囲気は全然違うし、迫力があって簡単に近づけない。でも『俺に任せとけ』っていう空気感はすごかったです。あんな人はなかなか見たことない」
偉大な先輩がすぐ目の前にいたが、その背中はとてもじゃないが「目指す」なんて言葉では片付けられないほど、遥か遠くに感じられた。
「もう、見習うとかのレベルじゃない。あの人がプレーするたびに、本当に毎回『うわー!すげえ!』って思ってました」
そんな才能が集う空間のなかで、楠美は冷静で、落ち着いている部類だった。だからこそ、今でも「ヴェルディっぽくない」と言われることもしばしば。
「自分でもよくあそこで生き残ったなと思います。でも逆に、俺みたいなタイプがひとりふたりいたから、チームとして成り立っていた部分もあった気がします。それは当時の監督にも言われました。

……というより、うまい選手だらけだったので、自分が他の方向を向いてやってる場合じゃなかったんです。あの環境で生き残るには、とにかく必死でした」
愚直に、自分のすべきことをやる。そして振り返ったとき、「あの時期も絶対に無駄ではなかった」と語る。
「プレーヤーとしての根っこにある部分は、ヴェルディで培ったものが今も残っていると思います。『結局、うまくなきゃダメでしょ』っていう価値観やサッカーを楽しむための遊び心とか。感覚的なものって、育ちですごく変わるので。
特にヴェルディはそういうのがすごくあるんですよ。裏をどうやってつくか、1対1で負けないための手の使い方とか。『勝利のためなら手段を選ばない』って言うのはよくないけど、そういうずる賢さは学べてよかったです。ただ真面目にやってるだけじゃ培われない能力ですし」

勝つことに貪欲であること。綺麗ごとだけでは勝ち上がれない現実。そして時に、反面教師のように見えたものからも多くを吸収してきた。
それでも、どこかで「はみ出す」ことへの憧れがなかったわけではない。
「ないものねだりというか(笑)羨ましくもあれば、あれでよかったなと思う気持ちもある。まあ、いろいろですね」

そして必死に食らいついた末、ついにトップチーム昇格を果たした。だが、周囲の選手は秀でた武器があったものの、彼には圧倒的なものがなかった。全体のバランスを取る存在としては必要とされていたが、個の力は足りず、ただ埋もれていくだけだった。
そんな苦しい状況のなかで、あるひとつの「差」に気づいた。
「何より、メンタル的なところが一番の原因だったと思います。自信を持ってプレーできなかったし、その日その日をなんとか乗り切るのに必死で。ミスもすごく怖くて、消極的になってしまった。本当にサッカーするのが嫌になった時期ですね。同期がどんどん試合に出て活躍していく中で、自分はそのレベルについていけなくて、本当に憂鬱でした。
もともと、そういう部分はすごく弱かったし、『プロのレベルじゃないな』って毎日思いながらやっていました。だからこれといって、良い思い出はあんまりないですね」
それは単に周りのレベルが高かったからではなく、控え目な性格ゆえに、自分自身をどんどん追い詰めてしまっていた。その傾向はユースに入った頃からあり、先輩たちに叱られる怖さのなかで、とにかくミスをしないことばかり考えていた。結果として、失敗を恐れてプレーが小さくなり、また怒られ、さらに萎縮するーーそんな負の連鎖だった。
「でも逆に言えば、プロになって一番感じた”差”ってそこだけかな。長く活躍できる選手は、そこが違う。中島翔哉(浦和レッズ)とかも、全くミスなんて気にせずに『サッカーを楽しみたい』『俺のプレーを見てくれ』っていう強気な姿勢がある。ああいう選手は、どんどん上に行けると思います」

今となって振り返れば「あの時期もよかった」と思える部分もある。だが、当時の自分にそんな余裕はなかった。サッカーしかなかった彼にとって、必死に食らいつくことしか方法はなかった。
「『ちょっとでも…』って、自分の中でも可能性を探し続けてなんとかやってたけど、結局最後はクビになって。そのときは、『まあ、そりゃそうだ。仕方ないな』って思いましたよ。これで残れたとしても、苦しさが続くだけだったので。
なんなら『やっと解放されるな』ぐらいの、ホッとした感覚が少しありました。それぐらいきつかったし、大変だった。別に誰のせいではなく自分が悪かったんですけど、そういう思いがやっぱりありましたね」
「まさか自分が」突然のキャプテン就任
東京ヴェルディを退団後、ここでサッカーを辞めることも視野に入れていたが、それでも当時JFLに所属していたFC今治(以下:今治)に加入した。そこから8年間、J3、J2というクラブの昇格の歴史とともに歩み、やがて「今治の顔」と呼ばれる存在となっていく。
転機となったのは加入4年目。今治がJリーグに昇格し、迎えたJ3初年度。その年からキャプテンを任された。キャンプ中に行われた選手間投票で突然抜擢されたのだ。
「みんなに選んでもらえたのは嬉しかったんですけど、当時はまだ自分のことしか考えてなかったし、チームの状況を見ることもできなかった。半分押し付けみたいな部分もあったのかもしれないけど、そんなふうに思われてたんだってめちゃくちゃ驚きました」

ユース時代は「お前はキャプテンじゃなくても、キャプテンみたいに振る舞うから、責任感を持たせたい他の選手にやらせたい」と言われたことも。ゲームキャプテンになったこともあったが、正式にチームの役職についたのは初だった。だからこそ、そこからの練習はとにかく必死で戸惑いも大きかった。
「その時同じチームには、駒野(友一)さんとか橋本(英郎)さんとかベテランの人たちがいっぱいいて。その中で、まだ中堅の俺がいきなりキャプテンになって『えっ、どうしよう』って……。
目をつけるところを増やさなきゃいけなかったし、隙を見せちゃいけないなって思ってました。毎回毎回気もめっちゃ張って、すごく疲れて。しかもその年はコロナの真っただ中で、半年間活動できない時期だったから、そういうイレギュラーもありましたね」

とはいえ、結果的にそのシーズンは上位に食い込むことができた。チーム全体が同じ方向を向いており、自分たちのスタイルがしっかりと確立していたからだ。そして彼自身もあることに気づく。
「勝てない時期に、ひとりの選手が与える影響なんて、大したことないなってすごく思ったんですよ。それなら誰かに投げかけるより、自分自身がちゃんとやった方がいいなって思って。その姿を見て、『圭史についていこう』とか『サポートしたい』って思ってくれればいい。
もっとキャプテンっぽく、いろんなことを言わなきゃいけないって抱え込んだこともあったけど、そうじゃないなって。結局それをやったからって、これだけ個性の強い人間たちの中で、たかがいち選手が言うことは大した影響はないし、最後に示すのは監督だから。
だから俺は監督を信じて、同じ方向を向いてやることは徹底してたし、そこについてくる選手を増やしていきました」

ピッチの外で揺れる、リーダーシップ
とはいえ、今治で過ごした8年間のうち、最後の2年間は全くうまくいかなかった。加入して以来、初めて試合に出れない時期を過ごし、昨シーズンは半分ほどがメンバー外。ピッチに立てたのも、ほんの数十分だった。
その理由を探ると、最終的に行き着くのは、やはり気持ちの問題だったという。
「もちろん、状況も立場もヴェルディの時とは違うけど、根本は一緒。うまくいかない時期を、うまくいかないまま何とかしようとしてて。楽観的に考えられなかったり、自信を持てなくなったんです」
もともとの性格も相まって、そんな簡単に考え方を変えることはできなかった。
「なんか、考えすぎちゃうんですよね。しかも、それがいい方向に転ぶことってあまりなくて。自分でもわかっているのに、考えすぎちゃう。曲げられないというか、逃げられないというか。物事を考えすぎちゃって、自分の世界に入っちゃったときは止まらないです。

でも、それは自分のいいところでもあるし、捨てたいとも思わない。ただ、そこが上手く噛み合わなくなると、抜け出せなくなるんです。それは良い悪いではなく、自分の性格や今まで積み上がってきたものが、そうさせていたのかなって」
それまで試合に出場できていたからこそ言えていたことも、立場が変われば口にするのが難しくなっていった。現状と役割を切り離して考えなければいけない場面も増え、そこでまた、葛藤が生まれた。
「『お前、出てないくせに』って思う選手も当然いたと思うし、自分自身もそう思ってた。それでも伝えなきゃいけない立場だったし、プレーで示せないぶん、余計に苦しかった。若い選手やイケイケな選手もどんどん増えてきて、みんな実力もある。その中で、自分が何も示せていない現実があって。難しさと苦しさは、かなりありましたね」

そんな苦しいシーズンを乗り越えた先に、昨年、ついに悲願のJ2昇格を果たした。自身は試合に絡めていなかったが、JFL時代からクラブを支えてきた彼にとって、それは一生ものの思い出となった。
「試合すら出てないのに、やばいぐらいうれしくて。『やっぱり俺って、今治への気持ちがすごかったんだな』って、めっちゃ思いました。これまでの充実感も、苦労も、すべて含めた上で、これを超える経験は、きっと残りのサッカー人生ではそうそう味わえないだろうなって」
そんな特別な瞬間を迎え、彼は本気で引退を考えた。クラブスタッフとして今治に関わり続ける道も見えていたし、今治のために自分にできることはなんでもあると思えた。だが、心はまだピッチにあった。
やっとの思いで昇格を果たしたが、特に最後の2年間は心の底から「サッカーが楽しい」とは思えなかった。責任感があったからこそ、そういうものだと言い聞かせることもあったがーーそれでも最後は、自分自身が納得できる形で終わりたかった。
「サッカーがつまらない、苦しいまま終わったら、そのあとの自分はどう思うんだろう……せっかくここまでやってきたのに、モヤモヤしたまま引退したら、一生後悔するだろうなって。サッカーって、一度辞めたらもう二度と戻れない。だから最後は、ちゃんと『楽しい』『好きだな』って思って終わりたい。そう思ったんです」
届いていた想い。日に日に増した、今治への愛
彼の今治への愛が、特別なものとして育ったのには、ふたつの理由がある。ひとつは、在籍期間の長さ。8年もいれば、自然と愛着も湧いてくるだろう。だが、それ以上に大きかったのは、ある転機があったからだ。
それが、昨年退団したときだ。
「応援してくれてる人たちの感じが、すごい良かったっていうか、嬉しかったっていうか。『こんなに応援してもらえてたんだ』『こんなふうに思ってもらってたんだ』って、退団するときに知れたことがたくさんありました」
もちろん、現役時代から常日頃その声援は感じていた。だが、別れのときにはその想いをよりストレートに、大きく伝えてくれる人が多く、胸に深く染みた。
「もう俺がいなくなって会えなくなるから、ここぞとばかりに、みんないろんな思いを会うたびに伝えてくれて。それがすっごく嬉しくて。『俺はこんな幸せな場所にいたんだ』『そう思ってくれる人たちの中でやれてたんだ』って実感したとき、一気にその想いが大きくなったんです」
クラブを去るとなったとき「まあ、しょうがないな」というふうに、もっと淡々と、そこまで感傷的にならないだろうと思った。けれど、たくさんの人のメッセージに心が揺れた。
「みんなのそういう声を聞いたら、『うわあ、やっぱり今治離れたくないな』って、どんどん寂しさがこみ上げていったんです」

そして、8年という年月を重ねてきた中で、今治への愛着を強く実感するようになったのは、キャプテンを務めてからだった。その中で、こんな裏話がある。
「よく先輩とかにいじられていたことなんですけど、ずっと試合に出ていたのにも関わらず、スタジアムで俺のユニホーム着てくれている人が、ほとんどいなかったんですよ。
よくサインとか頼まれたり、練習後にファン対応があったりするじゃないですか。スタジアムでも、自分のタオルやユニフォームが掲げられているとすぐにわかるし、試合後に挨拶でスタンドに行くときも、なんとなく探しちゃう。人気のある選手って、やっぱり求められる数が多いから目に見えてわかるんですよ」
今治のホームスタジアムには陸上トラックがない。そのぶんスタンドとの距離が近く、サポーターが選手を近くで見れると同時に、選手側からもサポーターの表情やリアクションがよく見える。
「でも俺の場合は、ほぼ見なかったです。『お前のユニフォーム着てる人、本当にいねえよな』って言われたこともあります。俺も笑いながら返してたけど、確かに言われてみれば少ないなって思ってました」

だが、キャプテンになった3年目あたりには、自分を応援してくれる人の存在を強く感じるようになっていった。それが徐々に増えていったのかーーと改めて聞くと、彼は口元を緩めて、嬉しそうににやけた。
「でも、ちょっとですけどね?(笑)気持ちとしては増えていったから、うれしかったなあって」
とはいえ、ファン対応については、あまり得意ではなかったらしい。
「ファンの方には『全然こっち見てくれない』『反応してくれないですね』って言われたこともありました。でも、ちゃんと見てたし、探していたんです。
手振ったりとか、大きなリアクションが得意じゃなくて。『おー!』って声をかけたりするのもあんまりできなかったけど、すごく感謝はしていました。『ありがとう』って、心の中でずっと思っていました」
”おちゃらけキャラ”ーーやっと戻ってきた、本来の自分
ここで取材中、突然山出旭がやってきた。どうやら楠美をからかいに来たようだ。「早く帰れよ」と軽くあしらう楠美だったが、その表情はどこか嬉しそうだった。
実は、楠美はチーム内では、”いじられキャラ”や”おちゃらけ”として知られている存在だという。他の選手やスタッフからもそんな話をよく耳にするし、筆者も練習後に、彼がチームメイトから軽くいじられている様子を何度も見かけた。当の本人も不思議と、まんざらでもなさそうだった。

「こんなの、サッカー人生で初めてですよ」
そう思うのも無理はない。これまでのキャリアを振り返るとーー特に今治のときは、まったく違うキャラクターだったからだ。
「『圭史君は厳しいから、圭史くんの前ではきっちりやる』って思われていました。自分も、キャプテンとして、誰かが適当なことをしてたら許さなかったですし、そういうキャラを作っていたところはありました。今治にあれだけ長くいたから、周りからも自然とそう見られちゃうんです。先輩たちはそんなことなかったですけど、後輩たちからはちょっと怖がられたり、厳しい人って見られていたかもしれないですね」
そんな姿もあったからこそなのか、今でも「見せ方がうまい」と評価をする声もある。
「マスさん(増嶋監督)が、プロライセンスの講習で布さん(布啓一郎)と再会したときに、俺の話になったらしくて。そしたら『あいつは見せ方がうまい』って言われたらしいんです」
布啓一郎は2021年に今治で監督を務めていた人物で、増嶋監督が市立船橋高校でプレーをしていたときの恩師でもある。
そんな”見せ方”というものが具体的にどういう意味を指すのか、自分でもわからず、特別意識しているつもりもない。だが、もともとの性格や振る舞いから、「真面目」や「厳しい」といった印象を与えていることは自覚している。
さらに今治時代では、こんな立ち位置でもあったという。
「試合で勝ったときって、よく活躍した選手がメディアや記者の方にインタビューされるじゃないですか。でも負けたときって、誰に聞けばいいのか、迷うと思うんですよ。そういうとき、マジでほとんど俺なんです。だからずっと、"敗戦処理"してました。
たぶん、言ってほしいことをわかってくれる人だろうと思われていたんでしょうね。俺も慣れてますし、『この人はこういう答えが欲しいんだろうな』って、だいたい分かるから。もう腐るほど答えてきてますからね。
そういう役割を求められることも多かったですし、自分もそれをわかっていたから、そう振る舞っていたところはあります。でも話すうちに頭の中が整理されることもあるから、よかったんですけどね」

だが、そんな彼が、今大きく変わりつつある。
「本当にこのチームに来て、マジで変わった。無理してるとかじゃなくて、これが普通の自分なんです。今までは、”自分”というものも作ってきちゃって、抜け出せなくなっていた。でも渋谷に入ってからは、俺のことを知っている人なんて誰もいない中で始めたので、めっちゃ気楽です」
おちゃらけキャラと呼ばれることもあるが、それもまた彼の素の一面だ。今までの姿が仮面だったわけではない。ただ、「サッカー選手として、キャプテンとして、こうあるべきだ」という意識が、自分自身を縛っていた。
「でも今は、仕事もあるからサッカーだけに全てを注げないじゃないですか。そういう中で、自分の中のどうバランスを取るかって考えていたら、こうなっていて。でも、このほうが自然体で、めちゃくちゃ楽です」
それほど自然体でいられるのは、渋谷というチーム、そして周囲の人たちのおかげなのかーーそう問うと、彼は満足そうに頷いた。
「間違いなくそうだと思いますよ。沼さん(岩沼俊介)とか旭も、ああいうふうに接してくれるから、自分も素でいられる。もし『圭史くんは真面目だから〜』って距離を置かれてたら、たぶん俺も変わらないままでしたけど。だから自分も素直に返せるし、それはみんなのおかげです」
彼が名前を挙げた岩沼とは、日頃から一緒にいる時間も長い。岩沼のほうが年上で、キャリアも長いが、互いにプロの舞台で戦ってきた者同士、通じ合う部分があるのだろう。
「沼さんも、多分最初に渋谷に来たときは、ギャップを感じたと思うんですよ。あの人なんて俺なんかよりも、もっとすごいレベルでやってきた人だから。
でも、そういう中で受け入れてくれて、あの人の適当さとかふざけ具合がすごく心地いいです。沼さんといると本当に楽しいし、気を張らなくていいし。沼さんとふざけ出したときなんて、結構マジで止められないんですよ。練習始まっても、ずっとふざけちゃう(笑)」
では、普段は岩沼以外だと誰と一緒にいるのか?と尋ねると、「いないなあ……」と苦笑する。
「でもナベ(渡邉尚樹)とかも仲良いですよ。旭とかもガンガン話しかけてくれるし。というか、旭はもう一線越えてきてるから、あいつはちょっとダメだなと思ってます(笑)でも、来てくれる子に対してはウェルカムですよ」
山出のことをそう言いつつも、特に年下に対しては自分から積極的にいけないタイプだという楠美。兄・姉がいる末っ子として育ったことも影響しているのか、年下との距離感には、少しばかり不器用な部分があるのだろう。

社会人チームである渋谷に来てからは、生活が一変した。慣れない仕事に追われる日々を過ごし、休日も家で寝ることが多い。チームメイトがいない職場では、どこか孤独を感じることもあり、「共感し合える感覚」が薄れていくような、もどかしさを覚えることもある。
それでも今、彼は確かにこう言える。
「やっと、探していたものを見つけられた気がします。さっきも言ったように、今治をやめるときに『サッカーを好きなまま終わりたい』『楽しかった頃の気持ちを思い出したい』って思ったんです。それをずっと探してきたけど、渋谷に来て、それをすごく感じられるようになってきました。
その気持ちを感じられているだけで、もう俺にとっては大成功。みんなとサッカーができて、めっちゃ楽しいんです。試合で結果が出なくて苦しい時もあるけど、それでも『絶対に勝ちたい』と思ってプレーできてる。そう思えるのが、すごく嬉しい。
今までみたいな、行き詰まった頑張りとか、今治のときのキャプテンとしての苦しみもない。純粋に、ただサッカーが楽しい。これがいいか悪いかはわからないけど、背負ってるものが今は何もないんです。
こういう言い方はよくないかもしれないけど、背負ってくれてる選手が他にいるというか。つっちー(土田)だったり、旭だったり、本当に熱い想いを持っている選手がいるんですよ。だから、自分がそこまで思い詰めてやる必要は、今はもうないのかなと。だからそういう意味では、本当に純粋に楽しいんです」
背負うことから解放され、一気に肩の力が抜けた。そんな今の彼は、これまでにないほど自然体でサッカーと向き合えている。

だが一方で、監督やチームメイトからは、あることをよく言われるという。
「普通にやってるつもりでも『ふざけてる』って言われるんです」
もちろん本人にそんなつもりはない。そう言われる理由は今でもわからない。
「『えっ!?どういうこと?そんなつもりないんだけど!』って、最初はめちゃくちゃギャップを感じました。別に嫌とかじゃないし、それはそれで楽しいんですけどね」
決して手を抜いて練習をしているわけではない。だから「ふざけてる」と言われるのも、悪い意味ではないとは思うがーーそう問いかけても、本人は「いや、わかんない」と苦笑する。
「別に怒られてるとかじゃないからね。多分、俺が楽しくやってるのが、ちょっとそういうふうに見られたのかもしれない。楽しいがゆえに、笑うこともあるから」

だが、そんなふうに見られるようになったのも、これまでのサッカー人生では考えられなかったはずだ。そう伝えると、食い気味にこう返された。
「ないないないない!サッカー人生で初めてですよ!練習中に『ふざけてる』なんて言われたのは。本当にそんな経験は一度もなかった。むしろ俺は、そういうのを注意する側の人間だったから。『お前、真面目にやれよ。ふざけてゆるくやってんじゃねえよ』って」
なんだか新しい自分がやってきたみたいだ。今のこの状況は、新鮮でちょっと不思議で、だけど悪くない。むしろ、それが心地いい。だがそんな違和感こそが、本来の自分だ。
「沼さんからは『いじめられているだけだよ』って言われるんですけど、俺は愛されてるって受け取ってます」
そう言って笑った顔は、晴れやかだった。

絶対に壊されたくない、大切なもの
今シーズン、楠美は渋谷で副キャプテンを務める。のびのびとプレーがしたい一方で、これまでの経験を踏まえ、チームから求められるものも少なくないはずだ。率直に、このチームで、どんな存在でありたいかと聞いてみた。
「いや、難しいな。言語化が……これは言っていいものなのか……」
そう言いながらしばらく悩み、隣のグラウンドに目をやる。そんなに言いづらいことなのかと少し不思議に感じたが、ようやく口を開いた。

「もうね、正直、自分が楽しめればいいとすら思ってて」
あまりにも潔い一言に、思わず驚いた。その真意を尋ねると、こう言い切った。
「結果を出したいし、出さなきゃいけないし、副キャプテンとしてチームを引っ張らなきゃいけない。そんなの、もう分かってる」
どこか苦しそうなその表情。責任を背負うことの覚悟と、過去の経験が交差しているのだろうか。だが、彼は「でも」と言葉を続ける。
「それに引っ張られて、苦しいままサッカーをやるのはもう嫌なんですよ。そういうのは、ここではやりたくない」
また少し間を置いて、「これも言っていいのかな……」と悩むように言葉を探す。そして覚悟を決めたように、はっきりと口にした。
「それで副キャプテンを降ろさせられるんだったら、それでもいいと思ってる」

「放棄したいとかじゃないですよ、これは」と念を押すように言いながら、ここからの話ぶりは饒舌になっていく。
「求められたことはちゃんとやる。チームを引っ張らなきゃいけないのも、ピッチに立ったら責任を持ってやるのも、わかってる。そんなのは、俺の根っこにあるものだから。考えなくても勝手に出てくるし、もう大丈夫」
いきなり早口で、次々と言葉があふれてくる。こちらが口を挟む隙すらないほどに。
「でも俺が”そうしなきゃいけない”みたいな意識を持って、わざわざ考えてプレーをするのは、もうしたくないんです。ただただ、ありのままの自分で、楽しくサッカーをしたい。それで結果が出てくれればいいし、チームのみんながついてきてくれたら嬉しい。『圭史くんに助けられてる』って思ってもらえるのが、やっぱり一番嬉しいから」

そして、最後にはこう宣言した。今までで一番、語気を強めながら。
「今は、自分の渋谷の中でそういう立ち位置とか、正直気にしてないです」
そう言って、少しだけ肩の力を抜いたように息を吐き、落ち着いたトーンで続ける。
「もう、みんなが捉えたいように捉えてくれればいいと思ってます。
でもこれは、もしかしたら無責任に見えるかもしれないし、クラブが俺を獲得した意図に反している部分もあるかもしれない。『圭史はキャプテンをやってきて、昇格も経験してきた。だからそのパーソナリティーを、渋谷のためにすべて使ってほしい』そう思ってもらってることも、ちゃんとわかってる」
どこか、苦し紛れにそう言った。クラブが期待している「楠美圭史」と、自分が今大切にしたいもの。その間にあるギャップを感じているからだろう。

「でも、そこで自分を抑え込むことはもうしたくない。変な言い方だけど、それは二の次。結果的にそうなってくれたら嬉しいけど、今の自分が渋谷でプレーすることの一番上にはないです。それよりも、ただみんなと楽しくサッカーをして勝ちたい。
だから自分が納得できるときに終われたら、それ以上に最高なことはない。サッカー選手って、やめたいときにやめられない人ばっかりじゃないですか。ケガしちゃったり、突然クビになったり。だから達成できるかどうか分からないけど、自分が納得してサッカーをやめられたときが自分にとっての頂点ですね。これだけ人生を注いできたものは、なかなかないから。
でも若い選手に切り替えたいって言われたら、それまでだと思う。ましてや、働きながらサッカーをする生活って、本当に大変なんですよ。自分の中でも、『あと何年できるかな』って思うぐらい疲れるから。
勝てなかったゲームのあととかも、めっちゃしんどくて。『やばい、どうしよう、自分がここにいる意味ないな』とすら思っちゃうほど。でも、それも自然と出ちゃうものなんですよね。そこは自分でも受け入れてます」
取材前のちょっとした雑談の中でも、近況を尋ねると「もうしんどいです」と何度も口にしたほどこの生活は疲労がたまる。

「だからそういう意味では、今の俺のあり方は、他の人やクラブの人が求める像とはちょっと違うかもしれないですね。この渋谷でやるっていうことを考えたら。
……でも、それも俺なんですよ。今までは、食事も睡眠も、すべてサッカーのために行動してきた。でも今は、いろんなことを自分の中で許してしまっている。普通に食べたいものを食べるし、ちょっと夜更かしもしちゃったり(笑)」
それで怪我などをしてしまうようでは本末転倒だが、自分の中でいい塩梅を見つけながらやれている今が、とても楽しくて、嬉しいという。
「そうやって自分のペースでやりながら、ちゃんと結果を出したいなって思います。その上で、渋谷を関東一部に昇格させて、自分がいるうちに行けるとこまで行きたい。それが一番の本音です」

ヴェルディや今治の頃みたいに、また苦しいまま終わることもあるかもしれない。そんな想いはもう二度としたくない。
「でも、今みたいに自分のやりたいようにやってて見切られたら『あっ、そうですか。ありがとうございました』って、思えると思うんです。だって、今が本当に楽しいから。それで切られたらしょうがないです。
この記事を読んで、『こいつ全然責任感持ってねえじゃん!』って思う人もいるかもしれない。でも逆に、すごく共感してくれる人もいると思う。
だけど、俺は今こう思ってる。渋谷のことが好きだし、渋谷以外の今までも自分のすべてを注いできた。そのうえで、自分のサッカー人生として考えたときに、今のこの感覚が幸せだなって」
やっと思い出した「楽しさ」。簡単なようで、ずっと、ずっと切望していたものだった。

一拍置いて、「……でも勝ちたいですよ」と続ける。
「絶対に今年、なんとしてでも昇格したい。自分がいるうちに、行けるとこまで行きたい。昇格したときの喜びなんて、誰よりも知ってるつもりだから。街の人がどれだけ喜んでくれて、クラブの人たちがどんな顔をしてくれるか、めちゃめちゃ分かってるし、理解している。
ましてや、あれほど小さなクラブだったから、そこはすごく感じていて。去年の渋谷にいた人たちも、そうだと思う。だから今年も同じ思いをしたいし、そのために自分にできることはあります」

ものすごく究極論だが、少し意地悪な質問をぶつけてみた。ーーもし、試合にまったく勝てなかったとしても、自分が楽しくサッカーをできていれば、それでいいと思えるか。
「まあ、究極ね?絶対そうならないと思ってる。でも逆に言えば、自分が一番楽しくサッカーをやれれば、他のことが多少うまくいかなくてもって思ってしまうくらい、今が楽しい。渋谷というチームでやれていることが、すごく嬉しいんです」

そして最後に「だから」と、こう言い切った。
「どうか、誰もこの楽しさを壊さないでくれ」
今、一番言われたいこと
最後には今シーズン、ここだけはこだわりたいところを聞いてみた。
「これはもう、さっき言った通り、楽しくやること。これ以外はないですよ。考えるまでもないです」
即答だった。それほどに、彼にとって「楽しむこと」は何よりも優先される軸になっている。

とはいえ、これまでのプレーを見てきた人たちからは、意外にも「今の圭史、楽しそうだね」と声をかけられたことはあまりないという。
楽しんでいるつもりでも、それが周囲に届いておらず、自分自身でもまだ出し切れていない感覚もある。だからこそもっと自然に、見ている人たちにも伝わるくらい、楽しめるようになりたいーーその想いは、誰よりも強い。
「今俺が言ってるのって、ふさけた感じの楽しさではないじゃないですか。苦しい経験があった中での行き着いたものだから、実現できた時って本当に最高だろうなと思います。そこは想像すると楽しいし、それを表現したいです。本当に伝わったら、一番最強な状態になれるので」

「だけど今の渋谷って、周りから見ると、どこか必死で切羽詰まってるように見えていると思います。いいチーム、いい選手なのに、苦しそうで、何か別のものと戦ってるんじゃないかって。『勝たなきゃ』っていうエネルギーが先走って、『失敗したらどうしよう』って怖さが生まれてしまう」
そんなチームの現状に、もどかしさを感じてしまう。だからこそまずは自分が、変化のきっかけになれるよう体現したい。
「それを乗り越えて自分たちらしくやれるようになったら、きっと負けることはなくなると思います。周りがとやかく言うことでもないので」

そして最後に、もし今後、彼のことを見かけたら、こんな言葉をかけてあげてほしい。
「この話をしたあとに、俺のことを見てくれたら見方が変わってくると思う。だから、そのあとに会ったとき、『圭史、最近楽しそうだね』って言ってくれたら、俺というものが出てきたなって思います。なので、ぜひ言ってください!今年の目標です」
取材・文 :西元 舞
写真 :福冨 倖希
企画・構成:斎藤 兼、畑間 直英
UNSTOPPABLES バックナンバー
#1 渋谷を背負う責任と喜び。「土田のおかげでJリーグに上がれた」と言われるためにーー土田直輝
#2 頂点を目指す、不屈の覚悟。全ては世界一の男になるための手段ーー水野智大
#3 冷静さの奥に潜む、確かな自信。「自分がやってきたことを発揮するだけ、『去年と変わった』と思わせるために」ーー木村壮宏
#4 這い上がる本能と泥臭さ。サムライブルーに狙いを定める渋谷の捕食者ーー伊藤雄教
#5 問いかける人生、答え続ける生き様。「波乱万丈な方へ向かっていく。それがむしろ面白い」ーー坪川潤之
#6 サッカーが導く人生と結ぶ絆。ボールがくれた縁を、これからも。ーー岩沼俊介
#7 楽しむことを強さに変えて。夢も、欲も、まっすぐに。ーー小沼樹輝
#8 誰かのために、笑顔のために。誇りと優しさが生む頂点とはーー渡邉尚樹
#9 九州で生まれた男の背骨。「やっぱり男は背中で語る」ーー本田憲弥
#10 選手として、父として。見られる過去より、魅せたい現在地ーー渡邉千真
#11 余裕を求めて、動き続ける。模索の先にある理想へーー宮坂拓海
#12 この愛に、嘘はない。激情と背中で示す覚悟の真意とはーー鈴木友也
#13 憧れた側から憧れられる側へ。ひたむきな努力が導く、まっすぐな未来ーー大越寛人
#14 楽しいだけじゃダメなのか?渋谷イチの苦労人が語る「俺は苦しみに慣れちゃってる可能性がある」ーー高島康四郎
#15 かつて自分も”そっち側”だったからこそ、わかる。「もう誰のことも置いていきたくない」ーー志村滉
#16 絶対の自信を纏う、超こだわり屋のラッキーボーイ「必ず俺のところに転がってくる。そう思ってるし、信じてる」ーー青木友佑
#17 SHIBUYA CITY FCに人生を懸けた男「俺をこんなにも好きにさせた、このクラブが悪い!」ーー植松亮
SHIBUYA CITY FC
渋谷からJリーグを目指すサッカークラブ。「PLAYNEW & SCRAMBLE」を理念に掲げ、渋谷の多様性を活かした新しく遊び心のあるピッチ内外の活動で、これまでにないクリエイティブなサッカークラブ創りを標榜している。
渋谷駅周辺6会場をジャックした都市型サッカーフェス「FOOTBALL JAM」や官民共同の地域貢献オープンイノベーションプロジェクト「渋谷をつなげる30人」の主宰、千駄ヶ谷コミュニティセンターの指定管理事業など、渋谷区での地域事業活動も多く実施している。
お問い合わせ
担当:畑間
問い合わせはこちら