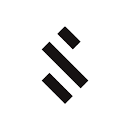どんな場所でも、俺はここで貫く「納得いかないことに対しても、納得いくまでやり続ける」ーー佐藤蒼太【UNSTOPPABLES】 #21
2025年8月4日
|
Article
「4年間でよかったこと……うーん、難しいな。マジでないんだよな」
高校時代、本気でサッカーに打ち込んできた者ほど、大学での温度差に戸惑うケースは少なくない。プロを目指す者もいれば、そうではない者もいるため、大学サッカーに生まれる熱量の差は時に激しい。もちろん、目標の大小に関わらず、真剣に取り組む選手もいるが、そうした存在は高校時代に比べると限られてくるのかもしれない。たとえ関東リーグの強豪大学の出身者であっても、その違和感を覚えた選手は決して少なくないだろう。
では、東京都リーグ所属の大学でプレーしていた佐藤は、どんな現実を目の当たりにし、何を感じていたのだろうか。彼の言葉がその答えの一端を教えてくれる。
【UNSTOPPABLES~止められない奴ら~】
昨シーズン、関東2部への昇格を決めたSHIBUYA CITY FC。その栄光の背後には、ただの勝利以上のものが隠されていた。選手たちの揺るぎない自信と勢いは、彼らの人生に深く刻まれた歩みから来ている。勝利への執念、それを支える信条。止まることを知らない、彼らの真の姿が、今明らかになる。
第21回は、大学4年時には東京都リーグ2部でプレーしていた佐藤蒼太。卒業後はJFLのクラブへの加入を果たした数少ない存在だ。そんな彼が、大学サッカーで直面した現実と、自らの信念を語った。
佐藤 蒼太(さとう・そうた)/ MF
2000年8月12日生まれ。埼玉県熊谷市出身。175cm、70kg。地元の強豪クラブ、クマガヤSCでプレーし、東京成徳大学深谷高等学校へ進学。3年時にはキャプテンとしてチームを牽引した。その後大東文化大学に進学。3年時には東京都2部リーグに降格する苦しいシーズンを経験したが、4年時には見事1部リーグへ復帰を果たす。大学卒業後はJFLのティアモ枚方に加入して、昨年からSHIBUYA CITY FCでプレー。右サイドから仕掛けるスピードと推進力を武器に、攻撃の起点としてピッチを駆け抜ける。
進路選択をやり直したい
当時、高校3年生だった佐藤の夢は、プロサッカー選手ではなく体育教員になることだった。そのため、教員免許が取得できる大東文化大学(以下、大東)のスポーツ・健康科学部に進学。出身である埼玉から通える関東圏内で、進学先を絞っていた。
出身校の東京成徳大学深谷高校(埼玉県)では、インターハイ県準優勝、選手権県ベスト4入り。全国的に見れば突出した成績とは言えないかもしれないが、その活躍ぶりが評価され、大東のサッカー部から練習参加の誘いが届いた。
教員になるための経験として、部活動を続けておいた方がいいかもしれないーーそんな現実的な判断から、彼は大学でもサッカーを続ける道を選んだ。将来のキャリアを見据えたとき、体育教員として母校に戻るという選択肢も、彼の頭の中にはうっすらと描かれていた。

しかし、いざ始まった大学でのサッカー生活は、想像していたものとは大きくかけ離れていた。
「高校サッカーは『絶対に選手権に出るぞ!』っていう明確な目標があったし、高校でサッカーを辞めちゃう人も多いから、どのチームでもある程度まとまりがあったと思う。でも大学に入ってみたら、本気度が低い人が多くて、練習への向き合い方とかチームの雰囲気がどこかバラバラで……。正直、何のためにサッカーをしてるのか、分からなくなる瞬間もあったくらい」
緩んだ空気がチーム全体に蔓延しており、それが当たり前になっていた。自主練をするにしても、他の部活との兼ね合いでグラウンドの利用時間は限られていたが、それ以前に自主的に練習に取り組む選手はほとんどいなかったという。

そんな中、彼は1年時ながらAチームに上がり、リーグ開幕戦ではいきなりスタメンに抜擢された。本来であれば喜びを感じるはずの出来事だが、当時の彼の胸中はまるで違っていた。
「正直、この場所でサッカーをやっても意味ないなってずっと思ってたし、ただなんとなく続けてるだけの時間が一番辛かった。『まあ、1年ぐらいやるか』って感じでやってたね」
しかも、当時Aチームに所属する1年生は、彼を含めてわずか2人であり、練習前の準備は、すべてその2人に任されていた。部のルールでは、練習開始の1時間前に集合する決まりがあったが、1年生は授業の時間割がぎっしり詰まっているため、準備を終える頃にはすでに練習が始まる直前で、ストレッチなど身体のケアをする余裕もなかった。
「ビブスは毎日20枚くらい持ち帰って、俺らが洗ってたし、✕はフラットマーカー、〇は普通のマーカー、△はコーンって書かれた紙を渡されて、それ通りに並べるのも2人でやってた。ボールの空気入れから簡易ゴールの設置まで、とにかく全部。
そういうのもひっくるめて、組織としてよくなかったと思う。『マジで大学選びミスったな』『高3の進路選択をやり直したい』って、何度も思った。他の大学に行ってたら、もっと違ってたんじゃないかって。まあ、他のチームのことは詳しく知らないけど、あの頃の大東よりは絶対にマシだったと思う」
頑張ってる人はダサい
とりあえず1年続けたら辞めようーーそんな思いを抱えながら過ごしていた彼だったが、ちょうど大学1年が終わる頃、新型コロナウイルスが大流行。感染拡大防止のため、世の中は一気にステイホームの生活へと移り変わった。
自宅で過ごす時間が自然と増えたことで、さまざまな情報に触れる機会も多くなった。それまで「卒業後にサッカーを続ける=Jリーガーになるしかない」と漠然と思い込んでいたが、JFLや関東社会人リーグといった、別の道があることを知った。
そのタイミングで、高校時代の恩師から連絡が入り、OBを集めた練習会が開かれることに。久しぶりにボールを蹴り、昔の仲間と汗を流すうちに、忘れかけていたサッカーの楽しさがふと蘇ってきた。さらにその場には、東南アジアでプレーしている選手や、自分と同じように大学でもサッカーを続けているOBの姿もあった。彼らと話を重ねるうちに、ある感情が湧き上がってきた。
「自分がこれまで必死にやってきたサッカーが、こんなかたちで終わるのがすごく嫌だった。正直、本気でやっていない人とひと括りにされるのが、どうしても納得いかなくて。
『頑張っていたら、自分の中で得られるものが違う』とか、『本気でやってきた人とそうじゃない人は、見えない部分で差が出る』っていう意見もあるかもしれない。でも、世間一般的に見たら、結局変わらないから」
そのことを考えれば考えるほど、このまま終わる自分が許せなくなった。そこで初めて、自分の中に明確な目標が芽生えた。「卒業後はJリーガーになる。サッカーをやれるところまで続けてみよう」と。

ただし、自分の気持ちが固まったからといって、周囲の環境が簡単に変わるわけではない。そこには大きなギャップがあった。
「当時のサッカー部って、『卒業後もサッカーをやりたい』なんて言うのが恥ずかしい、みたいな雰囲気があった。だから、そのときもコーチにしか言わなかったんだよね。周りの選手に話しても、どうせバカにされると思ってたから。
でも上を目指すって決めたから、この環境でもやるしかない。『自分のためだから』って割り切ってやってきたけど、『頑張ってる人はダサい』みたいな空気の中で続けるのはマジで辛かった」

東京都2部リーグへの降格
それでも、3年生になれば少しずつ状況は変わっていった。人数の少なかった自分たちの代は、自然とまとまりが生まれ、チームの雰囲気も以前に比べて格段にやりやすくなっていった。
「自分はどんな空気でも、周りに流されないって決めてたから、ダラダラやることは全然なかった。練習の質が良くなるように、自分から主体的に声をかけたり、盛り上げたりするようにした。
高校3年のときはキャプテンで、90分間声を出さない時間がないくらい、ずっと盛り上げてた。それは誰よりも自信があったし、背中でも引っ張ってた。マジで高校のときの俺を知ってる人に聞いてみてほしいぐらい。まあ、今の渋谷ではあんまり声出してないけどね(笑)」

少しずつ気持ちが前を向き始めた矢先、大学3年のシーズン開幕1週間前に、膝の靭帯を負傷。約3ヶ月間の戦線離脱を余儀なくされる。
そして夏にアミノバイタルカップの本戦で復帰したものの、再び同じ箇所を痛めてしまう。満足にプレーできない時間が続く中、チームの調子も上がらず、結果としてその年、大東は東京都リーグ2部への降格が決まった。
チームとしては同じ方向を向いてまとまっていた実感はあり、「落ちるべくして落ちた」という雰囲気では決してなかった。
だが、何よりもショックだったのは、大学4年という進路に直結する大事な時期に、自分の所属するチームが”東京都2部リーグ”で戦わなければいけないという現実だった。
「普通、東京都2部からプロなんて、ありえないじゃん。試合にスカウトの人が来ることなんてまずないし、声がかかるチャンスすらなかった。『この環境でやってて、さらに落ちるか……』って思ったよね」

とはいえ、2部リーグに降格したものの、そこでの結果はまさに圧勝だった。シーズン成績は19勝0分1敗。2位の東京大学に勝ち点差14をつけて、堂々の1位で東京都1部リーグへの復帰を果たした。
怪我人が多く、教育実習などで主力が不在の試合も少なくなかったが、それでも毎試合のように複数得点を挙げるなど、まさに力の差を見せつける内容だった。
だが、そこまで圧倒的に勝ってしまうと、それはそれで別の苦しさがあった。実力が通用しないことへの悔しさではなく、「物足りなさ」とでもいうような感情だった。
「モチベーションもないし、普通にやってたら勝てる。だから、成長してる実感も全くなかった」
努力して積み上げてきた力を、本気の勝負で出し切るような機会がなかなか訪れない。結果は出ているのに、目標も手応えもぼやけているようだった。

大学4年間でよかったことは何かと尋ねると、「なんだろう…ないことはないんだよな……」と、言葉を探すようにしばらく考え込んだ。
「サッカーで上を目指す環境でもなかったし。4年間でよかったこと……うーん、難しいな。マジでないんだよな」
それでも時間をかけて、自分の中にある答えを引き寄せるように、「でも」と前置きして静かに続けた。
「そういう環境だったからこそ、上を目指そうって決められたのかも。もし、関東1部とか2部の大学に行って、それなりに試合に出てたら、多分そこで満足して終わっていたと思う。
だから、周りの環境に流されずに自分の決めたことをやり続ける”貫く強さ”みたいなものは、この4年間で得られたと思う」
ただ、それは"強いて言えば”の話にすぎない。
「他にも、もっといろいろあったはずなんだけど……でも、ここでパッと出てこないってことは、そういうことだったのかな」
そうつぶやいたあと、少しの沈黙が流れた。その言葉の裏には、楽しかったことよりも、悔しさや虚しさのほうが強く刻まれていた。
JFL加入を掴んだ、這い上がりの軌跡
そんな大学生活を経て、卒業後はティアモ枚方への加入を果たした。東京都2部の大学から、J1から数えて4番目のカテゴリーであるJFLのチームに入団するのは、決して容易なことではない。そこには、地道な努力と周囲の支えがあった。
彼の中で大きな存在となっていたのが、現・大東文化大学のコーチの鈴木暢二(すずき・ようじ)氏。自身も大東サッカー部出身で、佐藤にとっては遠い先輩にあたる。
「毎日、オフの日でも暢二さんと2人でグラウンドに行って、自主練をずっとやってた。クロスとかシュート、ドリブルの練習にみっちり付き合ってくれて。
暢二さんがそうやってずっと気にかけてくれてたから、環境を変えるという選択肢は取らなかった。サッカーを続けようと思えたのも、高校の先生が声をかけてくれたのもあるけど、暢二さんがうまくなれる方法を一緒に探してくれたことが大きかったな」

そしてもうひとつ、辛い大学生活のなかでも頑張れた理由がある。それは、サッカー部以外の仲間たちの存在だった。
というのも、彼が私生活でサッカー部の仲間と遊びに行くことは、ほんの数回だけ。指で数えられる程度だった。4年生になって、チームでバーベキューをしたときには顔を出したものの、それ以外は気の合う数人とたまに話すくらい。心から信頼できる仲間がいる場所は、サッカー部の外にあった。
「サッカー部とは全然つるんでなかったんだけど、今でも連絡を取り合うくらい仲のいい友達が学部内にいた。バレーボール部のキャプテンの子とか、陸上部のやつとか。
他の部活でも、自分と同じような境遇で頑張ってる人がめっちゃいて、そういう仲間たちと愚痴を言い合いながらも励まし合ってた。その人たちの姿を見て、『俺もここで頑張らないとな』って思えたのが、大きな理由かもしれない。みんな今でも競技を続けているから、嬉しいよ」

結果として、卒業後にはJFLのクラブに加入することができた。では、支えてくれた人たちの存在を抜きにして、自分自身の行動や努力に焦点を当てたとき、その要因は何だったのかを聞いてみた。
「ティアモとは、コネやつながりは一切なかった。だから自分でプレー映像を作って、いろんなチームを探しては連絡して、練習参加のチャンスをもらえた。
大学1年のときからずっと、サイドで仕掛けるプレーは自分の強み。その縦への推進力とか、とにかく迷いなく全部勝負できる姿勢が評価されたのかもしれない。あとは、逆に言えば東京都リーグっていう環境だったからこそ、のびのびとプレーできた。
もちろん、技術が足りてないのは自分が一番わかってる。でもそのぶん、スピードを売りにしてるし、その中でも『やれるぞ』っていう感覚は持ってた。環境が悪いって言いながらも、自分がちゃんと頑張って『絶対どうにかしてやるぞ』ってずっと思い続けてた」

納得いかなくても
そんな苦難の道を歩んできた彼だからこそ、ここだけは誰にも負けないと胸を張れるものがある。
「自分に対して厳しいのは、チームで一番だと思う。自分の中で許せる・許せないの基準が高いし、自分の軸とかけ離れたことに対しては、踏み込まない。
だからこそ、良くも悪くもあんまり楽観的になれないことが多いかも。人に何かを言われてどうこうっていうより、自分の中でうまくいかなかったときにリズムを崩す。それが弱さかな」
そこまで考えるのも、持ち前の真面目な性格ゆえだろう。実際、これまでも周囲から「真面目だね」と言われることが多く、それは本人も自覚がある。
「深入りしすぎない、ちょっと客観的に見る性格だからこそ、真面目により映るのかもしれない。『俺が、俺が』みたいな勢いもマジでないし、面白くない性格だと思う。本当に表裏もない気がする。
みんなでワイワイするよりも、ちょっと一歩引いて見てるし、あんまり心は開示してないかも。自分でもなんでかわかんないけど、昔からそうなんだよね」

とはいえ、普段大人しい彼が、もし自分の中にある強い思いをもっと外に出したら何か変わるのではーーそんな問いを投げかけてみたが、彼は「うーん」と首をかしげる。
「感情的になるべき瞬間にちゃんと伝えればいいかなって思う。だから大事な時以外はあまり出さないかな。
でも俺は自我が強い方だと思うし、自分なりの考えはちゃんとある。誰かに感情的に言われたときに、それを受け入れられない瞬間も多いから。例えば、自分では『こういう意図があって、このプレーを選んだ』って考えてるのに、相手はその瞬間のプレーだけを見て、『なんでそうしないんだよ』って感情的に言ってくると、あまりその意見を聞かないっていうか、響かないことが多い。
感情的になっていい場面もあるけど、それがすべてじゃないから。だから心の中で処理することが多い。でも自分はあまり感情を表に出さないタイプだけど、内に秘めているものは熱いと思う」

そんなふうに自己分析ができてるゆえなのだろうか、こんな本音もこぼれる。
「めっちゃリアルな話を言うと、サッカーをいつまで続けられるかわからないって思うから、毎年毎年にかける思いは強いと思う。
去年の昇格戦の直前に右足を怪我して、痛み止めを打ちながら試合に出てたんだけど、『この試合で引退してもいい』って思うぐらいの気持ちでやってた。あとは、そうやって思えるくらい『絶対にこのチームで昇格したい』っていう思いが、去年の渋谷にはあった気がする。
だからもし今年でサッカーが終わるとしても、自分の中で納得できるように、日々の練習に向き合うことだけはこだわりたい」

そして、このインタビューの企画名にも通じる、”誰にも止められない瞬間”について聞いたときの答えにも、彼なりのブレない信念が表れていた。それは、これまで積み重ねてきた歩みと地続きになっている。
「自分がやりきると決めたことに対してやっている瞬間だけは、誰が何を言っても曲げないし、覆らない。今だったらサッカーも仕事も、100%でやるっていう軸は変えないし、自分の決めたことは、絶対に最後までやり遂げる」
どんな場所だったとしても、”やりきる”という信念。これは大学時代の引退ブログにも綴られていた想いだ。
「当時、大学生の自分がすごく意識してたのは、”どこに行くか”じゃなくて、”自分が選んだ道を正解にするための努力をする”っていうこと。
環境はよくなかったし、社会人クラブに移ろうって何度も思った。でも自分の中で『ここを正解にする』っていう気持ちを持ってから、チームを変えようとは思わなかった。
高校の時に、自分がキャプテンをやろうって決めた理由も、チームを全国に連れていくためだったら、自分がキャプテンをやった方がいいなって思ったから」
普段は控えめで目立たない彼だが、その胸に宿る信念は誰よりも熱く、揺るぎない。静かな佇まいの中に熱い覚悟を秘め、自分の意志を貫く姿勢こそが、彼の人生の根幹を成している。

「自分に認めてもらえる自分になるために、どんな形であれ、自分自身が納得できる人生だったら、それでいい。漠然としてるけど、例えばめちゃくちゃ金持ちになりたいとか、有名人になりたい欲はないけど、その時の自分が納得できる人生を送れれば、それが頂点。
たとえ納得いかないことに対しても、納得いくまでやり続ける。どんなことを考えても、結局行き着くところは一緒」
回り道にも思えた選択。ほかにいくつもあったであろう可能性。それでも「ここで勝負をする」と腹をくくった彼には、ただの根性論では片付けられない、強い説得力があった。
条件ではなく姿勢が、その人の価値を決める。彼はそれを証明し続けている。

取材・文 :西元 舞
写真 :福冨 倖希
企画・構成:斎藤 兼、畑間 直英
UNSTOPPABLES バックナンバー
#1 渋谷を背負う責任と喜び。「土田のおかげでJリーグに上がれた」と言われるためにーー土田直輝
#2 頂点を目指す、不屈の覚悟。全ては世界一の男になるための手段ーー水野智大
#3 冷静さの奥に潜む、確かな自信。「自分がやってきたことを発揮するだけ、『去年と変わった』と思わせるために」ーー木村壮宏
#4 這い上がる本能と泥臭さ。サムライブルーに狙いを定める渋谷の捕食者ーー伊藤雄教
#5 問いかける人生、答え続ける生き様。「波乱万丈な方へ向かっていく。それがむしろ面白い」ーー坪川潤之
#6 サッカーが導く人生と結ぶ絆。ボールがくれた縁を、これからも。ーー岩沼俊介
#7 楽しむことを強さに変えて。夢も、欲も、まっすぐに。ーー小沼樹輝
#8 誰かのために、笑顔のために。誇りと優しさが生む頂点とはーー渡邉尚樹
#9 九州で生まれた男の背骨。「やっぱり男は背中で語る」ーー本田憲弥
#10 選手として、父として。見られる過去より、魅せたい現在地ーー渡邉千真
#11 余裕を求めて、動き続ける。模索の先にある理想へーー宮坂拓海
#12 この愛に、嘘はない。激情と背中で示す覚悟の真意とはーー鈴木友也
#13 憧れた側から憧れられる側へ。ひたむきな努力が導く、まっすぐな未来ーー大越寛人
#14 楽しいだけじゃダメなのか?渋谷イチの苦労人が語る「俺は苦しみに慣れちゃってる可能性がある」ーー高島康四郎
#15 かつて自分も”そっち側”だったからこそ、わかる。「もう誰のことも置いていきたくない」ーー志村滉
#16 絶対の自信を纏う、超こだわり屋のラッキーボーイ「必ず俺のところに転がってくる。そう思ってるし、信じてる」ーー青木友佑
#17 SHIBUYA CITY FCに人生を懸けた男「俺をこんなにも好きにさせた、このクラブが悪い!」ーー植松亮
#18 絶対に壊されたくない、やっと思い出せた楽しさ「副キャプテンを降ろさせられるんだったら、それでもいい」ーー楠美圭史
#19 器用貧乏?いや、今は違う「俺の中に神様はもういない」ーー青木竣
#20 考えたからこそ、”あえて”何も考えない「今日もやっちゃおーよ」ーー小関陽星
SHIBUYA CITY FC
渋谷からJリーグを目指すサッカークラブ。「PLAYNEW & SCRAMBLE」を理念に掲げ、渋谷の多様性を活かした新しく遊び心のあるピッチ内外の活動で、これまでにないクリエイティブなサッカークラブ創りを標榜している。
渋谷駅周辺6会場をジャックした都市型サッカーフェス「FOOTBALL JAM」や官民共同の地域貢献オープンイノベーションプロジェクト「渋谷をつなげる30人」の主宰、千駄ヶ谷コミュニティセンターの指定管理事業など、渋谷区での地域事業活動も多く実施している。
お問い合わせ
担当:畑間
問い合わせはこちら