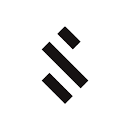「俺が」決める。数奇な29年を経て、背番号9が背負う矜持「もう覚悟は決まっている」ーー政森宗治 【UNSTOPPABLES】 #25
2025年9月6日
|
Article
GKからFWへ。そして元ホスト。
これほど数奇な人生を歩んできたサッカー選手は、他にいるだろうか。2023年夏、渋谷へ加入したストライカー・政森宗治。論理的に自己を分析し、迷いなく「俺が」と言い切る強靭なメンタリティ。その覚悟を知れば、誰もが彼から目を離せなくなるだろう。
【UNSTOPPABLES~止められない奴ら~】
昨シーズン、関東2部への昇格を決めたSHIBUYA CITY FC。その栄光の背後には、ただの勝利以上のものが隠されていた。選手たちの揺るぎない自信と勢いは、彼らの人生に深く刻まれた歩みから来ている。勝利への執念、それを支える信条。止まることを知らない、彼らの真の姿が、今明らかになる。
第25回は、渋谷の背番号9・政森宗治。転機を繰り返しながら、勝負強さと駆け引きを武器に歩んできた男が、いま渋谷で示そうとしている覚悟とはーー。
政森宗治(まさもり・ときはる)/ FW
1996年2月28日生まれ。兵庫県出身。175cm、74kg。地元クラブの尼崎南SCから長洲SCを経て、神戸国際大学附属高校に進学。卒業後はGKからFWへ転向すると、エベイユFCで1年目にしてリーグ得点王に輝く。その後はFC徳島、ブリオベッカ浦安で経て、2023年より東京蹴球団に加入。同年8月にSHIBUYA CITY FCへ移籍。抜群の得点感覚に加え、落下地点の予測や相手より先に体を入れる駆け引きにも秀でる。ピッチで結果を残すことに徹する渋谷のエースストライカー。
夜の世界を生き抜く“戦略”
政森宗治といえば、やはりあの肩書きを外して語ることはできない。
それはーー“元ホスト”だ。
少し野暮ではあるが、まずはその話から切り込んでみたい。
2018年1月、彼は地元である兵庫を離れてブリオベッカ浦安に加入した。だがわずか数か月後の3月、早くも退団を決断。
なぜそこまで早くチームを去ったのか。その理由は後に触れるとしてーー退団したその月に新宿・歌舞伎町に足を踏み入れ、ホストとして働き始める。きっかけは、東京で知り合った友人にオーナーを紹介されたことだった。
「『かっこいいし、やってみたら?』って感じで誘われて。俺のおかんも昔スナックをやってたから、夜の仕事に偏見はなかった。最初、体験入店に行ったら『あ、これなら俺でも行けるわ』って思って、次の日には本入店してた。マジでノリだったね」
そこから生活は一変。夜9時から深夜1時まで、活動時間は夜型へ切り替わった。新人時代は「掃除組」と呼ばれ、ヘアメイクを整えた状態で営業の1時間前に集合し、掃除やミーティングに励む。そんな下積み時代からのスタートだった。
始めた頃の時給はわずか千円。都内で一人暮らしなど到底できる金額ではなかった。1か月間だけホストの寮で共同生活を送ったが、寮費やヘアメイク代で給料はあっという間に消えていった。
「月一桁万円だよ。やばいっしょ。バック(歩合)もあるけど大したことないから。だから早く抜け出したかったし、いつまでも掃除組と一緒なのも嫌じゃん。めっちゃ頑張ってたね」
モチベーションはただひとつーーお金を稼ぐこと。なんとも単純明快だが、「そんくらいじゃない?女の子と喋って、お酒飲んで、お金を稼げて楽しいし。逆の立場だったら楽しいでしょ?」と、臆することなく口にする。
この3年間、サッカーとはほとんど無縁だった。せいぜい月に一度、店舗の企画で新宿・ビックロの上で開かれるフットサル大会に参加するくらい。経験者もいれば初心者も混ざる大会で、長年ボールを蹴ってきた彼にとっては遊びに過ぎなかった。

そしてホストの世界もまた、スポーツと同じ“実力主義”だ。売り上げを伸ばすためには、まずは自分の担当客を地道に集めるしかない。そのため当初は、出会う女性と片っ端から連絡先を交換する日々を送った。
「同業の人とかお偉いさんとかも来るから、1日で何人来てたかは分からない。でも自分の名刺を300枚刷っても、ほぼ毎日なくなるくらいだった。LINEの友達は6000人くらいは普通にいたし、もう誰が誰だか分からなくなってた」
当然、整理の工夫も必要になる。名前の前に来店日や初回かどうかをメモし、業界用語などを使って分類していった。
ただし、ホスト業界には独特のルールがある。他のホストの担当客になった女性の連絡先は、たとえ一度つながっていても必ず削除しなければならない。自分が辞めるか、別の店に移って指名が変わらない限り、その人は他人の客。グループチャットには「この子は〇〇の客なので削除してください」と通知が回る仕組みだ。それでも、そんな制約があろうと彼の手元には6000人近い連絡先が残っていた。
「男は取り合いのいざこざがないから、逆に仲間意識は強い。だから他の従業員に気に入られることが大事。あとは黒服とも仲良くしておけば、お客さんをつけてくれたり自分の都合に合わせて動いてくれたりする。まずは周りと仲良くなることからだね」

とはいえ、それ以上に大切なのはやはり目の前にいるお客さんとの関係だ。自分の担当にするには、何よりもコミュニケーションスキルが欠かせない。
「いきなり最初から『どこ住んでんの?』とか年齢や職業を聞かれたら嫌な子は嫌じゃん。しかも夜の世界にはいろんな子が来るから。でも相手から話させる分にはOK。だから何歳か聞くんじゃなくて、答えさせる流れに持っていけばいいだけ。あとはテーブルマナーを守ってテンポよく喋る。それで十分」
そう言い切るが、もちろん簡単なことばかりではなかった。情緒が不安定な女性など、今まで接したことのないタイプも多く、予測がつかずに戸惑う場面も少なくなかった。
それでも異性に苦手意識がない彼にとって、会話自体は大きな壁ではなかった。むしろ大変だったのは別にあるーー「お酒」と「連絡」だった。
お酒は嗜む程度なら好きだが、飲みすぎるのは苦手だ。そしてそれ以上に苦労したのが「連絡」。彼はなんと、1時間ごとにアラームをかけて返信していたという。
「まだ誰の担当にもなっていない子には、他のホストが連絡してない時間を狙って返さないといけない。誰にでも、自分のお客さんになるチャンスがあるからね。
例えば初回で来てくれた女の子に『今日はありがとうね』って送るとする。でも順番に送ったら、LINEの通知は最後に送った人が一番上に表示される仕組みだから、最初に送った人は下に埋もれちゃう。かといって遅く送れば、『返信が遅い』と思われるわけ。
だから他のホストの動きを見ながら、その日に誰がついたかを全部黒服に聞いて確認してた。『こいつはすぐこの後誘ったりするタイプだから、早めに止めとかないとな』っていう駆け引きはめっちゃしてた。
当たり前だけど、まだ誰のものでもない子は、自分の客になっちゃえば変えられないから。あとはお金を使ってくれるかどうかは、そのホストの腕次第。だからタイミングと言葉選びと(連絡を)返す時間を考えるのが一番大変だった」
次々と飛び出す高等テクニックの数々に、思わず圧倒される。それだけに、ここまでの駆け引きやコミュニケーションスキルには、やはり才能やセンスが必要なのではないか。そう問いかけると、「それに関してはいらない。やっていくうちに誰でも絶対に分かる」と断言した。
ただし、そこには前提がある。
「もちろんやる気がないとダメ。やる気がないなんて論外だから。だから俺はいつも言ってるの。『どんなに冴えない男でも、どれだけ女の子と喋れなくても、どんなに陰キャでも、どんなやつでも頑張って努力すれば100万は絶対稼げる』って。このラインは誰でも頑張ればいけるのよ。その先はもうセンス。それができなかったら、ずっと掃除組のまま。
でも俺は楽した方だと思うけどね。センスがある方だったから。もちろん誰よりも努力した自信はあったけど」

そして話題は再び「駆け引き」に戻る。連絡ひとつにしても、売り上げを伸ばすために、結局のところそこが肝になるという。
当時は、いまでは風営法で禁止されているランキングが店の前に掲示されていた。その順位が月の締め日で決まる仕組みだった。
締め日が近づくと、店内はまるでボーナスタイム。ホストたちはこぞって客に財布を開かせようとし、熾烈な競争が繰り広げられていた。締め日に一気に大金を使う客もいれば、毎日のように通って支える客もいて、実に多種多様だった。
だからこそ結果は読めない。60人ほどのホストがしのぎを削る中、数十万円の売り上げで1位になれる日もあれば、数百万を動かしても届かない日もあった。
「指名本数とか細かい仕組みはいろいろあるけど、俺の場合は毎日来る人と、月に一度ドカンと使う人を組み合わせてやりくりしてた。それと、お客さんが来ない日のことを“お茶を引く”って言うんだけど、それを絶対にしないようにしてた。
だから必ず1人は呼んでたね。自分のお客さんは自分の管轄内だから、最低でも1人は絶対に来る。100万以上使う手札を常に5人キープしておいて、他は来ればラッキー。それに売り上げを上乗せできればさらにラッキー。別に自分から無理に営業することもなかったよ。来そうな雰囲気だったら誘うことはあったけど、『来い』みたいに強引には言わなかった」

では、客はなぜホストクラブに足を運ぶのか。ホスト側からすれば知る由もないが、ふと聞いてしまった。
「えー?」と一瞬考え、ズバっと答える。
「好きだからじゃない?俺のことが。それしかないでしょ」
あまりの自信満々な答えに、一瞬言葉を失う。だが、笑いながら補足された。
「だって、そうじゃないと来ないでしょ。逆に興味のないやつに金とかプレゼントをあげたいと思う?好きな人とか彼氏相手だったら『こういうのあげたら喜ぶかな?』って考えるじゃん。それと原理は一緒」
一を聞いたら十を語るのではなく、理由づけされた“明確な一”が即座に返ってくる。口調は淡々としているのに、不思議と退屈させない。ここまでの数十分の会話の中で、彼の培ってきた能力と努力の片鱗が垣間見えたような気がした。
大好きだったサッカーへ
3年間ホストとして働いたのち、彼は再びサッカーに戻る決断をした。最後の年には草サッカーに顔を出すようになり、そこであらためてサッカーの楽しさを思い出したのだ。
ホストとしては、全国に約1200人ほどいる同グループの中で年間9位に入る実績を残した。もともと「お金が貯まったら辞めよう」と考えていたこともあり、潮時としてはちょうどよかった。
復帰先に選んだのは、当時東京都リーグ2部のFC PHOENIX。草サッカーでよく対戦していた馴染みあるチームだった。本格的に再開すると眠っていたスイッチが入り、シーズン途中の加入ながら10試合で20得点を記録。翌年も順当に結果を残し、東京都国体選抜にも選ばれた。
PHOENIXではエース級の活躍をしていたが、チームはなかなか1部昇格を果たせなかった。自分だけが点を取り続けていても大きな変化は見込めないーーしびれを切らし、2023年に国体で一緒だった仲間もいた東京蹴球団(以下、東蹴)へ加入した。

しかし、その年の夏に思わぬ展開が訪れる。リーグ第12節で渋谷と対戦し、東蹴が2-0で勝利。その2得点を挙げたのは政森だった。その活躍に目を奪われた代表の小泉翔から、熱烈なラブコールが届いた。
ただ、当初の彼に移籍の意思はなかった。結果として勝ったこともあり、クラブの存在も特別意識していなかった彼は、「自分は楽しくサッカーをしながら、東蹴で昇格を目指したい」と考えていたからだ。
だが、小泉の情熱はそれを上回った。毎日のように連絡を送り続け、ついに彼の心を動かしたのである。「あの人だよ、俺を困らせたのは。マジでしつこかったよ」振り返る口調は、まるで降参したかのようだった。
「本当にすごいんだよ、あの人。俺の草サッカーの仲間と翔さんがめっちゃつながってるの。だから、行く先々で周りから『渋谷からオファー来てるんでしょ?絶対やった方がいいじゃん』って推されまくった。『なんでそんなに知ってるの?』ってくらい、本当にいろんな人からね」
東蹴の仲間たちには引き留められたが、最後は快く送り出してくれた。そうやって自分の意思を尊重してくれたことも、今でも東蹴のことを大好きな理由のひとつだという。
背中を押され、2023年の夏に渋谷に加入した。「東蹴はお金を払ってサッカーをするから、いつでも戻れる。もし楽しくなかったり微妙だと感じたら、すぐ戻ればいい」と語るように、当初の彼に強い熱意はなかった。

そして迎えた初練習。ちょうど前節のリカバリー日で、メニューのひとつにサッカーテニスが組まれていた。そこで同じチームになったのが、轟木雄基(昨シーズン限りで退団)と、いまでも仲の良い山出旭だった。
「そのとき旭がろっ骨を怪我してて、試合の審判やってたのね。そしたらトド(轟木)と旭がすっげえ絡んできて、『あ、こいつらやべえな』って思った。でもそれがきっかけで話しかけてくれるようになって。今のチームは真面目な人が多いけど、あの頃はアホなやつとか変なやつが多かったね」
そんな空気感もあり、チームにはすんなり溶け込むことができた。だが、その矢先に思わぬアクシデントが彼を襲う。
「俺が、昇げる」
その週に行われたリーグ第15節・アローレ八王子戦。政森にとっては渋谷加入後、初めての公式戦だった。だがこの試合で左足のリスフラン関節を負傷し、2週間は歩くことすらできない状態に陥ってしまう。
これまで大怪我とは無縁だっただけに、初めての不自由な生活に戸惑った。手術も視野に入れていたが、それでは関東昇格を懸けた入れ替え戦には間に合わない。
悩んだ末に、反対の右足だけでプレーをする決断を下した。だが、走ることもままならず体重も増加し、思い描いたようなプレーには遠く及ばなかった。
そして渋谷はCOEDO KAWAGOE F.Cを相手に1-2で敗れ、関東昇格への道は断たれた。もちろん彼ひとりの責任ではないが、当の本人は今でも拭いきれない思いを抱えている。
「マジで壮絶だったね。翔さんの思いに応えて渋谷に入ったのに、すぐ怪我して全力を出せなかった。その申し訳なさがすごくある。あの時、俺が100%の力を出せていたら昇格できたかもしれないから」
試合後、チームは絶望的な空気に包まれ、泣き崩れる仲間の姿が至るところにあった。だが、彼だけは涙を流すことができなかった。加入してまだ数か月、チームへの思い入れが浅く、感情が追いつかなかったからだ。
「でもあの時、俺は客観的にみんなを見ることができた。もし自分も号泣して周りが見えてなかったら、悔しい気持ちでいっぱいいっぱいになってたと思う。でも俺は悔しさより、『自分が怪我してなかったらな』って気持ちだった。もちろん負けるのは嫌いだし悔しかったけど、試合後は俺だけキョロっとしてて、普通に弁当食ってたくらい」

だが、そんな光景を目にしたとき、彼の中に新しい感情が芽生えた。
「泣いている人たちが昇格のために残るのなら、自分も残ろう」
後の契約更新の場で、彼はクラブにこう伝えている。「増嶋監督と、試合に出ていたメンバーが残るのなら、自分も残る」と。
さらにもうひとつ、強く訴えた。「絶対に背番号9をつけたい」
「みんなのそういう姿を見たからこそ、自分も残りたい気持ちが湧いたし、同じ東京都1部の東蹴ともまた試合ができる。まあ、東蹴のみんなからは『どうせ今年も上がれないんじゃない?』なんて言われたけど、それでも自分がやりたいと思ったから残った。
めっちゃ鮮明に覚えてるもん。つっちー(土田直輝)がグラウンド脇のフェンスで翔さんと号泣してる姿とか、旭や他のみんなが死んだような目をしてるのとか。自分が紫のアウェイユニフォームで頭を抱えてる姿も、あの時考えてたことも全部覚えてる。笛が鳴った瞬間から、自分が外したヘディングや打たなかったシーン、試合が終わった瞬間まで全部。

今年だってCOEDOと対戦するとき、クラブがあの時の映像をよく出してくれるけど、もうあんなのなくても書けるくらい。
あの悔しさを知ってるから、去年は責任を持とうと思えたし、覚悟もめっちゃ決まってた。しかもスローガンが『俺が、昇げる』だったじゃん。もう、まさしくって感じだったね」
『NOW IS OUR TIMEーー渋谷を昇げるのは、俺だ』
2024シーズン、彼はその言葉を体現した。公式戦16得点を叩き出し、ギアは一気に全開。ついにはクラブのエースストライカーの存在にまで上り詰めた。
点取り屋へ覚醒。覚悟を決めた渋谷で
あの昇格戦こそ、政森にとってサッカー人生の大きな分岐点だった。だが、そのはるか前にも、キャリアを変えた転機があった。
いまのストライカーとしての姿からは想像しにくいが、彼の出発点はGKだ。高校卒業後、兵庫県1部のエベイユFCに加入したタイミングでFWへと転向した。
「『やれ』って言われたから。特に理由はないね。キーパーって、人が足りない時にFWとかやらされることが多いじゃん。それと同じ入りかな。あとは痛いし怖いし、点を取られたらなんか俺のせいにされるから嫌だった」
そしてもうひとつ、FW転向を決定づけたのが怪我だった。高校2年の冬の遠征で右手の小指を粉砕骨折し、いまも手術跡が残っている。
「パンチングもできないし、握力も落ちて。いまも曲げられないから、ちゃんと治しておけばよかったなとは思う。でもこれがなかったらFWを始めてなかっただろうから、まあいいかなって感じ」
高校時代までは同じGKの中でも足元の技術に優れ、ときにはBチームでCBやボランチを任されることもあった。そんな背景もあってか、エベイユで本格的にFWへと転向すると才能は一気に開花。リーグ戦19試合で29得点を挙げ、いきなり得点王に輝いたのである。FW1年目とは思えないほどの数字だ。
「『めっちゃ簡単やな』って思った。あんな大きいゴールに、いないとこに打つだけやんって」
飄々とそう語るが、何もせずに結果を残したわけではない。GKの経験しかなかった彼は、国内外のストライカーのプレー映像を漁り、研究を重ねていた。

やがて、彼の中にひとつ夢が芽生える。それが「Jリーガーになること」だった。
「キーパーだったやつがさ、『社会人になってフィールドに転向してJまでいきました』とか意味わかんないじゃん。だから本当にそうなったらめっちゃ面白いやんと思って、そこから上を目指し始めた」
その後、FC徳島を経てブリオベッカ浦安に加入。だが、ここで彼の熱い思いは次第に色褪せていった。
当時はまだ若く、チームの状況に対してネガティブになることも多かった。さらに、それまでのクラブでは「楽しさ」を軸にプレーしてきたが、浦安ではスポンサーの存在などもあり、次第に義務感が重くのしかかるようになった。
「俺さ、めっちゃサッカー好きなのよ。見てれば分かると思うけど。だから、サッカーをこれ以上嫌いになりたくなかった。仕事みたいになってくると、プレッシャーばっかりで楽しくなくなってきちゃって。それでスパンって辞めて、その月にホストを始めた」

そして今、あらためて振り返ると気づくことがある。先ほど触れた渋谷での転機にも通ずることだ。
「浦安では自分が上に上がるために点を取るし、チームを踏み台にしてた感じ。俺がJリーガーになることだけしか考えてなくて、チームが昇格するかどうかなんて正直どうでもよかった。加入したのだって、ちょうどJFLから関東1部に落ちた年で、レベルが高い関東リーグなら自分がステップアップできると思ったから。
でも渋谷での2年目は違ったね。自分のためというより、『渋谷のために』プレーした。年始に自分のInstagramで『ちゃんと昇格して翔さんとマスさん(増嶋監督)のことを泣かせます』っていうストーリーを上げたんだけど、本当にチームのためだった。何より『俺が』チームを上げる思いだった」
浦安と渋谷。どちらもクラブとしての環境は整っていたが、そこで抱いた決意はまるで別物だった。あの昇格戦の光景こそが決定的な分岐点であり、いまも脳裏に焼き付いて離れることはない。
“サッカーバカ”の誕生「俺がサッカーを呪っている」
母子家庭で育った幼少期。母は自分と二つ下の妹のために昼も夜も働き、3LDKの家に一人で過ごすのが日常だった。
昼食は自分で大きなタッパーにご飯をぎゅうぎゅうに詰め、すき焼きのタレで炒めた肉をのせるだけ。晩ご飯は母の作り置きがある日もあれば、自分で作る日もあった。机の上に置かれた千円札でやりくりしながら、サッカーの道具を買いそろえていた。
ただ、そのサッカーとの出会いは、決して前向きなものではなかった。
「おかんが坊主嫌いだったから。昔、お父さんが野球やってて坊主だったのね。おじいちゃんもやってたから野球一家なんだけど。だから俺が坊主になると『(お父さんのことを)思い出すから無理』って言われて、勝手にサッカーさせられた。
それで幼稚園ぐらいからいつの間にか始めてたね。その時デブだったからキーパーを始めたって感じ」
そんな経緯で渋々始めたサッカーは、やる気も興味も持てなかった。試合中でさえ退屈に感じ、砂で山を作って遊んでいたほどだ。
中学に入ってからも気持ちは変わらず、3年生になるまではサッカーが大嫌いだった。オスグットの怪我も重なり、1年生のころは練習に顔を出さない時期さえあった。

しかし、その後に大きな転機が訪れる。中学3年で出会ったコーチである、柏木健太郎(現・FC今治U-15監督)の存在だ。
政森が所属していた長洲FCはヤンマー尾崎グラウンドを拠点に活動しており、柏木氏は当時ヤンマーの実業団チーム(ヤンマー尾崎サッカー部)でプレーしていた。練習前には政森たちを指導し、ときには自らも練習に混ざっていた。
その真剣な姿勢と独特なサッカー観に惹かれた政森は、「柏木コーチがいるなら」と次第に練習に行くのが楽しみになっていった。
加えて、チームの仲間との結びつきも彼を変えていった。先輩や後輩と一緒に朝6時から公園で自主練に励むのが日課となり、電柱や遊具、段差など何でもゴール代わりとして延々とボールを蹴り続けた。夜中ですらサッカーをして警察に注意されたこともあるが、そのとき政森は「だから日本のサッカーは上手いやつが出ないんだよ」と言い返したこともあるという。
特に、一つ下の後輩・林誠道(現・松本山雅FC)とは、夏休みの間ほぼ毎日のように、シュート練習やサーキットトレーニングに打ち込んだ。
柏木コーチのおかげで、政森だけではなく林や周りの仲間たちもサッカーが大好きになった。サッカーがこんなにも楽しいものだと、初めて気づかせてくれた。

努力を重ねた末、推薦で神戸国際大学付属高校へ進学。すっかりサッカーにのめり込んだ彼は、高校では誰よりも早くグラウンドに行き、最後まで残ってボールを蹴り続けた。
通学は決して楽ではなかった。地元の尼崎から神戸までは片道1時間半。電車とバスを乗り継ぎ、最後は高台にある校舎まで約1キロの山道を歩く。明石海峡大橋を見下ろしながら通った3年間だった。
男子校のスポーツ科という環境だったこともあり、高校生活は華やかさとは無縁だった。だが、通学の行き帰りにはちょっとした楽しみがあった。
他校の女の子に見てもらうがために、毎朝髪の毛をセット。同じ電車で顔を合わせた女の子が学校の前や駅の改札で待っているのは日常茶飯事だった。「一番のモテ期だった」と本人も断言する。バレンタイン当日と重なった卒業式では、校門前で他校の女子生徒から山のようにチョコをもらった。
そんな青春の一幕もあったが、彼の本分はやはりサッカーだった。
「多分、国際のみんなは『あいつはサッカーバカだ』って言うと思う。そのくらい、ずっとサッカーばっかりしてた。月曜日は練習がオフだったから、学校に行く必要ないと思って行かなかったら怒られたこともあった。そのぐらいサッカーが好きだったね」

その熱量はいまも変わらない。練習が終われば必ず自主練に取り組む。以前、GKの積田景介を取材した際に政森の印象を尋ねたときも、その一点に尽きるといった。
この記事の企画名にちなんで、毎回選手に「誰にも止められない瞬間」を聞いている。政森はその問いに、一切の迷いなく答えた。
「サッカー。自分が一番たかぶってたり、集中してたり、ゾーン入ってて一番楽しいと思うことでしょ?それ以外にない。俺と関わってる人たちは『サッカー以外いいとこないじゃん』『サッカーなくなったら終わりじゃね?』って、みんな言うんじゃない?
だからサッカーできなくなったら終わりだね。俺は死ぬまでサッカーしてるでしょ。怪我とか事故とか病気で死ぬぐらいだったら、サッカーをずっとやり続けて死にたい。死ぬってそんな簡単になるもんじゃないけど。
でもサッカーができなくなったら、人間的に死んじゃうから。クソみたいな人生になると思う」
整然とした口調で、はっきりと言い切る。その主張を裏付けるのが、草サッカーの仲間から言われてきたある言葉だ。
「『ときくん、サッカーに呪われてるよ』って言われるんだよ。でも、俺がそう言われて返すのが『いや、俺が逆に呪ってんだよ』って。サッカーに取り憑かれてるんじゃなくて、逆に俺が取り憑いてんだよって」
受け身ではなく、常に主導権を握るのは自分。サッカーは彼の人生を縛るものではなく、自ら選び、執着し、人間的形成をしてきた存在だ。

『人生、ノリと勢いとタイミング』
ここまでの話を聞くと、彼にはいくつもの“ターニングポイント”があった。本人は「普通」と言うが、傍から見れば数奇な人生だーーそれは彼自身が一番よく分かっている。
「結構いろいろくぐり抜けてきたタイプだから、メンタル的な部分ではもう動じなくなった。ミヤ(宮坂拓海)みたいに、何か言われたらしょぼんとしちゃうタイプもいれば、逆に『なんやねん、こいつ』と思って空回りするやつもいる。
でも俺はそういうのはない。何か言われても『はいはい』って感じ。俺は俺でやることをやるだけ」
今でこそそんな姿勢を貫いているが、学生時代はまるで別人だった。本人いわく「激弱」。何か言われるとすぐに落ち込み、引きずってしまうネガティブな性格だったという。
「今でも考えたり、落ち込んだりすることはあるよ。でも、そういう時はちゃんと言葉にして自分を正す。俺、いつも言ってるじゃん。『どうせ点取れるっしょ、今日5点取るよ』って。そういうマインドに持っていくやり方を分かってるから、下を向くことはあんまない。シュートを外しても『うわマジかー、これ外すかあ』くらい」

そうした感情のコントロールはプレーだけではなく、日常の振る舞いにも表れている。普段は滅多に泣かず、仮に泣いたとしても意地でも他人には見せないという。
その理由を尋ねると、「キャラじゃないから」と一点張り。
「自分でもわかってるよ。だって俺、本当の性格は絶対こんなんじゃないのも知ってるもん。どう考えてもキャラでしょ。こんな自信満々でさ、『俺かっこいいやん』『俺だったら点取れるでしょ』みたいなの。みんなにいろいろ突っ込んだり、毒舌吐いたり、わがまま言ってるじゃん。俺しかそんなの言えなくね?普通はゴリゴリ言えないじゃん。
普通じゃないように仕立て上げてるのは周りだから。俺は自分のことを普通だと思ってる。その場その場の感情をむき出しで動いてるだけ。こうだと結果が出せるし、考え込むこともなくなる。これが一番楽なの」
かつて弱かった頃の自分も間違いなく、本当の自分だ。だが、もう振り返ることはない。結果を残し続ける今の自分を思えば、過去に戻る理由はどこにもない。

そんな彼が、自分を支える考え方として大事にしている言葉がある。
『人生、ノリと勢いとタイミング』
選択の一つひとつは衝動的に見えるかもしれないが、振り返ればすべてが今につながっている。
「最初からフィールドやってれば。あの状態でブリオベッカでサッカーをやめていなければ。東蹴のことも好きだったから、渋谷に入ってなければ。入った瞬間に怪我してなければ。あの時右足で打っていれば、とか。
後悔なんかいくらでもあるし、『あの時どうなってたんだろう』『この選択は間違っていたんじゃないかな』っていう瞬間はいっぱいある。でも、それもありきの自分。サッカーってそんなことの繰り返しだから」
だからこそ、余計なことは考えない。本能の赴くがままに動くのが一番心地よい。点を取ることも同じだ。自分の快楽のためにゴールを奪うーーそれが結果的にチームの役に立つ。
「俺、わがままだし自己中だもん。知ってるでしょ?でもそれをうまく活かせればチームのためになるわけじゃん。だからマインドセットが大事って話。
……でも、どこでこんなに変わっちゃったんだろうなあ。マジでわかんない。だって別に興味ないし、過去の自分に。毎日必死よ。周りから見たら必死感はないと思うけどね」

今、どうしても伝えたいこと「“あいつ”が原因だから」
俺様気質の政森には、特に心を許している仲間がいる。山出旭と鈴木友也だ。チーム内でも存在感を放つ2人とは、プライベートでも行動をともにすることが多く、チーム内ではいつしか「政森軍団」と呼ばれるようになった。
政森自身は、滅多に自分から誰かを食事などに誘うタイプではない。だからこそ、しつこいくらいに誘ってくる2人の存在が嬉しく、どこか可愛いとも感じている。多いときには、練習後ほぼ毎日のように食事に出かけていた。
練習中でも2人組やロンド、ボール回しでは自然と同じチームやペアになることが多く、あまりにも一緒にいすぎるため、増嶋監督からは「分かれろ」と言われるのも珍しくない。
そうした関係性を語るなかで、政森は山出の好きなところをこう表現した。「がめついところぐらいじゃない?あと“かまってちゃん”だし、メンヘラだし。だからわかりやすいよね」
「メンヘラ」とは情緒不安定な人を指すネットスラングのことだが、山出は気分の浮き沈みが激しく、すっかりチーム内では公認の“メンヘラキャラ”になっていた。

そんな山出に、大きな試練が訪れた。今季リーグ第9節・日立ビルシステム戦。1-1のまま迎えた試合終盤、激しい攻防の中で山出が負傷した。検査の結果は左膝前十字靭帯損傷・内側側副靱帯損傷。全治8か月の重傷で、今シーズンはここで幕を閉じることになった。
「あいつ痛がりじゃん。結局怪我した時も一瞬ピッチの外に出てテーピング巻いて、その後ヘディングも対人もしてたし。だから俺はベンチで他のやつと『痛がりかよ。またかまってちゃん出てるわ』って話してたんだよね。
でも次の日にCTを撮って、前十字が切れてるって聞いたときは『マジか』って驚いたね。あれだけプレーしてたし、俺だったらその場でアウトするレベルだから。『なんで切れてるのにプレーできるの?体の構造どうなってるの?マジゴリラやん』って半信半疑だった」
診断結果の連絡を最初に受けた政森。山出は大学4年のときにも半月板を痛めており、おおよその復帰期間は見えていた。それでも最初は戸惑いを隠せなかったと同時に「どうせあいつのことだから『サッカー辞めようかな』とか言い出すんだろうな」と予想もしていた。そして案の定、それは的中した。
ひどく落ち込む山出のために、「必ず戻ってこい」という願いを形にした。第10節・ヴェルフェ矢板戦では鈴木の発案のもと、『YOUR PLACE IS SHIBUYA ALWAYS』と描かれた応援Tシャツを作成。試合前、ロッカールームでそのTシャツを着たチームメイトたちを見た山出は、こらえきれずに涙を流した。

そこまでして山出の復帰を願うのは、単に仲が良いからではない。政森も鈴木も「旭のせいで」サッカーを続けているからだ。
「友也って、前所属のソニー仙台FCでサッカー辞めようとしてたんだよ。でも旭は大学の同期だったから『頼むから来てくれ』ってお願いして、無理やり渋谷に連れてきたって感じ。だから友也は旭が弱気になって『サッカー辞めようかな』って言うたびに、『絶対辞めんなよ。お前が誘ってきたんだから』って何度も言ってたのを聞いたことがある。
俺自身も、東蹴にいた頃に旭が翔さんに『ああいうFW取ってよ』って言ってたらしい。これは風の噂だし、もちろんいろんな流れやつながりがあって加入したんだけど、最初に仲良くしてくれたのはあいつだった。俺がチャラチャラした襟足とか、ニコちゃんマークのヘアバンしてたから、それを面白がって絡んできたと思うんだよね」

もし誰とも仲良くならず、ただ夏に移籍してきただけなら、残る理由なんてなかった。昇格を逃し、自身は怪我も抱えていたからだ。それでも、山出との関わりやあの昇格戦で見た涙を思い返すと、留まる気持ちが湧いてきた。
「もちろんあいつだけが理由じゃないけど、俺が渋谷にいる意味はあいつが一つの理由。クラブがあいつをクビにするとかは、そっち側の問題だから俺はどうしようもできない。けど、もしクビになってもサッカーは続けさせる。俺も一回サッカーを辞めて、翔さんとつながって渋谷に入ってるわけだから。サッカーやってれば絶対どこかでつながるじゃん。
俺も友也も渋谷に残って、旭の復帰を一番隣で待ちたい。それができなくても、『サッカーは辞めるなよ』って思ってるから」
そう言うと、「あいつバカだからサッカー以外できないじゃん」と照れくさそうに笑う。それも全部ひっくるめて、そこには間違いなく恋しさがある。絆と呼ぶにはあまりに簡単すぎるほどの、深い何かが彼らにはある気がする。
「旭が戻ってくること」が彼の一番の願いであり、約束だ。

「あいつは自分のことを『俺ゴリラだから治癒力人の2倍あるんだよね』って言ってるの。実際、いつも怪我しても半分くらいの期間で戻ってくるから、今回も早く復帰できるかもしれない。でも本人は『さすがにこれは無理だ』って言ってたから、あいつの頑張り次第だけどね。
俺が渋谷で楽しくいれるのは、あいつが原因なところはあるからね。もちろん他のみんなもだし、マスさんとかスタッフ陣のおかげで気持ちよくやらせてもらってる。でも一番近いのはあいつだから。だから戻ってこなかったらマジでしばくよ」
ピッチ内外で一緒にいた時間が長いからこそ、まだまだ隣で笑っていてほしい。政森の言葉は、自分の気持ちだけでなく、チーム全員の思いを代弁しているかのようだった。
最後に聞いた。親しみと愛を込めて呼ぶ“あいつ”が、本当に戻ってこなかったらどうするのか。政森は確信をもって答えた。
「絶対戻ってくるよ」

背番号9の覚悟「俺頼みでいい」
今季の政森はここまで3得点。第5節・tonan前橋戦で決めた豪快なループシュート以降、ゴールから遠ざかっている。昨季はまさに「政森の年」と呼ぶにふさわしい活躍を見せただけに、その落差は否応なく目を引く。
この現状をどう受け止めているのかーーそう尋ねると、彼は「いやー」と少し苦笑しながらこう答えた。
「最初はもちろん焦ってたけど、『やばい』っていうのはもう通り越した。もはや開き直ってる」
数字だけを見れば苦しい状況だが、意外なほど冷静な口調だった。どうやらリーグ中断明けの時点で、そうした心境に切り替わっていたという。
とはいえ、心の中にはもう一つの感情があるーーそれは、“疑問”だ。
「いつも通りやってるつもりだし、練習でも誰も俺が動けてないなんて思ってないはず。体のキレも悪くないし、なんなら年々コンディションは上がってる。少しゴツくなってるけど、それも武器に変えられてると思う。
別に自分では下手になったとは思ってないし、長く在籍してるメンバーと比べても上手くなってる自信はある。練習でもマスさんの言葉を誰よりも意識してる。我は出しているけど、何なんだろうね」
もちろん、今季から関東リーグという上の舞台に上がったことも影響しているだろう。試合中、相手からは「結局9番だから」というコーチングが飛んでくるのを耳にするたび、その警戒ぶりは嫌でも実感する。

とはいえ、チャンスをまったく作れていないわけではない。自分の感覚では「入った」と思う場面もあった。なぜならば無心で打てていたからだ。これまで決めたゴールは、すべて“無心”の瞬間に生まれてきた。だが、今年はその感覚があっても得点に結びついていない。
昨シーズンは良い緊張感やプレッシャー、そして強い覚悟を持ってプレーしていた。プロフィールやインタビューの言葉には常に「俺が」がついていた。「俺が得点王になる」「俺がチームを昇格させる」「俺が勝たせる」ーーそのぐらい言葉にして、気持ちを込めていた。
当然、今年も覚悟は決まっている。マインドセットの方法は身につけているはずだし、置かれている立場も理解している。自己分析だって誰よりもできている自信がある。1点さえ入れば、その試合で複数得点を挙げられるタイプだということも。

だが、肝心の“最初の1点”があまりにも遠い。お得意のシュートを打ち続ければ、そのうち決まると思っていたが、時間だけが過ぎていく。点を取れなければ、自分の存在価値を証明できない。その現実を理解しているからこそ、ここ数試合でのベンチスタートについても受け入れている。
「あれだけ使ってもらって、あれだけ信用されて。マスさん(増嶋監督)が考えてることもだいたい分かるんだよ。あの人は、俺が一回点を取れば流れに乗って勝手にノリノリになるのを知ってる。けど、その点を取るタイミングがいつ来るか分からないじゃん。
だから俺がどれだけ調子悪くても、とりあえず出場時間を延ばして、できるだけ点を取れるようにしてくれてるんだと思う。
でもこんなに結果が出てなかったら、ベンチだろうなってわかってた。なんならメンバー外かもなって。でも途中で出すってことは、やっぱり俺に点取らせて乗らせたいっていう思いもあるんだと思う。期待も込めてベンチに置いてるんだと思うし、意地でも下げないと思うのよ」
淡々と、今の自分の状況を分析する姿には、焦りの色は見えない。だが次の瞬間、ふっと表情が曇り、吐き出すように続けた。
「でももう残り4試合しかない。今3点だよ?そろそろ取らないとマジでやばいなって思う。3点なんてありえないでしょ。考えられない。こんなのフォワードやってきて初めて。『何が起きた?』って感じ」
そうこうしているうちに、タイムリミットは迫っている。今年は何が違うのだろうか。違いがあるならば、その正体は一体何なのか。糸口はどこにあるのか。

少し落ち着きを取り戻すと、また自分とチームを分析し始める。
「去年はあからさまに俺に対して『最後は任せた』みたいなボールが多かった。でも今年って誰でも触れるし、得点ランキングを見ても誰が決めてもおかしくないって思うじゃん。
だから俺って、ワンマンチームタイプなの。PHOENIXも東蹴のときもそうだった。渋谷の1年目は怪我してたから置いといて、2年目は(伊藤)雄教も(渡邉)千真くんもいたけど、結果的に1年間通して見たら、確実に俺の一年だったじゃん。
でも俺が去年みたいに調子が良かったら多分みんなから『ボール出せ』なんて言われないと思う。けど取ってないからこそそう言われるし、俺も言われて判断を変えちゃってる弱さはある。余裕ぶっこいてたかもしれないね」

自分自身に向き合う一方で、どうしても目を背けられないものがある。周囲からの期待だ。
「フロント、スタッフ、サポーターがめっちゃ待ってくれてるの分かるから。口に出さなくても嫌でも伝わってくる。
俺が出るときのスタンドの雰囲気、俺がプレーしてる時のベンチの視線、アップ前のちんたらしてる時間、試合後の空気。全部含めてマジでわかる。みんなが期待してるな、待ってるなって。
だから、それに応えないとなとも思うけど、そういう気持ちになっちゃったら逆に取れないだろうから、結局は楽しくやろうってね。楽しいときが一番点を取れるから」
畳みかけるように言葉を重ね、こちらが口を挟む隙を与えない。そして少し落ち着いて、再び口を開いた。
「……めちゃくちゃね、うざいぐらい伝わってる。『しつけーよ』って思うくらい。YouTubeの配信での翔さんと陸駆(ウィクラマラッチ陸駆 / インターンスタッフ)の実況とかもマジでやかましいくらい。でもそうやって思ってくれるのは、ずっと前からわかってる」
その彼の言葉を聞いてから「そろそろ取れそうではないか」と言いかけた筆者。だがその瞬間、彼がすかさず被せてきた。
「雰囲気が出てる?」
自分で言うのか、と驚いたが彼はあくまでスタンスは崩さない。
「みんなも言ってくれてるし、自分でもわかるよ。そろそろ取れるなって。あとは俺の場合、一回入ればケチャドバじゃない?俺なんて調子に乗れば乗るほどいいじゃん。
だから、どっちにしろ点取る。それだけ。取りたいとかじゃない、『取る』。得点王になる。あと4試合でしょ?1試合に2点取ればいけるでしょう」

残されたのはあと4試合。その初戦となる明日は、EDO ALL UNITED戦だ。過去の因縁はもはや言うまでもない。しかも、もし敗れればその時点で相手の優勝が決まる。2位だとしても昇格の可能性は残されているが、これはプライドを懸けた大一番だ。
「EDOには勝ちたいね。目の前で勝たれて優勝なんか喜ばれてみ?俺、腹立ちすぎてブチ切れるよ。負けず嫌いだから。ゲームも何もかも負けたくないから。ジャンケンでさえちょっと不機嫌になるし、笑えない。だから絶対にあいつらが目の前で優勝するのだけはナシだな」
あふれんばかりの闘志を向きだしにしたその口から、次に飛び出したのは覚悟の宣言だった。
「スタメンでも途中出場でも、もし俺が1点も取れなかったら、残りの試合全部メンバー外でもいいと思ってる。それくらい、もう覚悟は決まってる。
なので点取ります。点取るのが一番楽しいので。9番は点取る以外何もしなくていいんだから。アシストなんていらない。だから俺は、もっと“俺頼み”でいいと思ってるよ」

高まる重圧を力に変え、責任と覚悟を背負う姿は、まさにエースの矜持だ。
背番号9。それは、「俺が」決める者にだけ許される番号である。
取材・文 :西元 舞
写真 :福冨 倖希
企画・構成:斎藤 兼、畑間 直英
UNSTOPPABLES バックナンバー
#1 渋谷を背負う責任と喜び。「土田のおかげでJリーグに上がれた」と言われるためにーー土田直輝
#2 頂点を目指す、不屈の覚悟。全ては世界一の男になるための手段ーー水野智大
#3 冷静さの奥に潜む、確かな自信。「自分がやってきたことを発揮するだけ、『去年と変わった』と思わせるために」ーー木村壮宏
#4 這い上がる本能と泥臭さ。サムライブルーに狙いを定める渋谷の捕食者ーー伊藤雄教
#5 問いかける人生、答え続ける生き様。「波乱万丈な方へ向かっていく。それがむしろ面白い」ーー坪川潤之
#6 サッカーが導く人生と結ぶ絆。ボールがくれた縁を、これからも。ーー岩沼俊介
#7 楽しむことを強さに変えて。夢も、欲も、まっすぐに。ーー小沼樹輝
#8 誰かのために、笑顔のために。誇りと優しさが生む頂点とはーー渡邉尚樹
#9 九州で生まれた男の背骨。「やっぱり男は背中で語る」ーー本田憲弥
#10 選手として、父として。見られる過去より、魅せたい現在地ーー渡邉千真
#11 余裕を求めて、動き続ける。模索の先にある理想へーー宮坂拓海
#12 この愛に、嘘はない。激情と背中で示す覚悟の真意とはーー鈴木友也
#13 憧れた側から憧れられる側へ。ひたむきな努力が導く、まっすぐな未来ーー大越寛人
#14 楽しいだけじゃダメなのか?渋谷イチの苦労人が語る「俺は苦しみに慣れちゃってる可能性がある」ーー高島康四郎
#15 かつて自分も”そっち側”だったからこそ、わかる。「もう誰のことも置いていきたくない」ーー志村滉
#16 絶対の自信を纏う、超こだわり屋のラッキーボーイ「必ず俺のところに転がってくる。そう思ってるし、信じてる」ーー青木友佑
#17 SHIBUYA CITY FCに人生を懸けた男「俺をこんなにも好きにさせた、このクラブが悪い!」ーー植松亮
#18 絶対に壊されたくない、やっと思い出せた楽しさ「副キャプテンを降ろさせられるんだったら、それでもいい」ーー楠美圭史
#19 器用貧乏?いや、今は違う「俺の中に神様はもういない」ーー青木竣
#20 考えたからこそ、”あえて”何も考えない「今日もやっちゃおーよ」ーー小関陽星
#21 どんな場所でも、俺はここで貫く「納得いかないことに対しても、納得いくまでやり続ける」ーー佐藤蒼太
#22 渋谷で語る、再びの覚悟とサッカー人生の答え「僕は恵まれている。もう、それしか言えない」ーー吉永 昇偉
#23 フェイクじゃ終われない「もっと突き詰めていれば…」吹っ切れた先に見えた景色ーー河波 櫻士
#24 人として在るべきために、追い求める理想像「本当の意味で、“大きい人”に」ーー積田 景介
SHIBUYA CITY FC
渋谷からJリーグを目指すサッカークラブ。「PLAYNEW & SCRAMBLE」を理念に掲げ、渋谷の多様性を活かした新しく遊び心のあるピッチ内外の活動で、これまでにないクリエイティブなサッカークラブ創りを標榜している。
渋谷駅周辺6会場をジャックした都市型サッカーフェス「FOOTBALL JAM」や官民共同の地域貢献オープンイノベーションプロジェクト「渋谷をつなげる30人」の主宰、千駄ヶ谷コミュニティセンターの指定管理事業など、渋谷区での地域事業活動も多く実施している。
お問い合わせ
担当:畑間
問い合わせはこちら