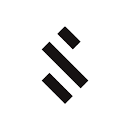人として在るべきために、追い求める理想像「本当の意味で、“大きい人”に」ーー積田 景介 【UNSTOPPABLES】 #24
2025年8月29日
|
Article
“真面目に、謙虚に、ひたむきに”
キャリアの浮き沈みや年齢を重ねる過程で、自らを何度も支えてきたのはこの姿勢だった。試合に出られない悔しさも、思うように結果を残せない日々もある。だが、折れそうになるたびに自分を突き動かし、前へ進ませてくれたのはこの指針だった。
【UNSTOPPABLES~止められない奴ら~】
昨シーズン、関東2部への昇格を決めたSHIBUYA CITY FC。その栄光の背後には、ただの勝利以上のものが隠されていた。選手たちの揺るぎない自信と勢いは、彼らの人生に深く刻まれた歩みから来ている。勝利への執念、それを支える信条。止まることを知らない、彼らの真の姿が、今明らかになる。
第24回目は、渋谷の守護神・積田景介。8年間過ごしたFC琉球での経験、ピッチ内外で貫いてきた姿勢、そして彼が追い求める理想像とはーー。
積田景介(つみた・けいすけ) / GK
1993年6月23日生まれ。千葉県市原市出身。185cm、81kg。地元クラブの五井FCでサッカーを始め、五井中学校を経て市立船橋高校へ進学。2年次には全国高校総体、3年次には全国高校サッカー選手権で日本一に輝いた。駒澤大学を卒業後、2016年にFC琉球へ加入し、8年間にわたり在籍。2024シーズンよりSHIBUYA CITY FCに加入。反応の鋭いシュートストップでチームを救い、クロスやハイボールに対しても落ち着いて処理し、安定感あるプレーでゴールを守る。
募らせた虚無感と思い出せた感情
積田がゴールキーパーを始めたのは、小学4年生のとき。もともとはFWやCBしてプレーしていたが、ある日GKのチームメイトが練習を休み、代役としてゴールを守ることになったのがきっかけだった。
想像以上に「止める」ことが面白く、そこから気づけば20年以上、ゴールキーパー一筋でプレーを続けてきた。
彼のInstagramには小学生時代の写真が投稿されている。小学6年の時点で身長はすでに173cmほどあり、周囲より成長が著しく早かった。両親は平均的な背丈だったが、幼稚園のころから「なぜ自分はこんなに大きく、周りはこんなに小さいのだろう」と不思議に感じていたという。
背の順はいつも一番後ろ。友達同士が背比べをして盛り上がっていても、自分だけは比べるまでもなく抜きん出ていた。そのせいで、友達と同じ目線でいたいと無意識に猫背になってしまうことも多々あった。
そんなエピソードを聞くと、彼がキーパーになったのはある意味必然だったかのように思える。そしてその選択が間違っていなかったことは、その後のキャリアが証明している。
高校は全国屈指の強豪・市立船橋へ進学。2年次には全国高校総体(インターハイ)、3年次には選手権で全国制覇を果たした。さらに、U-18日本代表候補や高校選抜にも選出され、まさにエリート街道を歩んでいた。怪我でベンチを温める時期もあったが、それでも名門の守護神として、チームを日本一へと導いた立役者だった。
大学では2年次に第五中足骨を疲労骨折し、再び怪我に苦しんだが、3年次には関東大学選抜に選出されるなど、確かな実績を残した。

順風満帆に見えたキャリア。しかし、2016年に大卒で加入したFC琉球ではかつてないほどの苦しみが待ち受けていた。
プロ3年目から退団までの6年間、選手会長を務めるほど人望を集めた一方で、ピッチに立つ機会はごくわずか。在籍8年間でリーグ戦出場はわずか8試合にとどまった。
なかでも、その苦しい現実を痛感したのが2021年シーズンだった。チームは開幕戦から5連勝と好スタートを切っていたが、その歓喜の輪に加わることができない現実は、どうしようもなく悔しかった。
「タッチラインからあっち側に行けない。タッチラインを超えるには本当に時間と能力がないといけない」そう語るように、無力さに押しつぶされ、強い虚無感に苛まれる日々が続いた。
そして翌年、チームは最終節を残してJ3降格が決まった。当時メンバー外だった積田は、テレビの前でその瞬間を見届けるしかなかった。画面越しに映る光景を前に、言葉にできないほどの苦しさが胸を締めつけた。
「自分は在籍年数も長いし、J2昇格に貢献した選手やスタッフの苦労を知ってるからこそ、その人たちの顔が次々と浮かんだ。あの瞬間の虚無感は、今でも忘れられない。やっぱり昇格することって簡単じゃないから。
俺が入団する前から、給料や環境面で厳しい環境でやってきた人もいる。落ちてしまったこともそうだけど、そういう姿を見てきた自分がピッチに立てず何もできなかったことが、すごく悔しかった」
さらに、残留を懸けたこの試合の相手はジェフユナイテッド千葉。幼い頃から応援していた地元クラブとの一戦だっただけに、胸に去来する思いは一層複雑だった。

加入から5年間はなかなか公式戦のピッチに立てない日々が続いたが、2022年の天皇杯第2回戦・大宮アルディージャ(現・RB大宮アルディージャ)戦でついにその瞬間が訪れた。リーグ最終節に出場した2018年以来、実に4年ぶりのことだった。
公式戦特有の緊張感は、いくら練習を重ねても味わえない。前日から胸の高鳴りは収まらず、夜もまともに眠れないほどだった。しかもその試合はナイターゲーム。キックオフまで時間がある分心は落ち着かず、緊張はさらに増していった。
そして、いざピッチに立った瞬間。緊張と同時に、ある大切なことに気づかされた。
「ユニホームを着て、試合用のスパイクとグローブを身に着ける。そしてお客さんの前でプレーすることが、『これだけ幸せなことなんだ』ってことを、改めて実感した。
天皇杯だったから観客はそんなに多く入ってなかったんだけど、それでも公式戦ならではの雰囲気やこのソワソワ感は、ベンチやスタンド、テレビでは味わえないね。『俺はこれのためにやってんだな』っていうのを感じた瞬間だった」
長らく公式戦の舞台から遠ざかっていただけに、その感覚は鮮烈だった。その実感こそが、後の彼に大きな影響を与えていく。

最後のあの日
2023年、ついに琉球退団が決まった。「遅かれ早かれ、契約満了は来るもの」と語ったように、クラブを離れる覚悟はできていた。だが、8年という長い年月を過ごしたクラブへの愛情は計り知れず、強い喪失感が胸に押し寄せた。
実際に契約満了を告げられたときは、素直に受け入れるしかなかった。それでも、これまで関わってくれた選手やスタッフ、行きつけの定食屋の店主たちの顔を思い浮かべると、どうしても離れがたい気持ちが込み上げてきた。
迎えた第37節・FC岐阜戦。これが積田にとって琉球でのラストマッチとなった。実は契約満了が決まった翌週の練習で、彼は指導陣にあることを頼み込んでいた。
「『満了になったからといって、最後だからメンバーに入れようとか、そういう情は一切いらないです』と。たとえメンバーから外れても受け入れるし、最後までプロフェッショナルとして、みんなと同じように評価される立場でいたかったから。
自分に嘘はつきたくなかったし、今までやってきたことは最後までやる。それはサッカー選手としてというより、人として今後生きていく上で大事なものだと思ったから」

譲れない姿勢を貫いた結果、積田は最後の試合でメンバー入りを果たした。
サブメンバーではあったものの、ピッチに立てる可能性があるかもしれないという期待に胸が高鳴った。試合前のウォーミングアップでは、「本当に自分は出れるのか」という不安と緊張、そして「このスタジアムでプレーするのも最後だ」という名残惜しさが交差する。たった一日で、こんなにも特別な感情が生まれるのかーー自分でも驚くほどだった。
「他のみんなからは『お前、後半45分から出るらしいよ』って言われてて、特に何も聞いてなかったけど、そうなのかな?って思ってた。それで前半が終わって交代するのかなと思ったら、交代しなくて『なんだよ』って思ったよ。そしたら他の人が『残り20、30分くらいから出るらしいよ』って言うから、『なんであんたが知ってんだよ』って(笑)
結局、残り5分になって、急に監督とコーチから『行くぞ』って言われて、『ここで!?』ってびっくりしたよ。でも、俺にとっては大事な5分だった」
ゴールキックで始まった、わずか5分間だけの出場だった。相手チームのサポーターのブーイングでさえ、どこか嬉しく感じられた。
短い時間でも、積田にとっては特別な試合だった。最後だからといって物足りなさを感じるどころか、あの天皇杯のときと同じように、試合に出られる喜びを人一倍嚙み締めた。

試合終了後、スタンド挨拶の際には、チームメイトたちが自分のもとに駆け寄ってくれた。特別何かを言うわけでもなく、肩を叩いてくれた。スタンドに目をやれば、サポーターが声援を送りながら自分のグッズを掲げている。そして、いつも通っていた定食屋の店主たちまでもが、応援に駆けつけてくれていた。
ここでプレーするのはもう終わりなのかーーその事実を身に染みて受け入れた瞬間、涙が止まらなかった。
「満了を受けた悔しさというより、この地を離れなきゃいけないことがすごく辛くて、寂しかった。定食屋の人たちとの関係だって、決して終わるものではないけど、日常だったものから離れなきゃいけない辛さがあったから、サッカー人生で一番泣いたんじゃないかってぐらい、めっちゃ泣いた。
当時は琉球に行くことを正解か不正解だとか考えなかったけど、こうやって時間が経って振り返ってみると、行ってよかったなって思う。試合には全然出られなかったけど、人として大きく成長できたからこそ、正解だなと思った。それだけいろんなことが楽しかったし、たくさん学ばせてもらった。すごく思い入れのあるチームだし、思い入れのある場所だったから」
そう当時のエピソードを語るこの取材の最中ですら、積田の目にはうっすらと涙が光っていた。
クラブの公式HPで公開された退団のリリース文も、自宅で涙を流しながら、一言一言に思いを込めて綴ったという。
思い返せば、あれは加入して最初の練習だっただろうか。グラウンドに着いた瞬間、サッカーコートより外のグランドゴルフ用の芝の方が整っているように見えた。用意されているはずの練習着はまさかの枚数が足りず、仕方なく持参したトレーニングウェアで初日を乗り越えた。
後に選手が移籍してきたが、当初はGKを含めてもわずか18人ほどしかメンバーがおらず、紅白戦すら成立しなかった。
本当にこのままやっていけるのかーーそんな不安を抱いたあの頃が、今では微笑ましく思える。

「『こんなこともありました!』っていう文句も書きたかったよ?」と冗談交じりに語る積田。だが、その後すぐに真剣な表情に戻り、こう続けた。
「でも、やっぱり終わり方ってすごく大事だと思ったから、それは違うなと思った。あの文章を書くのに、すごく考えたかな。20代の8割をあのチームで過ごしたわけだから、そんなやすやすとしたコメントは残せられないなって。大学卒業してから30歳までずっといたわけだし、ただの8年間じゃなかったから。
最後、定食屋のおばちゃんとか、いつも行ってた温泉の従業員さんに挨拶周りに行ったんだよ。そしたらみんなすごく泣いてくれて。付き合いの長かったクラブのフロントスタッフの人たちもいい形で送り出してくれたしさ。退団してからまだ一回も会いに行ってないから、また会いたいな」
まだまだエピソードは尽きないようだったが、それ以上は掘り下げないでおいた。「ダメだね……思い出すと泣いちゃうから」と、また今にも彼の目は潤んでいたからだ。その表情を見ただけで、語らずとも十分に伝わってくるものがあった。
仲間に捧ぐリスペクト
昨シーズン、渋谷に加入した積田は、現在チーム内で上から3番目の年長組にあたる。温厚で懐の深い性格ながら、チームメイトからは「いじられキャラ」として親しまれている。一方でピッチに立ったときの姿は頼もしさそのもので、仕事の場でも変わらぬ誠実さを見せる。どこにいても信頼を集めるーーそんな存在感がある。
琉球を退団後、社会人チームに進むという道もあった。だが、積田はその選択を取らなかった。サッカーで結果を残せなかったときに、心のどこかで仕事のせいにしてしまう可能性もあるかもしれない。そんな思いは抱えたくなかった。
そのため、一度はJクラブの練習参加に足を運んだ。だが、30歳を迎えた社会人としての自分に、どのような能力があるのかを確かめたくなった。
サッカーをいつ辞めるのか、未来の姿もまだ想像もつかなかったが、仕事をしながらサッカーをする生活は、自分に新たな成長をもたらしてくれるはずだ。そう考えた積田にとって、当時東京都リーグに所属していた渋谷への移籍は、大きなステップだった。
また、選んだ仕事はスポーツとは無縁の営業職だった。そこにも彼なりの理由があった。
「最初はスポーツ関連の仕事を紹介してもらったけど、なんかしっくりこなくて。どうせやるなら、サッカーとは全く関係ないところで働いてみたいと思った。そういったところに飛び込まなきゃ、痛い目にも合わないし、学べないから」
とにかくがむしゃらに、社会人としての基礎の基礎から学んでいった。右も左も分からない状態から少しずつ積み重ね、気づけば入社して約1年半。いまでは部署内での在籍歴は最長となった。自分より若い社員たちに囲まれながら、活気ある職場で充実感に満ちている。

そして今年は、可愛い部下たちも入ってきた。今季渋谷に加入した河波櫻士、小関陽星、宮坂拓海、大越寛人だ。さらに別部署には青木竣もいる。
なかでも、河波と小関の2人とは仲睦まじい関係を築いている。本人たちも認めるほどの楽観的な思考の持ち主で、上司の立場である積田に対しても遠慮なく甘えてくる。
「月に1、2回ぐらい、急に『つみくん、そろそろコーヒー飲みたいです』って言われるんだよ。それでオフィスの下にあるドトールで、部署内のみんなの分のコーヒーを俺が買うっていう(笑)毎回絶望しながら会計してるけど、それでみんなが頑張ってくれるならいいかなって。まあ、こういう立ち振る舞いも大事だからね」と、後輩2人に翻弄される日常を楽しげに語ってくれた。
同じくGKの高島康四郎によれば、木村壮宏を含めたキーパー会でも、積田がいつも食事代を持つという。その話を伝えると、「おごり要員じゃねえんだよ、俺は」と笑い飛ばしながらも、「それは全然払うよ」と、年長者として気前よく答えた。
「だからね、いずれ彼らが先輩になったときに、『ちゃんと払えよ』っていうメッセージを込めてるのよ。君たちも後々この立場になるから、その時にちゃんと(後輩に)払えるような人になりなさいって。俺には別に返さなくていいから、次世代につないであげなさいってね」と、冗談交じりにそう語った。

多方面から親しまれながらも、仕事もサッカーも一切妥協しない。その姿勢は、後輩たちにとってひとつの指標になっている。
一方で普段はおちゃらけたキャラクターの河波も、仕事になると見間違えるほどモードが切り替わるそうで、積田自身も後輩たちから学ぶことが多いと明かす。
「『そういうアポの取り方もあるんだな。なるほどな』って思うことは、櫻士もそうだし、陽星も、こっしー(大越)も、ミヤ(宮坂)からも学んでる。彼らは俺のことを上司だって言うかもしれないけど、俺はそんなつもりは全くない。
他の社員の人に対しても、別に自分が上に立ってるとは思わないし、同じライン……むしろ(自分が)下なくらい、みんな一生懸命やってるからすごいなって思うよ。みんな俺より年下なのに、立派にやってるから、自分もちゃんとしなきゃなって思うよね」
その尊敬のまなざしを向ける対象は、何も職場の仲間に限った話ではない。他の渋谷のチームメイトに対しても同じだ。見渡せば、個性豊かな面々が勢ぞろいしている。
「みんなサッカーも仕事も、100%……いや、それ以上でやってる。Jリーグのチームを見ても、練習がきつい中でもここまでサッカーが好きで、全力で取り組むチームはなかなかないよ。だから俺は選手全員をすごくリスペクトしてるし、『自分もやらなきゃ』っていう気持ちにさせてくれるから、みんなには本当に感謝してる」

そのなかでもDF鈴木友也の名前を挙げた。普段は落ち着いた雰囲気を漂わせながらも、ピッチに立てば一転。誰よりも闘志を前面に出し、堂々たるコーチングでチームをけん引する存在だ。
「ミスしてもトライするし、強くいくし、仲間を鼓舞できる。まだ27歳なのに、肝が座っているというか。あれだけガッツがあって、その後に崩れることもない。そういったところも学ばせてもらっているかな。
年下だけど、尊敬する対象に年齢は関係ないと思ってて。みんなから学ばせてもらってるし、このチームの選手の意欲は本当に素晴らしすぎる。リスペクトしかない」と、大切な仲間たちへの敬意を惜しみなく口にした。

「止まっている」瞬間
この取材では毎回、企画名にちなんで「止められない瞬間」を尋ねている。多くの選手が挙げるのは試合中や筋トレといった身体を動かす時間や、あるいはサウナやカフェ、ペットや友人と遊ぶことに夢中になる時間だ。
だが、積田の場合は少し違った。「止められない瞬間」を聞いたはずが、返ってきたのは「読書してるときは止まってるかも」という斜め上の回答だった。
その真意を尋ねてみると、こう語ってくれた。
「俺は逆に、“立ち止まる”ことをすごく大事にしてて。サッカーも仕事も、前へ進んでいくものじゃない。そうなると、一回立ち止まりたい時が欲しいんだよ。サッカーをしているときも、仕事をしているときもずっと駆け抜けている感じがあるからね。

だから評価とかそんなのは抜きにして、本を読んだりする時間が、俺の中では止まってる瞬間かな。サッカーをしているときなんて、立ち止まってる暇なんてないから。読書は立ち止まる隙を与えてくれる」
実際、積田は練習後には誰よりも早くハチドリ(※渋谷区スポーツセンター内にあるカフェラウンジ。選手の食事提供を行う)で昼食を取る。仕事の始業時間に間に合わせるため、ゆっくりと腰を落ち着ける余裕はほとんどない。
そんな生活を送っているからこそ、読書の時間は心身を休める大切なひとときであり、彼にとっては“止まっている”時間そのものだ。
「全然かっこつけてるわけじゃないけど、小説とか自己啓発本を読んでる。その場でまるまる一冊読み切れないけど、1時間でもいいから少しずつ読むようにしているかな」

一方で、読書は知識や教養を吸収できる時間でもある。裏を返せば、それはまさに「止められない瞬間」とも捉えることができるだろう。それを聞いた積田はハッとした表情になり、納得しながらこう語った。
「逆にいえば、サッカーも仕事もデジタルも一回放棄して、読書している時間が止められない時間なのかもしれないね。俺にとっては止まっている瞬間だけど、どっちとも言い換えられる。
でもどこかで立ち止まらないと、心も身体も疲弊しちゃうから。どこかで一回スパッと断ち切りたい。その方法が本を読むことなのかもしれないし、サウナに入ることもそうだよね。だから、その瞬間は立ち止まってる瞬間。でももしかしたら、それこそが止められない瞬間なのかもしれない」
せわしない日々を送っているからこそ、「立ち止まること」を何よりも大切にする。その瞬間こそが、彼にとっての止められない瞬間なのだ。
唯一誇れるもの
現在、渋谷に在籍するキーパーは3人。積田の他には、冷静沈着な木村と、ムードメーカーの高島がいる。互いに切磋琢磨し合う仲間であると同時に、ひとつの枠を争うライバルでもある。では、そのなかで積田はどんな自分の色を見せていきたいのかーー。
そう尋ねると、少し首をかしげながらこう答えた。
「俺は特に、めっちゃ目立ちたいとかそういうのはあんまりなくて。人として、ちゃんとしていきたいかな」
“人として”。その言葉を強調した真意を、さらに掘り下げた。
「例えば、今まで自分に課してきたウォーミングアップがあるとして、もしメンバーから外されたりすると、中にはそれをやらなくなってしまう選手もいるんだよね。『もう今週出ないから』と言って、今までやってきたものを放棄してしまう。
俺はそれを否定しないし、そういう感情があって当然だと思う。でも俺は、今までやってきた自分や周りの人たちの思いを裏切ることになるから、それはしたくない。それは試合に出る・出ない、試合に勝つ・負けることは二の次というか。そういったところをすごく大事にしてる。これは人として」

一方で、キーパーというポジションは、一つのミスがフォーカスされることは珍しくない。実際、今季第2節・東京国際大学FC戦では、渋谷は2点を先行しながらまさかの逆転負けを喫し、チームは重苦しい空気が漂っていた。
「あの時は俺のミスで失点してしまって、本当に辛かった。その後もなかなか気持ちを切り替えられなかったよ」と、苦い表情を浮かべながら振り返った。
だが、そこで何かが変わるかといったらそうではない。「でも」と言葉を続けた。
「どうしてもミスは出てしまうものだから、その後の立ち振る舞いは、すごく大事だと思う。そこが崩れてしまうと、信頼関係も一気に崩れてしまうから。
たとえ気分が落ちても、なるべく感情の波は作らないようにしてる。メンバーに入れないとか、試合に出れないことってよくあるんだけど、それでも自分のやるべきことはしっかりやろうって決めてるから、感情の変化で自分の行動が変わらないようにしてるかな。それは唯一誇れることだし、時が経っても変わらないようにしてる。
あとキーパーはコミュニケーションスキルがすごく求められるから、『俺はこうしたかったんだけど、どうだったかな?』っていう質問みたいな感じで、言葉のチョイスにはすごく気を遣うかな。でもそれも人によってやり方が違うし、別に他人のコミュニケーションとり方を否定するわけではない。あくまで1つのスタイルとして、俺はやってるだけ。
もちろんプレーの良し悪しはあるけど、それでも自分の行動であったり、人に対する発言は、気は遣ってきたし、これからも絶対に崩さないでいきたい」

“人として”見せたい姿
こうした一貫した姿勢の裏には、かつての恩師から授けられた言葉がある。その言葉が書かれた紙を、携帯の壁紙に設定していると見せてくれた。
“真面目に、謙虚に、ひたむきに”
高校時代、恩師に書いてもらった言葉。くじけそうになったときにはその文字を見返し、自らを奮い立たせてきた。単なる座右の銘ではなく、生き方そのものを支える軸となっている。
「学生の時からずっとそういうふうに教えられたからこそかもしれないね。『やっぱり人だよ。人としてちゃんとしないと生きていけないよ』って言われたからこそ、今がある。
もしも違う方向に進んでしまったり、グれてしまうことがあったら、今まで自分に指導してくれたり、支えてくれた人たちに対して裏切ることになるから、それだけはしたくない」

どんなときも守り続けてきた姿勢。それは口だけでなく、日々の行動にも表れている。
以前、主務の角野天笙からこんな話を聞いた。練習初日、大学生である角野の周りには年上の選手ばかり。今のように気軽に話しかけられる状況ではなく、チームにどう溶け込めばいいのか分からず緊張していたという。
そんなとき、最初に声をかけてくれたのが積田だった。それが角野にとってまさに救いの手であり、いまでも感謝している出来事だという。
そのエピソードを伝えると、積田は「そっか、そっか」と照れ笑いを浮かべ、こう語った。
「やっぱり選手とかマネージャーとか関係なく、チームの一員だっていうことを初日でも分かってほしかったからかもしれないね。みんなで戦ってるし、選手だけじゃ成り立たないから。
てんてん(角野)とか、大暉(北川大暉 / チームダイレクター)、真菜ちゃん(永堀真菜 / 昨年度マネージャー)だって裏方かもしれないけど、そういった人たちのハードワークがなければ、やっぱり成り立たないから。だからああいう行動になったのかもしれない」

そうした人柄の良さは、この取材の場面にも表れていた。多くの選手が練習終わりの合間を縫って対応する中、彼は練習も仕事も休みの月曜日に、わざわざ時間を割いてくれたのだ。
これまで掲載されたチームメイトのインタビューを見て、「自分とまったく違った人生を歩んでいる」と感心する一方で、彼には彼なりの思いがあった。
「だからこそ、自分もちゃんと答えなきゃなって思ったから休みの日にした。練習の後には仕事があるし、どうしてもバタバタしちゃうからね。自分のこともそうだし、周りの人のこともちゃんと話したかったから、適当に答えるのはナンセンスだと思った。周りの選手、職場の人、今まで関わってきた人たちがいるからこそ、今の自分がいるから。
それだけ思いがあるし、いろんな人に感謝を伝えられるチャンスだと思ったからね。本当は言葉で直接伝えたいんだけど、自分のことを知ってもらえて、かつ感謝も伝えられる。これ(取材)はそのためのひとつの手段だと思った。だから本当は全員の名前を挙げたいぐらい、もっと喋りたいんだけどね」
その感謝を伝えたいと、昨年の関東昇格を懸けた大一番を振り返る。職場の社員が10名以上も会場に駆けつけたというのだ。試合後に撮影した集合写真を見返しながら、「こんなに来てくれたんだよ」と、今でも驚きを隠せない様子で語る。写真には、積田を囲むように社員たちが笑顔で並び、彼のために作られた個人の横断幕を掲げていた。

「こんなに嬉しいことないよ。今年もめちゃめちゃ暑いのに来てくれてさ。仕事だって、まったくサッカーしか知らない俺を受け入れて、アドバイスまでしてくれる。こうしてイベントごととして試合に来てくれるし、ユニホームも買ってくれて、横断幕まで作ってくれて。自分のために時間とお金を使ってくれて、本当に職場の人に感謝しかない。当たり前じゃないよ、これは。
これで頑張れないわけないよね。サッカーもそうだけど、仕事もちゃんとやらなきゃダメだよねっていう気持ちにさせてくれるから、本当に嬉しいよね」
琉球時代にも身に染みたありがたみ。周りからの声援は決して当たり前ではなく、むしろ贅沢すぎるくらいだ。社会人経験のなかった自分に一から指導し、さらには休日に時間を割いて応援にも駆けつけてくれるーーその労力を思えば、感謝してもしきれない。
「だからそこの運の良さはあるかも。行く先々で、人に恵まれていること。小中高大、琉球でもそうだし、渋谷でもそうだけど、もう行く先で人に恵まれすぎてるよね。この運の強さだけはあると思うし、確実に周りがいなければ今の自分はないと思ってる。今こうやって楽しくやれてるのも、周りのおかげ。これは俺の力じゃない」

胸を張って「人に恵まれてきた」と言えるのは、積田自身の人望あってこそではないか。そう水を向けても、本人は「いや、そんなことない。これは周りがいいから。自分とかじゃない」とすぐさま首を振った。
謙虚すぎるほどに驕らず、決して自分を棚に上げない。その根底にあるのは、彼が思い描く理想のキーパー像である。
「感情が良くても悪くても、『どんとこい』っていうようなドシッと構えている、漢気のあるキーパーになること。
でも、そのキーパーになるにはまだまだ足りないと思ってる。たまにビビリだし、恐れもあるから。でも足りないからこそ、頑張れるのかもしれない」

さらに積田には、キーパーとしてだけではなく、‟人として”追い求める人物像がある。それは技術や勝敗の前に問われる「あり方」。そこには彼の信念が凝縮されている。
「本当の意味で、でけぇ背中を見せられるような人になりたい。自分の後ろ姿を見たときに、男としても、人としても、『あの人についていきたい』『大きい背中だな』って思ってもらえるような存在になりたい」
そう語りながら、ある写真を取り出しこちらに見せてくれた。

「口で言わなくても、俺の後ろ姿を見た人が『大きい人だね』『大きい男だね』『どっしり構えているな』って思ってもらえたらいいんだよね」
さらに次々と自身の後ろ姿の写真を見せていく。
「俺って、すごく背中の写真が多いんだよね。これとか。背中、背中、背中……もう背中ばっか」
そして最後は真剣な眼差しで、こう締めくくった。
「人として、本当に“大きい人”っていうのを背中で体現できるようになりたい。自分が器のでかい人間だと思うんじゃなくて、周りの人がそう言って評価してくれたら、それが頂点なんだと思う。俺は、後ろ姿がかっこいい人になりたい」

“真面目に、謙虚に、ひたむきに”
まず、人としてどうあるべきか。その問いに向き合い続けてきたからこそ、サッカー選手・積田景介がいる。その背中はこれからも、見る者を惹きつけてやまない。
取材・文 :西元 舞
写真 :福冨 倖希
企画・構成:斎藤 兼、畑間 直英
UNSTOPPABLES バックナンバー
#1 渋谷を背負う責任と喜び。「土田のおかげでJリーグに上がれた」と言われるためにーー土田直輝
#2 頂点を目指す、不屈の覚悟。全ては世界一の男になるための手段ーー水野智大
#3 冷静さの奥に潜む、確かな自信。「自分がやってきたことを発揮するだけ、『去年と変わった』と思わせるために」ーー木村壮宏
#4 這い上がる本能と泥臭さ。サムライブルーに狙いを定める渋谷の捕食者ーー伊藤雄教
#5 問いかける人生、答え続ける生き様。「波乱万丈な方へ向かっていく。それがむしろ面白い」ーー坪川潤之
#6 サッカーが導く人生と結ぶ絆。ボールがくれた縁を、これからも。ーー岩沼俊介
#7 楽しむことを強さに変えて。夢も、欲も、まっすぐに。ーー小沼樹輝
#8 誰かのために、笑顔のために。誇りと優しさが生む頂点とはーー渡邉尚樹
#9 九州で生まれた男の背骨。「やっぱり男は背中で語る」ーー本田憲弥
#10 選手として、父として。見られる過去より、魅せたい現在地ーー渡邉千真
#11 余裕を求めて、動き続ける。模索の先にある理想へーー宮坂拓海
#12 この愛に、嘘はない。激情と背中で示す覚悟の真意とはーー鈴木友也
#13 憧れた側から憧れられる側へ。ひたむきな努力が導く、まっすぐな未来ーー大越寛人
#14 楽しいだけじゃダメなのか?渋谷イチの苦労人が語る「俺は苦しみに慣れちゃってる可能性がある」ーー高島康四郎
#15 かつて自分も”そっち側”だったからこそ、わかる。「もう誰のことも置いていきたくない」ーー志村滉
#16 絶対の自信を纏う、超こだわり屋のラッキーボーイ「必ず俺のところに転がってくる。そう思ってるし、信じてる」ーー青木友佑
#17 SHIBUYA CITY FCに人生を懸けた男「俺をこんなにも好きにさせた、このクラブが悪い!」ーー植松亮
#18 絶対に壊されたくない、やっと思い出せた楽しさ「副キャプテンを降ろさせられるんだったら、それでもいい」ーー楠美圭史
#19 器用貧乏?いや、今は違う「俺の中に神様はもういない」ーー青木竣
#20 考えたからこそ、”あえて”何も考えない「今日もやっちゃおーよ」ーー小関陽星
#21 どんな場所でも、俺はここで貫く「納得いかないことに対しても、納得いくまでやり続ける」ーー佐藤蒼太
#22 渋谷で語る、再びの覚悟とサッカー人生の答え「僕は恵まれている。もう、それしか言えない」ーー吉永 昇偉
#23 フェイクじゃ終われない「もっと突き詰めていれば…」吹っ切れた先に見えた景色ーー河波 櫻士
SHIBUYA CITY FC
渋谷からJリーグを目指すサッカークラブ。「PLAYNEW & SCRAMBLE」を理念に掲げ、渋谷の多様性を活かした新しく遊び心のあるピッチ内外の活動で、これまでにないクリエイティブなサッカークラブ創りを標榜している。
渋谷駅周辺6会場をジャックした都市型サッカーフェス「FOOTBALL JAM」や官民共同の地域貢献オープンイノベーションプロジェクト「渋谷をつなげる30人」の主宰、千駄ヶ谷コミュニティセンターの指定管理事業など、渋谷区での地域事業活動も多く実施している。
お問い合わせ
担当:畑間
問い合わせはこちら