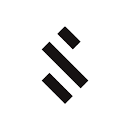「自分の情熱を捧げられる仕事に」父からの�教えを胸に、10年前に芽生えた夢を追いかける22歳「それが達成できたらもう、死んでもいいくらい」ーー 角野天笙(主務)【UNSTOPPABLES】 #27
2025年12月19日
|
Article
今シーズンのチームスローガン「WE WON’T STOP」にちなんでスタートした本企画。これまで26名の選手の歩みを追い、彼らが前へ進み続ける人生にスポットを当ててきたが、「止まらない」のは選手に限った話ではない。その裏側には、クラブの前進を支える大きな力となっている者たちがいる。
彼らの働きなしにチームは回らない。渋谷というクラブをもう一つの視点から捉えるために、その裏側へと踏み込んでいこう。
【UNSTOPPABLES~止められない奴ら~】
昨シーズン、関東2部への昇格を決めたSHIBUYA CITY FC。その栄光の背後には、ただの勝利以上のものが隠されていた。選手たちの揺るぎない自信と勢いは、彼らの人生に深く刻まれた歩みから来ている。勝利への執念、それを支える信条。止まることを知らない、彼らの真の姿が、今明らかになる。
第27回は、今年で22歳を迎えた主務の角野天笙。華やかな舞台の裏で地道に戦うこの仕事をなぜ志したのか。そしてその原動力はどこにあるのか。渋谷を支える喜びと、ひたむきに挑戦し続ける展望に迫る。
角野天笙(すみの・てんしょう)/ 主務
2003年10月14日生まれ。東京都品川区出身。立正大学経営学部経営学科所属。現在大学4年。2024シーズンからSHIBUYA CITY FCインターンとして副務の仕事を始める。今季からは主務としてチームの最前線に立ち、日々選手やスタッフを支えている。
10年前に宣言した夢
現在、渋谷にはひとりの若きチームマネージャーがいる。昨年、学生インターンとしてチームに加わった角野天笙だ。「天笙(てんしょう)」という名前にちなんで、選手やスタッフからは「てんてん」という愛称で親しまれている。
性格は明るく、人懐っこい。初対面でも臆さず距離を縮められるタイプで、普段はどこかマイペースな一面もある。あくまで立場はインターンだが、現場での判断力や選手へのサポートの質、そして何よりチームに対するまっすぐな熱量は目を引くものがある。
今年でマネージャー業は2年目となり、大学卒業と同時にチームを離れる予定だ。すっかり「渋谷のマネージャー」として定着したその姿を来季からは見なくなると思うと、寂しさを覚える人も多いだろう。

今でこそチームのためにサポート役に徹する姿が際立つが、そんな彼にも選手としての時代があった。小学3年から高校卒業までプレーしたが、突出した技術もなければ所属チームが強豪だったわけでもない。サッカーを始めた者なら大概は憧れるであろうプロ選手への夢も、「当時は内向的な性格だった」と語る彼の場合は小学6年の時点で早々に諦めた。
だが、そこでサッカーへの熱が冷めたわけではない。むしろ周囲の同級生とは少し違う形で、この競技に惹かれ続けていった。
思い返せば、今から10年前の小学校の卒業式。壇上で卒業証書を受け取る際、角野を含む卒業生たちは全校生徒と保護者の前で一人ずつ「将来の夢」を宣言する決まりがあった。そこで12歳の角野少年が迷わず口にしたのは、プロサッカー選手でもなければ、子供たちが憧れる人気の職業でもない。
「Jリーグのスタッフになること」だった。
「良くも悪くも現実的だったんです。選手としては無理だけど、サッカーに関わる仕事がしたいなとずっと思ってました。自分の好きな(川崎)フロンターレの試合に行くときも、ウォーミングアップで選手を見るのはもちろんなんですけど、そこでボールを受けているマネージャーやコーチのことも見ていて。ああいう人たちがすごくかっこよく映っていたんです」
ピッチで輝くスターのプレーに胸を踊らされながらも、自然と視線が奪われるのは“選手ではない人たち”。ピッチ脇でボトルを並べ、準備や片付けを抜かりなくこなす。そんな姿にことごとく魅了されていた。
「めっちゃ変わっていますよね、今考えると」照れくさそうに笑うが、そこで抱いた思いこそが角野の原点だった。10年の時が経っても変わらない、目指すべき場所である。
即断即決に踏み切った一本の動画
高校卒業後はスポーツの専門学校や医療系の大学でトレーナーを目指すことも視野に入れたが、「万が一道が狭まってしまったときのことも考えて」という親からの助言もあり、エスカレーター式で立正大学に進学。
強豪である大学のサッカー部でマネージャーになることも考えたが、サッカー部の練習拠点は埼玉県の熊谷キャンパスにあり、自宅からは片道2時間半ほど要する。それを大学4年間続けるという現実的な負担を考えれば、入部は断念せざるを得なかった。
それでも、サッカーに違う形でも関わり続けたいという思いから、大学1年の頃にコナミスポーツクラブでスクールコーチのアルバイトを始めた。実はここ、彼がサッカーを始めた小学3年から2年間通っていたクラブでもある。
月日が経ち当時の恩師はいなかったが、増嶋竜也監督の市立船橋高校時代の後輩が、コーチの一人として在籍していたという。のちに渋谷で活動することになったことを思えば、渋谷とは不思議な縁を感じさせるものがある。

大学3年に差しかかった頃には徐々に就職活動が現実味を帯び始め、将来について考え始めるようになった。
そこでスポーツクラブでの経験をさらに積むべく、インターネットで最初に見つけたのが渋谷のインターン募集だった。自宅から渋谷までは約20分という通いやすさにも魅力を感じたが、決め手は別にあった。
サッカーを始めたのと同時期に川崎フロンターレの虜になったという角野は、クラブ公式YouTubeチャンネルで公開されている「【卒業後の今に密着】”vol.2 田中裕介” 人の心を動かすって結局人だと思う。」という動画を見つけた。かつて川崎でプレーし、現在は渋谷のスポーツダイレクターを務める田中裕介の生活に密着するという内容だ。
「あの動画を見て『裕介さんって、いまこんなことしているんだ』って驚きました。翔さん(小泉翔 / 代表取締役CEO)や(植松)亮くんの姿も映っていて、この動画のおかげで渋谷のことを深く知れたんです。
なのでインターンの募集を見つけたときはすぐに応募しました。誰にも相談せずポチッて。ホームページやSNSを見てもシンプルでかっこいいし、そのころちょうど(渡邉)千真さんを補強していたのでチームの勢いもすごかった。『絶対にこれから強くなるでしょ』っていうワクワク感を持って応募しました」
こうして昨年の4月下旬に迷うことなく応募し、のちに面談を受けることになるが、その過程には彼ならではのこんな裏話があった。
「服装自由って書いてあったので、普通に私服で行こうとしたら、親に『ダメだよ』ってめっちゃ怒られて。面談前日の夜に、閉店間際のイオンに連れていかされてリクルートスーツを買ったっていう(笑)。自分以外の他のインターンはみんな私服だったらしいんですけどね。
そしたら翼さん(酒井翼 / 取締役・セールスダイレクター)に『めっちゃ真面目じゃん』って笑われたのをいまでも覚えてます。それが渋谷での第一歩です。やっとスーツを買ったことで『ついに就活が始まるんだな』って実感も湧きました」
「ついていくだけで精一杯」
無事に選考を通過した角野は、4月末に渋谷区スポーツセンターで行われた2024シーズン最初のホームゲームで、インターンの体験活動に参加。のちに、全社(全国社会人サッカー選手権大会)予選を控えた5月下旬、ついに正式なマネージャーとしてチーム練習へ合流した。
「ホームゲームはお祭り感があって会場もワイワイしてたけど、練習は良い意味でピリピリしてたのでめっちゃ緊張しました。その頃はまだファンの心が残っていたので、そこで千真さんや沼さん(岩沼俊介)、増嶋監督を見て、『うわ、すげえ!本物やん!』って驚いたのを覚えています。他の選手もみんな大きいし、髪を染めたりパーマをかけていたのでめっちゃ怖かったです。
でも一番最初にツミくん(積田景介)が『サッカーは好きなの?』『将来はこういうこと(マネージャー)をしたいの?』ってめっちゃ優しく話しかけてくれて。『選手としては全然上手くないから、裏方で関わりたいです』って返したら、『好きな気持ちが大事だから、一緒に頑張ろう』って言ってくれたんです。『超いい人やん、神だわ!』って思いましたね(笑)」

そうして期待を胸に膨らませながら、念願の新しい世界への一歩を踏み出した。だが、これまで部活動などでのマネージャー経験がなかった彼にとって、右も左も分からない状況が続く。
「もう、ついていくだけで精一杯でした。他にマネージャーが3人もいたので、正直、自分がいなくても仕事が回っていたんです。だから逆に何をすればいいのかわからなくて、そこは戸惑いましたね。でもその人たちが急に体調不良とかで欠けたりすると、みんなに任せきりにしていたぶん、自分が何もわかっていなくて『やばいやばい』って焦ったこともあります」
それでも徐々に現場の流れは掴めるようになっていったが、自分の仕事ぶりに自信を持てるようになるまでには一年を要した。シーズンが終わるまで、一つひとつの動作に迷いがあり、たとえ正解だとされる行動にも選手のリズムを乱してしまわないか不安がつきまとった。
「例えば『このタイミングでボトルを片付けていいのか』『ここに置いて大丈夫なのか』とか。一個一個の細かいところまでめっちゃ気にしていましたね。練習の緊張感もあったので、選手に話しかけるのでさえ戸惑いましたし。それこそ最初は選手の名前も、スタッフが何をしているのかもわからない状態だったので。トレーナーなのかコーチなのか、この人がどういう立場なのか、誰に聞くべきなのかわからず大変でした」
主体的に動けていない実感。チームの一員として任されているはずなのに、どこか“手伝っているだけ”のように感じてしまう自分。
そうこうしているうちに気づけば時間だけが進み、チームは悲願の関東昇格を果たすが、その歓喜の場にいながら、彼の中にはどうしても拭いきれない思いが残っていた。
2年目の大きな変化。すべては「チームのために」
大学4年に上がり、マネージャー業2年目を迎えた今シーズン。これまでは大学の授業との兼ね合いで週に3日の活動にとどまっていたが、週5日と増やせるようになり、チームに完全にコミットできる状態になった。役職も「副務」から「主務」に変わったことも大きな変化だ。
さらに昨季まで在籍していたマネージャーが大学卒業を機にチームを離れたことで、求められる仕事量は「(極端に言うと)0から100」に増えたという。練習や試合での準備や片付け、ピッチでのサポートといった日常業務に加えて、練習場の確保、練習試合前には相手チームとの日程調整も行った。
秋以降は練習生の受け入れ対応も担い、練習生用のウェアの準備から代理人や監督とのやり取りまで担当し、業務の幅は一気に広がった。

「選手から『こうしてほしい』っていうLINEも来れば、スタッフからも来るので連絡は鳴り止まないです。だから練習後に家に帰って昼寝とかしてたら、LINEが溜まってるときがあるのでなかなか気が抜けないですね。
最初シーズンが始まった時は楽しい気持ちのほうが大きかったんですけど、実際は想像以上に大変でした。ストレスでめっちゃ肌荒れしましたもん。トモくん(水野智大)や(高島)康四郎くんからは、『なんか最近疲れてない?』『元気なくない?』って心配されて恥ずかしかったです(笑)」
常にチームのことを考えざるを得ない慌ただしい毎日だが、昨年の自分と比べれば、顔つきも立ち振る舞いも明らかに変わったと自覚している。なぜならば、そう言い切れるだけの努力をしてきたからだ。
不安や迷いを消す一番の方法は、結局のところ現場で経験値を積むこと以外にないと気づいてからは、考え方を切り替えられるようになった。
「昨シーズンが終わる1か月前くらいから、『今シーズンはいっぱい失敗して、たくさん見て学ぼう』って強く意識し始めたんです。怒られてもいいやじゃないけど、どんどん自分でやって、もしダメでも修正するだけ。『まずはやってみよう精神』が強くなりました。何でもやってみないと始まらないので。
それこそ最初の頃は余裕がなかったんですけど、だんだんと仕事に慣れてきて見栄え的にも雰囲気的にも『余裕を持つこと』を心掛けました。やっぱりマネージャーがバタバタしていると、選手は不安に思うしお願いもしにくいので。仕事がたくさんあるときは他のスタッフとしっかり分担をして効率を考えるようになったし、全部自分だけでやる必要はないと割り切れるようになりました。そこは本当に成長しましたね。

あとはやっぱりコミュニケーション力も向上しました。年上にはリスペクトを持ちつつも、ビビらずに自分の意見をはっきり伝える。気になることがあれば遠慮せずにガツガツ聞く。こうして自主性が伸びたのは、『自然と場数を踏むしかない』と思ったからです。
練習中にボトルの置き場でマスさん(増嶋監督)に指摘を受けることもありました。広がったメニューのとき、本来ならボトルを各スポットに置けば選手はすぐ飲めますけど、マスさんは選手同士でコミュニケーションを取らせるために一か所に置いてほしいというこだわりがあるので、それを尊重してやってました。選手からは『ちょっと遠い』って言われたけど、そこもうまくなだめたり(笑)」
最初は何もかもわからなかった「初心者」の状態から、いまとなっては選手やスタッフの細かな要望やこだわりにも応えられるようになった。「勉強は苦手」というが、トレーニングウェアやスパイクなどの道具が誰のものなのか、そしてドリンク一つとっても、選手それぞれの好みを把握している。
「(鈴木)友也くんは粉を2杯半入れるとか、(植松)亮くんは夏場は氷を入れない、(青木)友佑はシェイカーのドリンクを足さなくてもいいとか。(小関)陽星くんは心配性だからか、4割くらい残っている状態でも入れてほしいって思うタイプなので、なくなったらすぐに足すようにしました。
逆に(楠美)圭史くんやコシくん(大越寛人)は1杯飲んだらもういらないタイプなので、それ以上は足さないようにしましたね」

もちろんこれは一朝一夕で身についたものではなく、日々のコミュニケーションや観察の積み重ねがあってこそ。現場外での努力も欠かさず、YouTubeで他クラブが公開しているマネージャーやホぺイロの密着動画を片っ端から何度も繰り返し視聴したという。
次のメニューを想定しながら、ボトルやボールの位置まで細かく意図をもって配置する。プロの現場で当たり前に行われている準備や立ち回りを自分なりに噛み砕くことで、日々の仕事の質は確実に高まっていった。
「なるべく事前に練習メニューを聞いて選手の動線を考えるように意識するようになりました。一つのメニューが何セットで終わるかまで把握しておきたいんです。メニューが終わりそうなタイミングでボトルやボールを先に移動させておけば、選手は次のメニューの説明を聞きながら飲めるので。
だから練習中にマスさん(増嶋監督)にボソッと『もうすぐこれ終わりますか?』って聞いて、ボールを半分ぐらい次のメニュー場所に持っていく、みたいなことをやっていました。もしそれが聞けなくても、1セット目の時間を自分で測れば大体の流れは読めます。例えば6分で終わるなら、最初の5分はボールを拾いをして、ラスト1分はボトルのところに行ってすぐに渡せるように準備しておく。そしたら意外とうまくいって、その時はめっちゃ気持ちよかったです」
他にもInstagramやXといったSNSでは、各クラブのスタッフが投稿しているロッカールームの写真や備品の並べ方を参考にして、使えそうな点はそのまま業務に落とし込んでいった。
「こういう写真を見ると、やっぱりプロってすごいなって思います。めっちゃ綺麗だし、憧れますね。マジで気持ち悪いぐらいチェックしてます。ストーカーなんじゃないかってくらい(笑)。JクラブのINSIDE CAMの動画も見て、マネージャーさんとか裏方の人が一瞬映るときがあるので、『あの人いた!』って気づくくらいには見てますよ。
あとは何より自分も選手としての経験があったからこそ、覚えるのが早かったんだと思いますし、昔からフロンターレの選手を見てて『この人はこのスパイクを履いてる』っていうのを勝手に覚えてたので、研ぎ澄まされたのかもしれないです。自分の好きなことは勝手に覚えられるようになっちゃいますね。そういう感覚は大事にしてます」
いつもニコニコしている可愛らしい印象とは裏腹に、その根底には「チームのために」自分が何をできるか考え続ける胆力と覚悟がある。日々試行錯誤するその姿勢は、彼が大切にしてきたポリシーそのものだ。

「選手、スタッフがストレスのないような場を作る。とにかくそこだけです。自分を犠牲にしてでも、時間を費やしてでも、選手がやりやすく。LINEの文章ひとつにしても、簡潔にわかりやすく。とにかく選手にストレスがかからないようにピッチ内外で意識しています。
連絡ひとつにしてもこだわってるのは、 毎回練習前日にグラウンド場所のアナウンスをグループラインでするんですけど、16時ごろに送ると選手はまだ仕事中で気が散るかもしれないし、逆にお昼頃に送っても夜になったら『どこだったっけ』って忘れちゃうかもしれない。だからあえて仕事が落ち着く19時以降に送っています。
あと一時期やってたのはそのアナウンスと一緒に『明日も頑張りましょう』って一言つけたり(笑)。でも意外とリアクションがなかったので、これはあんまり意味がないんだなと思ってやめました。でも、これも『挑戦して修正』です。チームのために、とにかく徹します」
こうした細部にまで及ぶ改善の積み重ねの先に「ベストゲームでした」と言い切れる手応えを得られたのが、今季のEDO ALL UNITED戦だった。負ければ相手のリーグ優勝が決まる瀬戸際の一戦。張り詰めた緊張感のなかでも、ロッカールームでのセッティングの準備段階から、選手に余計な負担を一切かけない環境をつくり上げることに成功したという。
「しっかり(ロッカールームに)スムーズに入れて、その日は特に選手に対して『申し訳ないな』って思うこともなかったんです。『そこにボトル置いてなかったか』『ケア用品をちょっと遠いところに置いちゃったな』とか。自分なりに気にしたところがうまくいかなかったときは申し訳ないけど、EDO戦はそれがなかったんです。
そのぐらい自分もあの試合にめっちゃ懸けてたし、EDOの優勝は見たくなかった。余談ですけど、試合前に会場の最寄りのコメダ珈琲で浦和さん(浦和史哉 / チーフトレーナー)と一緒にお腹パンパンになるぐらいまで食べたのも良い思い出です。『これ勝ったな』『準備完了だわ』って言って(笑)。
だから勝った瞬間は自然とマスさん(増嶋監督)に抱きついてました。体が勝手に動いちゃいましたね。そしたらメンバー外の選手たちも来て、みんなで輪になった時にめっちゃ泣きました。正直、記憶にないくらい熱くなってましたから」
「普通は試合中にこんなに前に出ることないですからね」と自覚するその一枚は、理性では抑えられない衝動がそのまま映し出されていた。

愛するチームと夢のために
ここまで語られたマネージャーとしての道のりは、数字にすればわずか2年。その歴の短さゆえに本人は「まだまだです」と口にするが、経験の短さを理由に語れる時間ではないだろう。彼にとっても、そしてチームにとっても濃い2年であり、自分の課題や伸びしろはことさらにある。さらに実りのあるものへと変えていくためにも、いまこそ新たな船出に出るときだ。
当然、その一歩に迷いがないわけではない。新卒で挑むのなら、この先に待つ世界は決して甘くない。そもそも枠が空く保証すらないうえに、日々の多忙さは避けられず、自分の人生そのものを差し出す覚悟が求められる。
まずは一般企業に就職し、安定した基盤を得てから夢を追うべきなのか。現実的な選択肢が頭をよぎるたびに、自分のなかで天秤が揺れることも何度もあった。
そんな悩みに悩める彼の背中を、そっと押したのが父親の存在だった。地元で「立呑み8」という居酒屋で店長をしているという父は、もともとは会社員として働いていたが、夢を追うために仕事を辞め飲食の道へ飛び込んだ、いわゆる「脱サラ」というやつだ。
その道が平坦でなかったことは、実の息子が一番よく知っている。休日でも新メニューの試作に没頭し、夜中に寝ているときでさえ仕入先からの電話に飛び起きる。常に店のことを考え、働き続ける父の姿を見て何も感じないはずがない。それでも覚悟を持って舵を切り、自分の人生を全うする背中をずっと側で見てきた。
「前にお父さんと二人で飲みに行った時に、『自分の情熱を捧げる仕事にした方がいいよ』って言われたんです。『大変だけど仕事はめちゃくちゃ楽しい』って、目を輝かせて言うんですよ。すごく説得力があるし、俺もそうなりたいなって。だからもし普通に就職したら、ずっと(夢が)チラついちゃうと思います」
最終的に情熱を選んだ偉大な姿を見てきたからこそ、“どう生きたいか”の答えは揺るがなかった。そうであれば、なるべき姿、ありたい姿はもう定まっている。突き進むしかないのだ。

「前に赤井さん(赤井寛之 / アスレチックトレーナー・フィジオセラピスト)が、レイソル時代にカップ戦で優勝したときのことを『あれはマジで最高だったね』って言ってて。その話をしている赤井さんがめちゃくちゃ笑顔で幸せな顔してて、それがすごくいいなと思って。
だから俺もJリーグのマネージャーになって優勝したい。将来自分がどこのチームにいるかわからないけど、天皇杯の決勝やリーグ優勝のような記念すべき大きな舞台に、友達や家族を招待したいです。それが達成できたらもう、死んでもいいくらいです。今までやってきた意味が報われる気がするので」
掲げる目標は大きいが、そうなってほしいと思わせるだけの情熱と真摯さがある。温厚なトーンの語り口から突き出た野心がそれを証明していた。
企画名にちなんだ「誰にも止められない瞬間」を尋ねたときにも、その思いがそのまま回答として返ってきた。
「やっぱりグラウンドにいる時間かな。物理的にもずっとグラウンドで走り回っているし、気持ち的にも他のことを考える余裕もないし、考えないようにしています。練習の2時間もめっちゃ楽しいし、やっぱり自分が一番夢中になれて楽しいのはこの瞬間なんです。
本当に、選手が楽しそうに練習とかサッカーをしてくれたら、それだけでいいんです。ロンドひとつにしても楽しそうにやってくれたらそれで嬉しいし、よかったなって安心できる。Jから移籍してきた選手とかが、カテゴリーや環境が全く違う中でも楽しそうにプレーしてくれたら安心できるんです。選手が楽しそうにやってくれたらもういいかな、みたいな。
なので、練習後は一人で帰ることが多いんですけど、みんなで一緒だったあとに急に静かになるから、その瞬間はなぜか急に寂しくなったりします(笑)いつも選手のこと、スタッフのこと、チームのことを考えていますよ」

欲深いほど夢に対して貪欲で、叶えるためにいま何をすべきかを迷わない。夢に対しても、人に対しても、そして何より自分の仕事に忠実であろうとする。経験の大小では測れない「誠実さ」が彼の最大の魅力なのだろう。
そういう人物だからこそ、最後にどうしても聞きたくなったことがある。少しばかり誘導質問のようになってしまったことは否めないが、それでも確かめずにはいられなかった。
「渋谷に戻ってくる気持ちはあるか?」と。
返ってきた言葉に迷いはない。
「そうですね。いつか渋谷に戻りたいです。冗談かもしれないんですけど、前に(田中)裕介さんが『渋谷が強くなってきた時に帰ってきなよ』って言ってくれて。それがすごく嬉しかったです。自分も成長して、渋谷も大きくなって、ここに帰ってきたいです」
愛するクラブの成長速度に負けないように、彼自身も歩みを止めるつもりはない。一時は渋谷を離れるが、どこのクラブへ身を移したとしてもその忠誠心は変わらないだろう。彼自身が加えるプラスアルファの力は必ずチームの底力になる。

いつしか渋谷が大きなスタジアムで喝采を浴びているとき。ふとピッチの外へ視線を向けてみてほしい。チームを支える見慣れた姿がきっとそこにあるはずだ。
取材・文 :西元 舞
写真 :福冨 倖希
企画・構成:斎藤 兼、畑間 直英
UNSTOPPABLES バックナンバー
#1 渋谷を背負う責任と喜び。「土田のおかげでJリーグに上がれた」と言われるためにーー土田直輝
#2 頂点を目指す、不屈の覚悟。全ては世界一の男になるための手段ーー水野智大
#3 冷静さの奥に潜む、確かな自信。「自分がやってきたことを発揮するだけ、『去年と変わった』と思わせるために」ーー木村壮宏
#4 這い上がる本能と泥臭さ。サムライブルーに狙いを定める渋谷の捕食者ーー伊藤雄教
#5 問いかける人生、答え続ける生き様。「波乱万丈な方へ向かっていく。それがむしろ面白い」ーー坪川潤之
#6 サッカーが導く人生と結ぶ絆。ボールがくれた縁を、これからも。ーー岩沼俊介
#7 楽しむことを強さに変えて。夢も、欲も、まっすぐに。ーー小沼樹輝
#8 誰かのために、笑顔のために。誇りと優しさが生む頂点とはーー渡邉尚樹
#9 九州で生まれた男の背骨。「やっぱり男は背中で語る」ーー本田憲弥
#10 選手として、父として。見られる過去より、魅せたい現在地ーー渡邉千真
#11 余裕を求めて、動き続ける。模索の先にある理想へーー宮坂拓海
#12 この愛に、嘘はない。激情と背中で示す覚悟の真意とはーー鈴木友也
#13 憧れた側から憧れられる側へ。ひたむきな努力が導く、まっすぐな未来ーー大越寛人
#14 楽しいだけじゃダメなのか?渋谷イチの苦労人が語る「俺は苦しみに慣れちゃってる可能性がある」ーー高島康四郎
#15 かつて自分も”そっち側”だったからこそ、わかる。「もう誰のことも置いていきたくない」ーー志村滉
#16 絶対の自信を纏う、超こだわり屋のラッキーボーイ「必ず俺のところに転がってくる。そう思ってるし、信じてる」ーー青木友佑
#17 SHIBUYA CITY FCに人生を懸けた男「俺をこんなにも好きにさせた、このクラブが悪い!」ーー植松亮
#18 絶対に壊されたくない、やっと思い出せた楽しさ「副キャプテンを降ろさせられるんだったら、それでもいい」ーー楠美圭史
#19 器用貧乏?いや、今は違う「俺の中に神様はもういない」ーー青木竣
#20 考えたからこそ、”あえて”何も考えない「今日もやっちゃおーよ」ーー小関陽星
#21 どんな場所でも、俺はここで貫く「納得いかないことに対しても、納得いくまでやり続ける」ーー佐藤蒼太
#22 渋谷で語る、再びの覚悟とサッカー人生の答え「僕は恵まれている。もう、それしか言えない」ーー吉永 昇偉
#23 フェイクじゃ終われない「もっと突き詰めていれば…」吹っ切れた先に見えた景色ーー河波 櫻士
#24 人として在るべきために、追い求める理想像「本当の意味で、“大きい人”に」ーー積田 景介
#25 「俺が」決める。数奇な29年を経て、背番号9が背負う矜持「もう覚悟は決まっている」ーー政森宗治
#26 人生を変える覚悟を胸に。背番号10を背負う渋谷のニューヒーロー「まだまだこれから」ーー宮川瑞希
SHIBUYA CITY FC
渋谷からJリーグを目指すサッカークラブ。「PLAYNEW & SCRAMBLE」を理念に掲げ、渋谷の多様性を活かした新しく遊び心のあるピッチ内外の活動で、これまでにないクリエイティブなサッカークラブ創りを標榜している。
渋谷駅周辺6会場をジャックした都市型サッカーフェス「FOOTBALL JAM」や官民共同の地域貢献オープンイノベーションプロジェクト「渋谷をつなげる30人」の主宰、千駄ヶ谷コミュニティセンターの指定管理事業など、渋谷区での地域事業活動も多く実施している。
お問い合わせ
担当:畑間
問い合わせはこちら